Coffee Break<週刊「世界と日本」2297号より>
爽風エッセイ
食のまち大阪 ―しょう油の魔術―
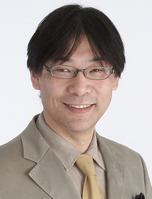
元大阪府教育庁文化財保護課・考古学者
西川 寿勝氏
大阪・関西万博が開幕し、会場は盛り上がりをみせています。日本にいながら世界の文化や食に触れられることはもちろん、10年先、20年先の未来を見据えた最新技術を披露するパビリオンが数多く出展しています。経済産業省が主管する万博最大規模のパビリオン、日本館もそのひとつ、眼には見えない微生物や藻類(そうるい)が主なテーマです。エネルギーやゴミなど、未来の循環型社会を語るのみならず、伝統的なコウジ菌の発酵による味噌・しょう油・日本酒が、多様な味や風味をかもすことも語られます。
万博に限らず、外国人観光客が急増する昨今、日本の食文化への関心が高まっています。2013年には和食(日本人の伝統的な食文化)がユネスコ世界遺産委員会に無形文化遺産登録されました。また、全国各地の和食文化が文化庁の日本遺産に認められ、振興や保護継承が応援されています。
和食の担い手の一つにしょう油があります。醤(ひしお)と呼ばれた肉・魚・穀物を塩で漬け込む保存食が源流です。紀元前3世紀の中国で、穀物を使った発酵調味料、豆醤(トウジャン)が生まれ、朝鮮半島経由で、飛鳥・奈良時代に日本へと伝わりました。奈良の平城宮跡からは「醤」を記す納税の木簡が多数出土しています。
これとは別に、鎌倉時代の禅僧がコウジ菌によって味噌から抽出した調味料が、現在のしょう油の起源という見方が有力です。和歌山県由良町にいた禅僧の覚心(かくしん)が、中国の径山寺(きんざんじ)から持ち帰った味噌をもとに径山寺味噌を製造しました。このとき偶然流れ出た液体がとても美味しかったので、液体調味料としてのしょう油が見いだされました。大豆と麦を日本のコウジ菌で発酵させ、搾るという製法です。現在の濃口しょう油に通じます。濃口しょう油は江戸時代には和歌山のみならず、千葉の銚子や野田などにも製法が伝わり、それぞれの環境に生息するコウジ菌を使って成立しました。関東・東北では今でも濃口しょう油が好まれます。
一方関西では、塩づくりが盛んだった大阪湾岸や瀬戸内で、薄口しょう油が生まれます。淡口(うすくち)とも書きます。色は淡くても香りや「にがり」がしっかりし、京料理や煮物などに適した調味料です。薄口しょう油は、出汁と調和することが重視され、繊細な和食の味を引き立てる大切な存在です。江戸時代、しょう油業は味噌・酒とあわせて製造、糀屋(こうじや)と呼ばれました。大阪では、三味一体の糀屋が数多く軒を連ね、和食の味や風味を決定づけることとなったのです。しかしながら濃口しょう油も、のちにすき焼きや醤油ラーメンを爆発的にヒットさせました。新たな日本の食文化の道をひらいたのです。
明治時代以降、しょう油は工業生産へと移行します。関東では野田しょう油のキッコーマン、銚子しょう油のヤマサやヒゲタ、関西では和歌山の湯浅醤油などが全国流通を担う一方、各地の小規模蔵元も地元の環境に根付いたコウジ菌で伝統の味を守り続けます。薄口しょう油のヒガシマル、長期熟成が特徴の小豆島マルキンなどです。
現在、しょう油は日本の代表的な発酵食品として輸出され、世界中でソイ・ソースと呼ばれ重宝されています。昨年のしょう油輸出量は約5万㌧にのぼり、前年比21%の増加でした。











