2025年の政治、世界経済は波乱が続きます。それでも日本は景気拡大持続へ。それぞれの専門分野で、深く丁寧に将来を見通します。
2025年5月5日号 週刊「世界と日本」2292号 より
政治家を評価することは容易ではない
同志社大学法学部教授
村田 晃嗣 氏

《むらた こうじ》
1964年、神戸市生まれ。同志社大学法学部卒業、米国ジョージ・ワシントン大学留学を経て、神戸大学大学院博士課程修了。博士(政治学)。広島大学専任講師、助教授、同志社大学助教授を経て、教授。この間、法学部長・法学研究科長、学長を歴任。現職。専攻はアメリカ外交、安全保障研究。サントリー学芸賞、吉田茂賞などを受賞。『大統領たちの五〇年史』(新潮選書)など著書多数。
トランプ劇場を巡る評価
「辞書の中で関税ほど美しい言葉はない」と、ドナルド・トランプ大統領は豪語してきた。
その「トランプ劇場」は、さながらジェット・コースターである。トランプ氏は就任早々から大統領令を乱発し、ついには関税カードを弄ぶようになった。改めて、「ニクソン・ショック」が想起されよう。1971年7月に、ニクソン大統領は金・ドル交換停止や10%の輸入課徴金などの新経済政策を発表し、8月には宿敵だった中国を翌年に訪問すると発表した。トランプ大統領がウクライナを見捨てて、ロシアとの大幅な関係改善を図れば、それこそ「ニクソン・ショック」の再来である。ただし、ヘンリー・キッシンジャー博士の知恵と戦略なしで。
さすがに、トランプ大統領の支持率も低下し、米国をはじめ世界の株価も下落している。ドルも米国債も、売りに出されている。すると、トランプ氏はイーロン・マスク氏と距離を置き、大統領3選に言及しはじめた。民主党にとっては、トランプを攻撃しても効果は乏しいが、今や、マスク氏は格好の攻撃対象なのである。先般も、この大富豪が巨費を投じながら、ウィスコンシン州最高裁判所判事の選挙で、民主党のリベラル派が勝利を収めた。
大統領3選はなるか。次の選挙でJ.D.ヴァンス副大統領が大統領候補になり、トランプ大統領が副大統領候補に回る。当選、就任後にヴァンス氏が辞任すれば、トランプ副大統領が大統領に昇格する。さすがに、米国の能天気な有権者も、保守化した連邦最高裁判所も、これは認めまい。むしろ、三選を仄めかさなければならないほど、トランプ政権にとって、1期限りという時間的な制約が大きいのである。とりわけ、来年11月の中間選挙で、共和党が連邦議会の多数を失えば、その後のトランプ政権は「死に体」(レイム・ダック)になってしまう。
石破茂首相は2月に訪米し、日米首脳会談を「成功」させた。だが、関税攻勢を前に、石破氏はなす術もない。むしろ、トランプ大統領は安倍晋三元首相の名前に言及した。トランプ大統領は「強い」リーダーが好きなのである。だから、習近平もウラジーミル・プーチンも、金正恩さえ好きである。強くなければ、トランプ氏と「取引」(ディール)しても、国内で実行できないかもしれない。もとより、安倍氏は独裁者ではなかったが、自公連立政権が衆議院で3分の2を超える多数を擁し、自民党内でも安倍派の議員が100人を超えていた。石破氏とは大違いである。
評価する側の見識も
振り返ってみて、安倍氏の最大の業績は平和安全法制を定めて、限定的とはいえ集団的自衛権の行使を可能にしたことであろう。トランプ大統領は今でも日米安全保障条約が不平等だと語っているのだから、この法制がなければ、日米関係は今よりかなり不安定になっていたであろう。トランプのアメリカはどうせ日本を守りはしない、だから大切なのは軍事力ではなく外交の力だと、ある識者が述べていた。なぜ軍事と外交が二者択一なのか。また、日米安保条約は信じないくせに外交力を説く―この程度の論理の飛躍や自己矛盾に気づかない「文化人」は、外交や安全保障の分野には不向きである。しかも、長らく有事法制に反対してきた人々が、日本の危機管理体制の不備を批判するのなど、実に噴飯ものである。平和安全法制については、数々の違憲訴訟が起こされたが、「憲法学者の多数意見」は司法の場でことごとく斥けられている。これを不満としてシールズが再びデモを展開したという話も、寡聞にして耳にしない。もうお忘れであろうか。シールズとは、「自由と民主主義のための学生緊急行動」なる団体のことである。彼らなしにも、立憲主義は立派に守られている。
健全な民主主義を育てる
他方で、安倍氏のロシア政策は、今となっては失敗だったと断ぜざるをえまい。おそらく、プーチン大統領に北方領土を部分的にも変換するつもりなど、まったくなかったであろう。また、いわゆるアベノミクスがどれほど成功したかについても、大いに意見が分かれよう。
わずか10年ほどで、政治家やその政策への評価は大きく変わりうる。荒唐無稽に見える「トランプ劇場」が、10年後、20年後には歴史の中で然るべき評価を受けているであろうか。それとも、決定的な「ぶち壊し屋」と断罪されていようか。そして、安倍氏や石破氏の評価はどうなっているか。
昨年末に、米国のジミー・カーター元大統領が100歳で死去した。人権外交を推進したカーター元大統領の人生は、ほとんどトランプ大統領の反語である。ジョー・バイデン前大統領も、カーター氏の人格を絶賛した。だが、そのカーター氏も、在職中には未熟、頑迷、軟弱と罵詈雑言を浴びせられ、再選は叶わなかった。われわれは政治家と政策を常に評価し、時には厳しく批判しなければならない。さもなければ、民主主義は守れない。しかし、自らの判断や評価を疑い見直す精神がなければ、健全な民主主義は育たない。左右を問わず、今日の政治に欠けているのは、この自己懐疑の精神であろう。
先ほど、トランプ大統領は「強い」リーダーを好むと述べた。当のトランプ氏には1期しかなく、しかも中間選挙で敗北する可能性が高い(おそらく下院で)。彼が「取引」しようとしても、実はプーチンも習近平も「弱い」トランプ政権を相手に、大きな政策変更をするつもりはあるまい。政治にとって、力や金よりも時間こそが貴重な資源なのである。だからこそ、独裁者は強い。
そしてもう一つ、政治にとって重要なのは知恵である。確かに、トランプ氏は政治的経験を増して、したたかに知恵をつけてきた。しかし、日本をはじめとする諸外国も、トランプ大統領とどう向き合うかの知恵を積んできたはずである。関税競争の背後で、トランプ大統領とわれわれの知恵比べが展開されようとしている。そして、集合知に乏しい分、長期の知恵比べでは、独裁者は脆い。自己懐疑の精神を欠き、諫言を退けるトランプ大統領にも、それは当てはまろう。
2025年4月21日号 週刊「世界と日本」2291号 より

《しおた うしお》
1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『昭和の教祖 安岡正篤』、『日本国憲法をつくった男 宰相幣原喜重郎』、『憲法政戦』、『密談の戦後史』、『内閣総理大臣の沖縄問題』、『危機の権力』、『解剖 日本維新の会』、『大阪政治攻防50年』。近著に『安全保障の戦後政治史』など著書多数。
3月31日に2025年度予算が成立し、翌4月1日、石破茂内閣が半年を超えた。
戦後80年、実質的な少数与党政権は、1955年の自民党結党の前の吉田茂内閣(第5次・約1年7カ月)と鳩山一郎内閣(約11カ月)、それと30年前の94年の羽田孜内閣(約2カ月)、現在の石破内閣の計4例だ。
少数与党政権で半年超の在任は70年ぶりである。石破首相は半年の政権担当を振り返って、誤算続きと受け止めているのか、計算どおりと見ているのか。
24年10月の「いきなり解散」による総選挙は、選挙後の11月に取材した森山裕自民党幹事長によれば、首相、幹事長とも、「負け戦覚悟での衆院選」という作戦だったと映る。
選挙後、国民民主党との政策協議方式での「自公国」3党体制、25年度予算に関する日本維新の会との協調路線の「自公維」3党体制と、綱渡りの与野党連携を繰り返し、24年度末にたどり着いた。
自民党内の反対勢力の石破降ろしの動きも何とか不発に押さえ込んだ。少数政権は野党の協力が不可避だが、反石破側には、現状では石破首相以上に野党の支持を得られる代替候補が見当たらないという弱点がある。
負け戦覚悟の首相側の深謀遠慮も効果的だった。超早期の衆院選だと、痛手は反石破勢力のほうが大きいと読み、首相自身は逆に新型自民党への転換の主役にと目論んだふしがあった。結果的に狙いどおりとなった。
結局、石破首相はこの半年、おおむね計算どおりと受け止め、この先、安全運転第一の政権運営で、最短でも7月の次期参院選までは政権継続、と踏んでいるのではないか。
そこまでで、政権をめぐる攻防戦は「①4月の衆議院解散と5月の衆院選、②連立組み替え、③石破降ろし成就による自民党総裁選、④会期末前の石破内閣不信任決議案の提出と可決による解散、⑤衆参同日選」の5つの場面が焦点となる。
この点について、首相は予算成立後の4月1日の記者会見で、③を除いて、「現在考えているものでは全くございません」と否定した。今後、何が飛び出すのか、予測不能の面はあるが、参院選まで「特別の仕掛けなし」で政権継続可能と判断したのだろう。③も、前述の党内事情を前提に、起こりそうにないと見たに違いない。
野党各党も「次の一手」で決定打を欠く。
立憲民主党には「内閣不信任案の提出・政権交代」というカードがあるが、参院選は相手が石破首相のほうが有利という計算から、不信任案可決による衆議院解散と衆参同日選は避けたいというのが本音で、及び腰だ。
維新も動きが鈍い。4月13日に開幕した大阪・関西万博が終わる10月までは、中央政界での政争への参戦は見合わせという空気だ。自民党との関係では、2月の取材で、共同代表の前原誠司氏、参議院議員会長の浅田均氏とも、「連立はない。それをやればわが党は消えてなくなる」と明言した。万博後は不明だが、現在はこれが基本路線である。
もう一つ、高人気の国民民主は、次の参院選での連続勝利が最重要目標で、参院選前の政変は視野にないと見る。独自路線で、与党とも他の野党とも距離を置く方針のようだ。
石破首相は国会会期中、政権強化の対野党工作などを自ら仕掛けたりせず、アメリカの関税政策よる経済悪化への対策、懸案の企業・団体献金問題、新しいテーマの「能動的サイバー防御」の関係法案、選択的夫婦別姓案など、重要課題に対処する構えである。
重大な失敗がなければ、政権は参院選まで持ちこたえる可能性が高い。石破交代も含めた政変は、参院選の結果次第という展開となりそうだ。
隠れた問題点は、安全運転第一の石破首相が賞味期限とならないかどうか。期限切れを招かないポイントとして、首相が自己認識すべき点が2つある。
第1は「実質的最高権力」の掌握だ。
表向きの形式的最高権力の保持者は、いうまでもなく首相だが、実質的に政権を左右する決定的な最高権力を時の首相が手にしているとは限らない。
「1強」だった第2期の安倍晋三首相はほぼ全期間、形式と実質の両面で最高権力を確保していたが、岸田文雄前首相は在任中、一度も実質的最高権力を手にできなかったのでは、と見た人が多かった。少数与党政権の石破首相も、もちろん現在、未掌握だ。
少数政党並存政治では、実質的最高権力は漂流状態となる場合が多い。その争奪についても、「1党支配」や「2大政党政治」「1強」とは本質的に異なる方程式が生まれる。
実質的最高権力の掌握も、新型リーダーとしての資質や発想、才腕が必要だが、その武器となるのが第2のポイントの「民意との結託」である。
一言で民意といっても、価値観が多様化した現代の日本社会では民意の把握、吸収、実現は簡単ではない。
注目の的は国民民主だ。衆院選で「手取りを増やす」「対決よりも解決」を叫び、特に39歳以下の若者層の強大な支持を獲得した。
経済の分野も含め、ミクロ政策での強力なアピールが推進力となっている感が強いが、玉木雄一郎代表はその点について、25年2月末の取材で、「わが党以上にマクロ経済政策を重視している党はない」と強調した。その姿勢は的を射ている。
少数政党が並存する「緩やかな多党政治」では、国民民主に限らず、各党とも、「民意との結託」はマクロ政策を含めた「大きな政治」が決め手となる。
個別の具体的な政策を取り上げる「小さな政治」も重要だが、政治・経済・社会などの将来像と達成のシナリオ、世界の中での日本の役割と使命など、立国の基本路線を軸とする「大きな政治」が民意の動向を左右する。
「大きな政治」で各党が民意の争奪戦を演じる流れになれば、政治大変動と政党大再編が現実となる。むしろ大変革後の新しい政党政治に期待したいが、もしかすると25年7月の参院選の直後、開演のベルが鳴り始めるかもしれない。
2025年4月7日号 週刊「世界と日本」2290号 より

《かわくぼ つよし》
1974年生まれ。東北大学大学院博士課程単位取得。専攻:日本思想史。現在、麗澤大学教授。論壇チャンネル「株式会社ことのは代表取締役」。主な著書に『福田恆存』(ミネルヴァ書房)、『方法としての国学』(共著、北樹出版)、『ハンドブック近代日本政治思想史』(共著、ミネルヴァ書房)、『日本思想史事典』(共著、丸善)など多数。
左翼全盛の中でインテリからの罵倒語に過ぎなかった「保守」が、今や人々の賞賛を受ける状況となっている。こうなると「保守」の看板の奪い合いも起こり、互いを似非保守と呼んで叩き合う風景が日常化している。こうした状況のなかで改めて「そもそも日本の保守とは何か」という根源的な問いが浮上してくるのは当然であろう。
そもそも保守というのはイギリスのconservatismの訳語であるから、「日本の保守」といったときにすでにそこには本質的な矛盾が内蔵されており、「日本の保守」なるものは成立するのだろうかという疑義が生じる。それは、本来西洋の学問である哲学philosophyに日本人が取り組む際に「日本の哲学はそもそも成立するのか」という問いに直面せざるを得ないのと同じである。
イギリスの保守思想conservatismの祖は『フランス革命の省察』で知られるエドマンド・バークであろうが、実は、1729年生まれのバークとたった一歳違いの1730年生まれの日本の思想家に、国学の確立者の本居宣長がいる。この事実はほとんど話題にならないが、大変重要であると思われる。つまり、イギリスで保守思想が定式化されたのと同時平行的に日本には国学思想がひとつの重要な思想的立場として確立されたのである。バークの『フランス革命の省察』は、革命からヨーロッパの秩序を守るための書であり、それゆえ保守思想の原典と称されるわけだが、宣長もまた、当時の日本の大陸支那礼賛の風潮の中で日本的なるものを掘り起こし、守ろうと考え、国学思想を唱えたのである。同じ十八世紀前半において、洋の東西に、イギリスの保守思想と日本の国学思想は同時的に成立してくるのである。他の国・地域に先駆けてそれぞれ固有の文明社会を築いていたイギリスと日本に同じような思想が誕生したのである。この点に重要な思想史的意味が含まれているといえないだろうか。
つまり「日本の保守」とは何かという問題を解く際に手がかりになるのは、宣長によって大成され、その後様々な思想家によって深められていった国学思想ではないかということである。大胆に言ってしまえば、「日本の保守思想」とは国学思想なのではないかということである。一般的に、「日本の保守思想」とは何かという問いを前にして話題になるのは、戦後保守を代表すると言われる、小林秀雄、福田恆存、江藤淳などの文学者であり、彼らの系譜を社会科学者として継承した西部邁などであるが、実はここに、そもそもの間違いがあるのではないだろうか。というのも、これらの人々は、確かに保守の思想を説いたといえるが、みな共通して西洋派であり、小林はフランス文学、福田と江藤はイギリス文学、西部はバークをはじめとする西欧の保守思想を専門としたのである。つまり彼らは、西洋から日本を眺め、西洋の保守思想を日本の文脈に持ち込んだのである。したがって彼らは、西洋由来の保守思想の重要性については論じることが出来たが、「日本の保守とは何か」という問題についてはまとまった論考を残すことが出来なかった。そこに彼らの問題点があるのではないだろうか。
確かに、小林は宣長を賛美し、福田は国語を論じ、江藤は江戸・幕末を描いた。それらは戦後日本の思想を画する作品であることは間違いないし、「日本の保守とは何か」という主題につながる数々の洞察も見られる。しかし、そこには、保守すべき日本人の自然観、人間観、死生観とはこれだというような体系的考察が展開されていない。彼らは、戦後の左翼的風潮によって見落とされた日本的なるものの価値に向かいはしたが、その内容について全体的に明らかにし、ひとつの思想として確立しようとはしなかった。それゆえ、彼らを参照しても「守るべき日本的価値とは何か」という点がはっきりしない。そこで、顧みるべきは、やはり国学思想の系譜ではないだろうか。
実は戦後日本にも「新国学」と称して、日本的価値の開示に取り組んだ人々がいたのである。それは新京都学派とも称された、京都大学の今西錦司や梅棹忠夫、梅原猛たちである。彼らの仕事は、同じグループの一人であった上山春平が「開かれたナショナリズム」と呼んだように、現代世界における日本思想の意義について正面から探究した点に特徴があった。彼らは、それぞれの学問方法で日本人の自然観・人間観・死生観について明らかにするとともに、それが人類の新たな時代を開く文明の原理となり得ることを説いた。今西たちは、日本民俗学を開拓した柳田國男や西洋近代の自我哲学に変わる日本思想に根ざした哲学を創出した西田幾多郎の学統を継承しながら、戦後日本の怒涛のような欧米化の風潮の中で、守るべき日本的価値を明らかにしていったのである。ちなみに、小林と今西は同年齢であり、互いに敬意を表する間柄だった。小林たちは欧米化の先頭を走る東京圏にいて、絶えず時流に向き合わざるを得なかったのに対し、今西たちは、東京から距離があり、日本的なるものが温存された京都にいたということも、それぞれの仕事に影響したであろう。
中曽根康弘は、梅原猛との対談で、「私が政治家になり、とくに総理になる前後、京都大学の皆さんは、日本的な立場を基本に置いて諸学を研究されていました」、「この人たちが日本の思想の中軸となり、政治家は、彼らとの交わりの上に日本の政治を行なっていかなければならない」というのが、私の結論でした」(『リーダーの力量』)と述べている。今日、小林や西部の保守思想と京都学派の日本思想研究を自らの内に統合し、「現代における日本の保守とは何か」という問題にひとり向き向かっているのが京都大学の佐伯啓思である。佐伯が参照している京都学派の知見は、西田幾多郎の哲学であるが、わたしは、西田哲学とともにその発展的展開ともいえる今西たちの思想にも眼を向けることで、「守るべき日本」をより明らかにすることが出来ると考えている。
2025年2月17日号 週刊「世界と日本」2287号 より

《やぎ ひでつぐ》
1962年生まれ。早稲田大学法学部卒、同大学院政治学研究科博士後期課程研究指導認定退学。憲法学専攻。教育再生実行会議や法制審議会民法(相続関係)部会の委員を歴任。『宿命の子 安倍晋三政権クロニクル』に「(戦後70年談話を評価する論文を)八木秀次さんが書いてくれた」との安倍氏の生前の発言が掲載。
2014年11月、オーストラリアのトニー・アボット首相がミャンマーのネービドーで開かれた東アジアサミットの際に漏らした発言だ。
アボット氏は日本の安倍晋三首相とブルネイのボルキア国王と立ち話をしていた。そこに中国の李克強首相が近付き、安倍氏の存在に気付くと「日本は歴史問題を克服できていない。真剣に反省していないし、謝罪もしていない」と説教を始めた。アボット氏はボルキア氏に語るように冒頭の発言をした。李氏は不愉快そうに立ち去った。
アボット氏は同年1月、スイスのダボス会議でも安倍氏を呼び出し、「私はつくづく思うのですが、日本は戦後、平和国家として立派にやってきた。世界はそれを真正面から認めるべきです」「日本はもはや戦争で行ったことに対して謝り続ける必要はない」と告げていた(以上、船橋洋一著『宿命の子』文藝春秋)。
歴史は現代に生きる者に教訓を与えてくれる。しかし、一部の国は歴史を持ち出して自らが被害者であると強調し、道徳的優位性や政治的優位性を確保しようとする。歴史を武器にして相手を支配しようとしている。日本はここから脱して国際社会で指導力を発揮すべきだ、とアボット氏は安倍氏に伝えたのだ。
今から10年前、戦後70年の節目に当たって安倍氏が発表した首相談話はアボット氏の助言などを背景にして作成された。それは「戦略的な歴史観」とでもいうべきものであった。
今年は戦後80年の節目に当たる。そうしたことから新たな首相談話を発出することが議論され始めている。
林芳正官房長官は「現時点では新たな談話を発出するかは決定していない」としたが、公明党の斉藤鉄夫代表は「戦後80年、被爆80年の節目の年に(談話を)出すべきだ」と述べている(1月22日)。
新たな談話の必要を訴える背景には安倍首相談話が戦後50年の村山富市首相談話を「上書き」したことへの不満が垣間見える。村山談話は「侵略」や「植民地支配」に「痛切な反省」と「心からのお詫び」を述べ、その後の卑屈な「謝罪外交」を決定付けた。
昨年12月の日中外相会談後、中国側は日本の岩屋毅外相が「歴史問題では『村山談話』の明確な立場を引き続き堅持し、深い反省と心からの謝罪を表明する」と述べたと発表した。岩屋氏はその後、この発表は「正確ではない」とし、「歴史認識に議論が及んだ際に、石破茂内閣は平成7年の村山談話、安倍首相談話を含むこれまでの首相談話を引き継いでいると説明した」と中国側の認識を修正した。
しかし、最新の安倍談話があるにも関わらず、村山談話に言及したことは不用意であり、中国には好機到来と映ったはずだ。中国が歴史を「支配者」にして日本を従わせるには、村山談話は有効な道具となるが、それを「上書き」した安倍談話は障害でしかない。村山談話に引き戻すことが必要と考えているようだ。
改めて安倍談話の主要部分を見てみよう。まず「百年以上前の世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました」と世界の近代史を俯瞰してみせた。その上で「日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気付けました」と日本の役割の意義を説いた。
その後、第一次大戦後、「新たな国際社会の潮流が生まれました」とし、しかし、「日本は、世界の大勢を見失っていきました」とした。そして満州事変以降を「満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした『新しい国際秩序』への『挑戦者』となっていった。進むべき進路を誤り、戦争への道を進んでいきました」と批判的に位置付けた。
村山談話の「侵略」や「植民地支配」の語は「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇も行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない。植民地支配から永遠に訣別し、すべての民族の自決の権利が尊重される世界にしなければならない」と、日本を主語にせず、国連憲章にも示される国際社会の大原則を遵守する文脈で用いた。その上で「先の大戦への深い悔悟の念と共に、我が国は、そう誓いました」と大原則の共有を誓ったとした。
そして「自由で民主的な国を創り上げ、法の支配を重んじ、ひたすら不戦の誓いを堅持してまいりました。70年間に及ぶ平和国家としての歩みに、私たちは、静かな誇りを抱きながら、この不動の方針を、これからも貫いてまいります」と戦後70年の「平和国家」としての歩みに誇りを持ち、堅持すると宣言した。
村山談話が述べた「痛切な反省」と「心からのお詫び」は「我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました」との文脈で踏襲したが、同時に「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と謝罪の世襲を断つと宣言した。
そして「だからこそ」、「『積極的平和主義』の旗を高く掲げ、世界の平和と繁栄にこれまで以上に貢献してまいります」と述べ、その後、「戦後80年、90年、さらには百年に向けて、そのような日本を、国民の皆様と共に創り上げていく、その決意であります」と将来をも展望した談話であることを強調した。
談話は一部の日本の保守派に批判はあったが、広く国内外に受け入れられた。そして日本の外交・安全保障政策を「軍国主義」への回帰との警戒心を持たずに受け入れ、国際社会で指導力を発揮する背景を作った。それを意図した「戦略的な歴史観」だった。
あれから10年、日本を取り巻く国際環境は変わっていない。日本への期待は高まっている。安倍談話に加えるべきものはなく、新たな談話は屋上屋を重ねるだけだ。首相は「安倍談話を継承する」と述べればよい。
2025年2月3日号 週刊「世界と日本」第2286号 より

《しまだ としお》
1959年山梨県甲府市生まれ。81年中央大学法学部政治学科卒、日本放送協会入局。福島、青森放送局記者を経て、報道局政治部記者となり中曽根内閣以降の政治報道に携わり、2001年より解説委員となり「日曜討論」キャスター、解説主幹、解説副委員長、名古屋拠点放送局長等を歴任し、24年より現職。
石破茂氏が内閣総理大臣に指名されて4カ月。直後の衆議院選で大敗を喫してからは少数与党政権のトップとして苦悶の表情が消えることはない。その姿は、視界不良の泥湿地の中を匍匐前進するレンジャー部隊の隊長のようにも見える。
2009年以来の自公連立政権の過半数割れは、解散・総選挙の時期を巡る石破首相の掌返しがあったにしても、政治とカネに対する国民の怒りが決定づけたものだ。パーティー券裏金不記載問題での岸田前首相の中途半端な対応に加え、非公認の候補者にも政党交付金から2000万円を支給していたのを「赤旗」に暴露されたことが大きかった。
そこに見えるのは自民党のビジネスモデルの経年劣化だ。集金マシン「国民政治協会」を受け皿に企業から献金を集め、それを党に寄付し自由に使う。1990年代の政治改革論議を経て、献金の額が制限されるようにはなったが、企業頼りは変わらないまま。献金を表に出したくない企業は、派閥や政治家個人のパーティー券を匿名で購入して義理を果たす。昨年の2度の政治資金規正法改正で、パーティー券購入者の公開基準が引き下げられ、政策活動費という勝手気ままな支出項目が廃止されるなど透明度は増した。とはいえ根本の企業団体献金の扱いは未だ議論の俎上に上ったままだ。
自民党の財務体質は、高度経済成長期に「政権党にカネを入れれば儲けにつながる。先行投資だ」という企業社会の右肩上がり幻想が産み育ててきた。しかし政党交付金が導入された後、企業経営者・幹部を除く一般の有権者の視線は次第に厳しいものに変質してきた。民主党政権の崩壊後に2度目の安倍政権が発足し、アベノミクスの名のもとに改めて右肩上がり幻想を待望する向きがあったが、現実はそうならなかった。自民党を支える仕組みが劣化したまま温存され、一気に国民の不興を買った。石破首相は貧乏くじを引いたと言える。
では少数与党に転落した石破政権に対抗して、野田政権が誕生する可能性は増しているのだろうか。答えはNOだ。自民党が国民から指弾を受け続ける一方で、立憲民主党にも支持増大の気配はない。先の衆議院選挙での比例代表の全国得票を見ると、自民党が前回2021年選挙より530万票あまり減少した一方で、立憲民主党は7万票程度増やしただけだ。議席増は小選挙区で自民候補に競り勝ったところが増えたからで、新たな支持が拡大したわけではない。その後の各種世論調査でも、自民党と同様に政党支持率の伸びは見られない。
喘ぐ石破首相、顔色のさえない野田代表を尻目に、1人元気なのが玉木雄一郎国民民主党代表(例の件で役職停止中だが)である。
なぜ国民民主党が議席4倍、比例得票2・4倍に増える躍進を果たすことができたか。自民党から剥がれ落ちた層と生活保守主義的な無党派層を受け止めたからだ。国民民主党の支持基盤は「連合」の中でも旧同盟系の電力総連、電機連合、UAゼンセン、それに加えて自動車総連といった民間の産業別組合が中核になっているのはよく知られるところだ。こういった労組は経営側との一体感が強く、経営が自民党に求めるのと近似した要求を、組合も国民民主党に提起する。どちらも「儲かる、手取りが増える」が合言葉で、現在も協議が継続している「103万円の壁」も、そうした労使一体の勢力が生み出してきたテーマだ。
石破首相にしても、長年連立を組む公明党に加え、政策面で距離が近い国民民主党と結び、「新しい自公民路線」を模索するのが現実的だと考えるのは自然だ。1990年代に社会党(当時)の影響力を排除するために自民党・公明党・民社党(当時)の「自公民路線」が模索され、PKO協力法などの成立に漕ぎつけた歴史を思い出す。
だが、政策ごとの協力・連携では不安定だ。背に腹は代えられないと仮に国民民主党と連立を組む判断に傾けば、足元を見られて「玉木首相」を求められることもありうる。1990年代の自社さ政権発足の時に社会党の村山富市委員長を神輿に乗せて担いだが、あれは初めて下野した自民党が復活を賭けたからこそできた芸当だ。
そこで囁かれるのが立憲民主党との大連立だが、野田代表は「未曽有の大災害の時などは別だが、目指すのはあくまでも政権交代による政治改革だ」とブレはない。確かに自民党救済のための大連立では国民の共感を呼ばないだろう。
2月の下旬にも山場を迎える令和7年度予算案の衆議院通過に、国民民主党や日本維新の会の協力が得られない時には、国政の土台の政府予算案が宙に浮く。暫定予算を組むはめになり、立憲民主党が内閣不信任決議案を提出し、野党がそろって賛成に回ればひとたまりもない。
しかし現状を見ると立憲民主党と国民民主党の隔たりは大きく、「野党側はそろって」という状況は生まれにくい。同じ「連合」傘下の労組でありながら、旧総評系の労組が中心になって支える立憲民主と主に旧同盟系の労組が支える国民民主の間の溝は深い。双方の最優先課題は夏の参議院選挙に向けた野党連携・共闘よりも、存在感と独自性の発揮に傾いている。内閣不信任決議案が出ても、直ちに石破退陣、あるいは追い込まれ解散へと見通せないのが視界不良の現状だ。
そうなると、6月の東京都議選、7月の参議院選を経て政界地図がどう変動するかが焦点になる。国民の側から見れば、政権の姿形がどう変わろうが政治に求めるものは明確だ。①厳しさを増す東アジアの安全保障環境に向き合うために必要な取り組み、②人口減少と超高齢化が進む中で社会保障を持続可能にするために必要な取り組み。①については中国との関係をコントロールする新たな外交展開が重要で、②については全世代の国民に応能負担を求める誠実で責任ある政治が求められる。
すべての政党が、この①②に対する姿勢を国民から厳しく問われる局面が続くのは不可避だ。自民党が引き続き先頭に立とうとするならば、政治とカネをめぐる問題で更に一段の自己改革を果たし、『新自民党に脱皮した』と評価されることが欠かせないだろう。
2025年2月3日号週刊「世界と日本」第2286号 より

《ますだ やすよし》
博士(経済学)、1958年生まれ。1981年京都大学経済学部卒業後、富士銀行入行。1988年、富士総合研究所に転じロンドン事務所長、主席研究員等歴任。2002~23年、東洋大学経済学部・大学院経済学研究科、情報連携学部教授。2016~18年、国立国会図書館専門調査員。専門は金融、国際経済。現在は東洋大学・特任講師、客員研究員等。
1月20日に誕生した第二期トランプ政権は、第一期にも行った対中経済制裁、規制緩和、移民抑制等を強化し、脱炭素政策を縮小すると予想される。需給が逼迫(ひっぱく)した米国において、これらの政策はインフレを加速し世界経済に甚大な影響を与える懸念がある。またトランプ政権の再登場により、国際協調は頓挫し、これが世界経済・社会もたらすダメージは計り知れない。そうした衝撃に対し、日本企業・政府は以下に対応すべきか。
トランプ2.0の主要政策
予想されるトランプ2.0の主な経済政策は以下のとおりである。
第一は、輸入関税引上げである。トランプは、中国からの輸入品に60%、日本・欧州を含む世界からの輸入品に一律10?20%、メキシコ産の自動車に100~200%の追加関税を課すと公言する。この驚愕的な高関税は様々な二国間交渉の為のブラフの面もあろうが、米国と軋轢のある国には実際に高関税が課される可能性が高い。
第二は、脱炭素政策停止である。トランプは、政権復帰後パリ協定から再び離脱し、バイデン前大統領が進めたEV(電気自動車)購入に対する税額控除等のグリーン政策を停止すると公言する。さらに「ドリル・ベイビー・ドリル」の標語を掲げて化石燃料回帰まで宣言する。
第三は、減税である。2025年末に失効するトランプ減税(TCJA)の延長、米国内で生産する企業の法人税率の21%から15%への引下げ、残業代や社会保障給付に対する免税を公言する。CBO(議会予算局)は、これらの大減税により米国の財政収支は今後10年で4・6兆ドル悪化すると試算する。
第四は、移民受入れ抑制である。第一期トランプ政権で抑制され、バイデン政権で緩められた移民受入れは、第二期トランプ政権では再び引締められるであろう。これは、労働需給逼迫を加速し賃金上昇要因となる。
第五は、内向きの産業政策である。中国産品を徹底的に締め出し、生産の国内回帰を促す。さらに、本来は歓迎すべき対米直接投資についても、経済安全保障を根拠にしばしば制限をかけるであろう。
経済政策変化の米国・世界への影響
これらの政策が実施された場合の影響は多大である。
まず高関税を課せば、輸入業者は関税分を価格転嫁し、また輸入品の供給が細り需給が逼迫し、これらは確実に物価上昇要因となる。そして、米国の消費者は高い輸入品を買わされ消費者余剰は縮小し、米国民の福祉は低下する。また、中国やEU(欧州連合)が報復関税を課せば、米国の輸出数量は打撃を受ける。
アジア経済研究所の磯野生茂・熊谷聡氏らの試算によると、米国が中国に対して60%、その他の国々に一律10%までの関税を課した場合、2027年時点の米国のGDP(国内総生産)は関税を課さない場合に比べ1・9%減少するとのこと。特に、EV電池の材料の天然黒鉛・永久磁石、リチウムといった中国依存が高く代替が難しい生産財では、輸入価格が大きく上昇し米国経済に強い打撃を与える。
中国のGDPも0・9%減少するが、米国自身より打撃は小さい。代替品の少ない財は、高関税が課されても輸出は減少せず、その他の財も中国は第三国経由で輸出を維持できるからである。世界全体のGDPは0・5%減少する。
他方で、日本のGDPは+0・02%と微増し、東南アジアやインド、EUのGDPも増加する。既存の対米輸出は減少するが、中国の代替としての輸出が増え「漁夫の利」を得ると見込まれる。つまり、高関税の打撃は一に米国、二に中国で、他の国々へのダメージは小さい。
拡張財政と移民受入れ縮小は、高関税設定と相まってインフレを加速する。特に移民は、バイデン政権下で労働需給を緩和する役割を果たしてきた。トランプ2.0で移民が再び抑制されれば、大都市での社会問題は改善するが人手不足と賃金インフレは悪化する。インフレが進めば長期金利は急騰し、経済成長が低下する。下手をすれば、米国は50年ぶりにスタグフレーションに陥りかねない。
為替レートについては見方が分かれるが、米国の金利上昇は更なるドル高をもたらすとの見方が一般的である。ドル高が進めば、その最大の被害者はドル建て対外債務の大きい新興国となろう。米国金利上昇は変動金利のドル債務の返済額を拡大させ、ドル高(借入国通貨安)は借入国通貨換算の債務返済額を膨らませる。つまり、ドル建て債務の返済負担は複数ルートで膨張し、新興国の債務危機につながる懸念がある。
世界の分断と国際協調破壊の罪
トランプ2.0の世界レベルの最大リスクは、国際協調・枠組みの破壊であろう。トランプは国際協調を軽視し、国際合意を平気で反故にする。国際協調・合意は、各国が国益と国家主権を移譲して初めて成り立つ。トランプが固執する自国第一主義は、国益を譲る国際協調・合意と相いれない。
トランプは、第一期政権中にNAFTA(北米自由貿易協定)を改組し、2015年の国連COP21でようやく結実したパリ協定から離脱し、前任のオバマ大統領が提唱したTPP(環太平洋経済連携協定)からも離脱した。G7やG20といった国際協調にも背を向けた。
第二期でも、トランプは国際協調を嫌い、国際合意を反故にするであろう。最も深刻なのは、バイデン政権が2021年に再加入したパリ協定からの再離脱である。CO2排出国世界二位の米国が離脱すれば、他の国々の脱炭素の意欲が低下しパリ協定は形骸化しかねない。世界が積み上げた地球環境改善の為の努力は露と消える。
また、ウォール街に近いトランプは、国内の金融規制を緩和するだけでなく、半世紀に亘って世界の金融健全化策の中核となったバーゼル合意(国際銀行に対する自己資本比率規制)をも葬り去る懸念がある。米国が、導入中のバーゼルⅢの適用を停止するようなことがあれば、世界の金融システムが揺らぐ。
日本企業はどう対応すべきか
トランプ再登板の多様なショックに、日本企業はどう対応すべきか。
まず、中国での生産ベースを、極力、米国や日本を含む第三国に移すべきである。ただし、米国での生産拡大を図る際には、日本製鉄によるUSスチール買収への妨害の教訓を踏まえ、M&Aでなくグリーンフィールド投資とする方が良い。
米国への輸出も、極力、欧州や新興国向けにシフトすべきである。
日本政府には、トランプ政権との緊密な対話を持ち、理不尽な制裁を避ける努力を願いたい。他方で、堂々と正論を交え、トランプ政権の暴走を抑えることも試みて欲しい。その際には、国際社会で発言力の強い欧州との連携が重要である。特に、日本と並んで米国と同盟関係にある英国との協働が有効である。そうした意味で、年末に英国がTPPに加わった意義は高い。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より
ネット時代と民主主義の危機
日本大学 危機管理学部教授
先﨑 彰容 氏

《せんざき あきなか》
1975年東京都生まれ。専門は近代日本思想史・日本倫理思想史。東京大学文学部倫理学科卒業。東北大学大学院博士課程修了後、フランス社会科学高等研究院に留学。著書に『国家の尊厳』、『本居宣長:「もののあはれ」と「日本」の発見』、『批評回帰宣言:安吾と漱石、そして江藤淳』など。
昨年は、国内外において民主主義が問われた一年であった。自民党総裁選を挟んで行われた東京都知事選と衆議院総選挙は、改めて、SNSがもつ新しい風を感じさせるものであった。都知事選での「石丸現象」は、SNS戦略が大きな意味を持つことを実感させ、衆院選での国民民主党の躍進も、SNSなくしては考えられない。さらに兵庫県知事選での元知事返り咲きは、NHKから国民を守る党の立花党首のSNS戦略なくしては考えられない結果である。一知事候補の最終日の演説に異様なまでの熱気を帯びた群衆が集まり、携帯電話を構えている。日頃、選挙参加熱が低いことを嘆く論調は多々あるが、では逆に、この熱気を肯定すべきなのかと問われれば、躊躇いを覚えるのではないだろうか。
この一連の現象をポピュリズムというのはたやすい。だが、この流れが不可避の現実であることを思う時、もう少し深い時代考察が求められると思う。いったい、私たちが何に巻き込まれているだろうか。私たちはどんな時代を生きていて、情報に踊らされているのだろうか―この問いに対し、微視的と巨視的の二つの観点から考えてみたい。
第一に、石丸現象とN国党が、いったい何を意味しているのかということである。石丸氏の新しさとは、政策の新しさではない。人の話を揶揄し、皮肉めいた口調で語るその語り口に、人々は惹きつけられている。またN国党の場合、都知事選に計24名の候補者を乱立させ、同一ポスターを掲載した。また兵庫県知事選においては、ネット上で特ダネの暴露記事を入手解説し、大きな影響力を発揮したと聞く。
二人の人物にまつわる、この簡単な解説だけでも、すでに時代状況を診察する手がかりがある。彼らに共通するのは、「真面目」な世間に対して、皮肉によってゆさぶりをかけることである。民主主義における選挙は、本来、各候補者の政策をしっかりと学び、その是非を自分で判断し、一票を投じることで、日本をよくする行為である。だから各候補者は、自らの政策を問い、他候補と競い合うべきだ―これが「真面目」な解答だ。ところが、彼らが行った一連の行動は、この「真面目」に対し、ナンセンス!を叫びながら、秩序にゆさぶりをかける行為だった。落選確実にもかかわらず、24名を乱立させたのも、「真面目」な状況それ自体への異議申し立てだ。
彼らが大きな支持を受けたのは、この「真面目」を「ゆさぶる」点にあった。ここで私が、状況を「破壊」するのではなく、「ゆさぶる」と書いていることに注目してほしい。要するに、私たちは、日本社会が閉塞感に覆われており、にもかかわらず決定的な革命や破壊、変化が起きるとは思っていない。しかし不平不満は渦巻いている。だとすれば、時代状況を皮肉り、嫌味を言ってニヤリと笑うしか、ストレス発散の方法はないではないか。こうした人々の感覚の象徴こそ、石丸現象であり、N国党の奇妙な存在感の原因なのである。その際、彼らが駆使したのが、SNSというツールだった。
以上が、微視的な観点からみた時代状況である。以下では視野を大きく広げ、巨視的な視点から、現在、私たちがどんな社会を生きているのかを見てみよう。ここでも注目すべきはネット社会である。そのネット社会を創造した企業集団をGAFAMと呼ぶことはよく知られている。自分の生活を振り返ってみると、会社の同僚であれ、大学の学生であれ、生身の人間と接している時間以上に、私たちは画面の向こうに広がる空間で生きていることがわかる。パソコン画面の向こうにある世界に向かって、やり取りをし、物を買い、広告を見せられているからだ。こうした状況を説明する言葉に、「デジタル荘園」というものがある。ネットを使っている私たちは、「デジタル荘園」の小作人だというのだ。いったいどういう意味なのか。
中学校の歴史教科書を思い出してみよう。律令国家が誕生すると、中央集権化を進めるために、国家が口分田を支給し税を徴収した(班田収授法)。しかし次第に国家統治機能が弱まると、過酷な税を逃れて、人々は逃散したり、国家秩序の外側で、自力で生産活動をはじめる。これが荘園の誕生であり、自警団が武士の登場を促すわけだ。
さて、この比喩を現代社会に当てはめるとどうなるのか。それは石破総理を頂点とした国家権力とは全く別の組織、すなわちGAFAMが所有する広大な私有地こそ、ネット上の世界だとわかるだろう。そこでYouTubeを配信する者も、それを視聴する者も、どちらもGAFAMに金銭を上納している。つまり、国に税金を支払う代わりに、デジタル荘園を創った数人の経営者に、税を納めていることになるのだ。私たちが視聴し、検索する行為は、荘園を耕しているのと同じである。だから私たちは現代の小作人なのである。
ここで注意したいのは、私たちが国境を軽々と超えたGAFAMの経営者に、情報から生活スタイルまで支配されてしまっていることだ。石破茂という人物は、衆院選挙を勝ち抜き、自民と総裁選を勝ち抜いた人物であり、民主主義制度に従っている。ところが、GAFAMの経営者を、私たちは選挙で選んだわけではない。だとすれば、今日、私たちは、巨視的な視点から見た場合、国家権力よりも巨大かつ少数の人間の支配下で生きていることになるだろう。
以上をまとめよう。微視的に見た場合、現在の日本社会は閉塞感に覆われている。人々は、その留飲を下げる方法として、ネットを駆使し、「真面目」な世界を馬鹿にしている。巨視的に見た場合、今、世界全体がごく一握りの人間に支配されようとしている。微視的、巨視的、双方の視点に共通するのは、今、私たちが「真面目」な民主主義制度の危機に直面しているということだ。トランプ大統領とイーロン・マスクの登場、プーチンの戦争、韓国大統領の危機―令和六年にはじまった課題を抱えたまま、私たちは新しい年を迎えたのである。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より

《かわた よしあき》
関西大学特別任命教授・社会安全研究センター長、人と防災未来センター長。京都大学名誉教授。国連SASAKAWA防災賞、防災功労者内閣総理大臣表彰など受賞多数。瑞宝中綬章。日本自然災害学会および日本災害情報学会の会長を歴任。著書に『これからの防災・減災がわかる本』『にげましょう』『津波災害(増補版)』等。
阪神・淡路大震災がきっかけとなった国難災害研究
この震災が発生した時、兵庫県南部地震は、次の南海地震の活動期に入った証拠となる、という地震研究者の合意のようなものがあった。筆者は、阪神・淡路大震災のような巨大災害は、わが国で起こると予想していたが、被害を少なくすることはできなかった。だから、防災研究は実践的でなければならないと誓った。そこで、震災後、直ちに「東海・東南海・南海地震研究会」なる官民学からなる組織を立ち上げた。発足当初、300人を超える同志が集まった。なぜ、この組織を立ち上げたのか。それは、防災・減災を実現するには、研究者だけの力ではできないと考えたからである。この組織は、NPO法人大規模災害対策研究機構と名を改め、今日に至っている。2000年の省庁再編で、それまでの国土庁防災局に代わって、内閣府防災が発足したが、そこで専門調査会の第一号として、「今後の地震対策のあり方に関する専門調査会」が立ち上がったのは、この組織の功績と言われている。
東日本大震災が教えてくれた「社会現象の相転移」の発見
津波被災地の現地調査を重ねて、被災市町村の町丁目単位で来襲した津波の高さと死亡率を1枚の図面にまとめてみたところ、まったく特徴が見いだせず、途方に暮れた。しかし、何度も図面とにらめっこして、ある時、死亡率の大きさに上限らしきものがあることに気がついた。これが相転移発見のきっかけとなった。この震災が起こった当時、地震後、巨大な津波が沿岸各地を襲い、津波避難したけれど間に合わなかった、というようなストーリーが共有された。慎重に調べてみると、浸水した沿岸域の住民は約60万人で、その内27%は必死になって避難しなかったことがわかった。地震後に第一波が最も早く来襲した岩手県沿岸でも、30分近い避難の時間があった。だから必死になって避難しておれば多くの人は助かっていたことがわかった。仙台市など50分近い避難時間があったのである。相転移を起こしたと判断できる死亡率の上限値に近い値は、27%どころか、100%に近い住民が避難しなかった例であると言える。
能登半島地震が突き付けた高齢社会の災害関連死の多さ
この地震では、震度6弱以上の地域住民は約17万人であり、災害関連死は12月27日現在、276人である。まだ、約200人が判定を待っていると言われている。一方、2016年熊本地震では前者が約148万人に対し、関連死は222人であったから、能登半島地震では、熊本地震に比べて災害関連死による死亡率は約10・8
倍も大きい。なぜこのように極端に大きくなったのだろうか。最近の米国・カリフォルニア大学の調査によると、過去に米国に上陸した501個のハリケーンの被災地での災害関連死の発生は平均15年も続き、約7千人から1万1千人が死亡したことが明らかになった。わが国で災害関連死が問題となったのは30年前の阪神・淡路大震災で、912名が犠牲になった。しかし、これが15年も発生してきたかどうかは、そもそも解析に堪える医療情報がわが国では揃っていない。もし南海トラフ地震が起これば、地震と津波によって約6100万人が被災すると想定されている。そうすると、能登半島地震と事情が同じなら約9万人が災害関連死することになる。しかも、将来はもっと後期高齢者が増えることがわかっている。災害関連死は、避難所の居住環境や医療や福祉のレベル向上など、科学的な所作の充実だけでは減らないことを理解する必要がある。後期高齢者は平均余命が短い。被災経験はこれをさらに短くすると考えれば、災害関連死対策が極めて困難なことがわかるだろう。
現実になる防災庁の創設と必要な日本国憲法の緊急事態条項明記
筆者は防災庁を創設しなければ、国難災害が起った途端にわが国の衰亡が始まると主張してきた。そして唯一、国会議員としては石破茂氏が主張していた。そして、同氏が首相に就任して、防災庁がにわかに実現できる環境となった。筆者はすぐに彼に手紙をしたためた。何としてもこの機会を逃すまいと、必死だった。防災庁などできそうにないという人たちの共通の意見は、各省庁は人員と予算が少なくなるのは決して容認できないとか、たとえできたとしても失敗するに決まっているという類のものが圧倒的に多かった。ひどいのは“屋上屋を重ねる”とか“行財政改革に反する”いう類のもので、素人判断丸出しの反対だった。
でも、筆者には勝算がある。なぜなら、現行のレジリエンスに代表されるように、欧米は事後対応が中心である。歴史的に国難災害のような大災害は滅多に起こらないから、起ってからの対応で間に合うと考えるのである。ボランティア活動にそれが現れている。欧米では、ボランティアとは、被災地に住んでいて被害を被らなかった人が活躍するということである。ところがわが国では、ボランティア元年は阪神・淡路大震災とともに始まったが、わが国では被災地の外で生活している人が被災地に駆けつけて活動するというように定義された。この結果、被災地に住んでいる人はすべて被災者になってしまった。これでは、南海トラフ巨大地震や首都直下地震が起これば、能登半島地震よりももっと悲惨な結果が見えてしまう。
一方、今回の衆議院選挙で与党が圧倒的に勝っておれば、日本国憲法に緊急事態条項を明記するという憲法改正は可能だったように思われる。
筆者は、この運動を進めていたニュー・レジリエンス・フォーラムの防災分野の代表として参画していたので、もう一歩のところで頓挫し、残念でならない。でも、あれだけ活動していた憲法改正実現本部は一体、どうなってしまったのだろう。早急に方針を示さなければ、防災庁が創設できても、十分に機能しない状態のままに置かれることになろう。つまり、創設と明記は一対をなすものであって、片方だけでは防災・減災・縮災は機能しないことは明白である。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より

《そね やすのり》
1948年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学大学院修了後、同大学法学部助手、同教授、総合政策学部教授、政策・メディア研究科教授などを経て、2018年から現職。イェール大学客員研究員、エセックス大学客員教授、 ハーバード大学客員研究員、日本アカデメイア運営幹事。主な著書として、『日本ガバナンス』(東信堂、2008)等
政治とカネの問題が公になって1年以上たっても、依然として釈然としないことは残っている。パーティー券収入の不記載はなぜ行われたのか。この問題は、マネーロンダリングのように思われているが、実は逆のことをしてきた。
通常のマネーロンダリングとは、裏金を表金にして、堂々と使えるようにすることである。裏金は、使い勝手がいいと思われているが、それは、帳簿に載せることができない金で、あくまでも裏のまま使わざるをえない。
もう一つが、安倍晋三清和会会長が、不記載はまずいので、止めようといったのに、それを復活してしまった。この「なぜか」に明確に答えた者はいない。政倫審に登場した清和会幹部たちの曖昧な答弁は、「意思決定に責任をとる」政治家ではないと自ら宣言しているようなものである。
では「政治とカネ」に一年間振り回された日本政治はどうなったかを整理しておくと、岸田首相は結局、退陣せざるを得なかった。総選挙で自民党は約50議席減らし、石破総裁が設定した自・公で過半数のラインに届かなかった。「政治とカネ」がすべてとはいえないが、総じて、政治家が金の流れや額を曖昧にしていることに、国民は依然として怒っている。世論の納得をどのように得ることができるかがまず主要な課題である。
総選挙後の自民党・公明党は少数与党なので、従来どおりの方法では法案を通過させることはできない。また、少数与党運営のノウハウの蓄積も多いとはいえない。当然、野党との協議や過半数確保のための多数派工作が必要になる。
政治資金規正法の再改正に向けて、与野党から9本の法案が提出された。論点は、大きく分けると、①企業・団体献金の禁止、②政策活動費の廃止、③第三者機関の設置で、各党で意見に大きな差がある。調査研究広報滞在費(旧文通費)の公開や政治資金パーティー問題もこれに付随して出てくる。
結局のところ、3法案を成立させ、企業・団体献金については、2025年3月までに結論を得ると先延ばしした。つまり、自民党は野党案を飲むことによって法案成立を図った。政治資金の透明化の原則はどの党も反対をしない。どこまで使い勝手のいいデータベース化ができるのかは今後の課題となってくる。自民党が政策活動費の公開を渋る理由も、煎じ詰めれば選挙の時に幹事長が陣中見舞いに持っていく金額が、候補者によって違うのが、公開で明らかになるのがまずいという。しかし、それはもっぱら党内の内向きの議論である。旧文通費もそうであるが、いわゆる「渡しきり」の支出から、かならず領収書を添付し、公開を前提とするということは、できないことではない。
しかし、政治資金の第三者機関の設置、政治資金パーティーの禁止、企業・団体献金の禁止なると各党の思惑は異なる。
第三者機関については、会計検査院のような行政機関として置くのか、国会内に設置するのかであるが、行政機関説を採ってきた公明党は、国民民主党と共同提案で、国会設置の「政治資金監視委員会」に舵を切った。
自民党は、第三者機関を、プライバシーや外交機密などの「公開方法工夫支出」(要配慮支出を改称)の監査を念頭にしてきたが、立民などからの、新たなブラックボックスを作ることになるとの批判を受け、断念した。国会設置の第三者機関は国会議員にとどまるようだが、政党支部やすべての政治団体、地方議員の政治資金の問題が残るだろう。
企業・団体献金の禁止についてはもっと抵抗が強いが、いうまでも無く、政治資金パーティーも同様だが、禁止したとしても、抜け穴はいくつでも作れる。
企業・団体献金の禁止には、理念と実態と両方からの主張がある。そもそも、平成の政治改革では、政党交付金を導入することと引き替えに企業・団体献金を禁止したのだから、当然に、それを実行するだけでいいという主張が片方にある。一方、自民党は政党交付金との引き換えに、企業・団体献金の禁止がなされたわけではなく、5年後に見直し(復活)するということであったと理解している。石破首相は、憲法21条まで持ち出して、禁止は憲法に抵触と主張する。
もう一つが、実態面からのもので、どんなにきれいごとをいっても、寄付により、政策を左右し、政治を歪めるというという主張である。
ただし、どこまで影響を与えたのか、政策を歪めたかの立証は簡単ではない。それゆえ、「クリーンハンド」や「李下に冠をたださず」という一般原則が過去主張されてきた。また、透明性というが、記載、公開、追跡可能性の問題は本来、詰めておく必要がある。
ただし、政党への寄付は認めたとしても、経団連が行っているような、選挙の際のマニフェストを評価して、献金額を決めるという方法は、個別政策への寄付とは違うとはいっても、「政策を金で買う」ということになりはしないか、という疑問はでてくる。
では、政党への寄付はどのような分野なら許容できるのかだが、民主主義のインフラへの寄付、政策開発のためのシンクタンクへの寄付などは、直接に政策を買うことにならないだろう。
この問題は、世論調査でも禁止が多数ではなかった。「認めたうえで、透明性を高めるべき」60%、「禁止すべき」30%(読売新聞 2024.12.16)は石破首相の主張に似ているが同一ではない。
そもそも、民主主義のコストは誰が負担すべきについては、大きく意見が分かれる。現状は、税金(政党交付金)、事業収入(政治資金パーティーや機関誌発行など)、寄付、党費、その他からなるが、最近では政党交付金の比率が高くなっている。
自民党は収入総額約225億円のうち、交付金が159億万円で70・5%になっている。そのことは、企業・団体献金をあくまで固執する自民党の主張と整合的ではない。
政治とカネの問題を語ることは、政治とは政党とは、を語ることになる。明確なルールのもとで実行可能な案をつくることと、国民が納得できるような答えを見いだすことは簡単なことではない。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より

《おかだ あきら》
1947年大阪市生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、日本経済新聞社に入社。記者、編集委員を経てテレビ東京に異動。WBSプロデューサーを経て、ニューヨーク支局長、テレビ東京アメリカ初代社長、テレビ東京理事・解説委員長。06年より経済評論家として独立し、大阪経済大学客員教授に就任、22年より同特別招聘教授。主な近著に『徳川幕府の経済政策―その光と影』。
2025年は第2次トランプ政権の発足やウクライナ情勢の行方など国際情勢のリスクが山積している。国内政治も不安定で、日本経済にとって厳しい年になりそうだ。しかしその中にあっても、「日本経済復活」の動きは2025年も続くだろう。
トランプ氏がカギ握る、「脱・中国」加速へ
2025年の国際情勢のカギを握るのはトランプ氏だ。ちょうど本号の発行日である1月20日に同氏は第47代米大統領に就任するが、初日から、1期目以上に強い姿勢で政策を実行する構えだ。
問題は、その政策の中身とその影響である。
まず、選挙戦で掲げていたトランプ減税延長、法人税引き下げ、国内製造業の投資促進などの国内経済政策は、景気にプラスだ。トランプ氏の勝利後、ニューヨーク市場で株価が史上最高値を更新したのも、その期待を反映したものだ。
一方、対外政策では中国への強硬姿勢が際立っている。選挙中から「中国からの輸入品に60%、全ての国に一律10~20%の関税」と主張していたが、選挙後の2024年11月25日には「中国への関税を10%、カナダとメキシコへは25%引き上げる」と表明した。
中国に対しては今後さらに関税を引き上げると見られ、半導体規制なども強化すると予想される。こうした対中政策は、米国だけでなく日欧なども含め「脱中国」の流れを加速させるだろう。過度な中国依存という経済構造の是正につながると評価できるものだ。
3つのリスク― 関税、インフレ、円高
だがその反面、トランプ氏の経済政策には3つのリスクがある。
第1は、関税引き上げによる世界経済への悪影響だ。ジェトロ(日本貿易振興機構)の試算によれば、「中国に60%、他の国に一律20%」の関税が実行されると、2027年の米国の実質GDP(国内総生産)は2・7%減少するという。2024年7~9月期の成長率が2・8%だったことを考えれば、計算上はほぼゼロ成長、または状況によってはマイナス成長に陥る可能性があることになる。
また中国のGDPは0・9%、世界では0・8%の減少となる。
問題はそれだけではない。米国の関税引き上げに他の国が対抗して関税を引き上げれば世界が貿易戦争に突入する事態となりかねない。そうなれば各国経済への悪影響はもっと大きくなる。
さらに「全ての国への関税引き上げ」は同盟国との関係をも悪化させ、ただでさえ緊迫している国際情勢を一段と不安定化させる恐れがある。
これらは金融市場を一段と動揺させ、世界経済の悪化を加速する要因となる。
第2のリスクは、米国のインフレ再燃だ。前述の国内経済政策が景気押し上げを通り越して「過熱」状態となったり、関税引き上げで国内物価が上昇する可能性がある。インフレ再燃で米国経済が悪化すれば、日本経済も影響は避けられない。
第3は、急激な円高への転換だ。為替相場はトランプ政策による米景気拡大期待からドル高・円安傾向となっているが、トランプ氏自身はドル安論者であり、「円安は大惨事」と発言したこともある。国際情勢緊迫化も「リスクオフの円買い」の要因となる。
緩やかに円安が是正されるのなら好ましいが、短期間での急激な円高は日本経済にとって新たな打撃となる。
強さ取り戻しつつある日本経済
こうして見ると日本経済の先行きは厳しいように思える。だが「それでも日本経済は復活する」と強調したい。その根拠の一つが、この1~2年、「過去最高」「バブル期以来」などの経済指標が続出していることだ。
例えば、2023年度にGDPの実額が実質、名目ともに過去最高を記録していたが、2024年度の4~6月期に名目GDPが初めて600兆円(年率換算)を超え、7~9月期も2四半期連続で過去最高を更新している。
日本経済は長年の低迷から脱して本格復活に向けた前向きな動きが始まっているのだ。それは以下の3つの要素が牽引している。
第1は、日本企業の競争力回復・強化だ。上場企業の業績は2024年3月期に3期連続で最高益を達成していたが、2025年3月期も最高益記録を伸ばす見通しだ。設備投資額(GDPベース)も2024年4~6月期に33年ぶりに過去最高を更新し、7~9月期は2期連続で過去最高を記録した。各企業が本来の意味でのリストラ(restructuring=事業の再構築)や技術力強化など経営の構造改革を進めてきた成果である。
第2は、インバウンドだ。訪日外国人数が過去最高となっているのは周知のとおりだが、世界中で今「日本ブーム」が広がっている。日本の技術力やきめ細かいサービス、おいしくヘルシーな食、アニメなどの文化、さらに安全、ホスピタリティなど、トータルで日本の人気が高まっているのである。これがもたらす経済効果は幅広い分野に及んでいる。
第3は、「新冷戦」によって日本の地政学的重要性が高まっていることだ。「脱中国」の流れの中で日本企業の国内回帰の例が増え、欧米企業のリスク分散の受け皿として日本の存在感が高まっている。TSMC(台湾積体電路製造)の熊本進出はその一例で、日本のハイテク産業や地域経済の活性化効果を生んでいる。国際情勢の緊迫が日本にとって追い風になるという側面は、もっと注目されてよい。
このように日本経済は構造的に強さを取り戻しつつある。この動きは2025年もその先も続く可能性が高い。山積するリスクは直視すべきだが、過度な悲観論に陥ることなく、前向きな動きにもっと注目したい。それがリスクを乗り越えるパワーにもなるのである。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より

《にわ ふみお》
1979年、石川県生まれ。東海大学大学院政治学研究科博士課程後期単位取得満期退学。博士(安全保障)。2022年から現職。拓殖大学国際日本文化研究所所長、大学院地方政治行政研究科教授。岐阜女子大学特別客員教授も務める。著書に『「日中問題」という「国内問題」―戦後日本外交と中国・台湾』(一藝社)等多数。
昨秋の衆院選で自民党と公明党の連立与党が過半数を割り込み、石破茂内閣が綱渡りの政権運営を強いられる中、早くも今夏に行われる参院選に向け、与野党間の攻防が激しさを増している。参院選を考える時、重要な要素として挙げられるのが時期である。参議院議員の任期は6年で3年ごとに半数を改選するため、3年に1回行われ、しかも1956年の第4回参院選からは必ず6月か7月に実施されている。参院選は「通常選挙」と呼ばれるように、時期を勝手に動かすことができない。衆院選は、時の首相が衆議院議員の任期である4年以内であれば自由に時期を設定できる。
しかも、参院選は、その段階で浮上した旬な課題が注目される。「不易流行」からすれば、「流行」が取り上げられるのが参院選である。しかしながら、一時のブームによって、大衆の琴線に触れない課題が矮小化することには疑問を感じざるを得ない。
その1つが参議院改革である。参院選だからこそ問われるべきテーマであるはずが、毎回、忘れ去られている印象を受ける。そもそも参議院改革の必要性が指摘される理由は、その曖昧さにある。与党が衆参両院で過半数を占める中において参議院は「衆議院のカーボンコピー」と揶揄され、逆に参議院で野党の議席が与党を逆転する「ねじれ現象」が生じると、今度は物事が一向に決まらず「有害」と言われる始末で、「無用の長物」と化している。では、そもそも参議院は何のために存在しているのであろうか。
参議院は1947年5月の日本国憲法施行と同時に誕生した。参議院を設けるに当たり、1946年9月20日に行われた貴族院帝国憲法改正案特別委員会において、「憲法の産みの親」と称される憲法担当の国務大臣だった金森徳次郎は、「一院專制と云ふやうな傾き、又議會の審議が愼重を幾分缺く憾みがあると云ふこと、及び輿論が果して何を目當にして結集せられて居るかと云ふことに付きましての判斷を的確ならしめると云ふやうな、此の三つの要點はどうしても二院政治の美點として擧げなければならぬのではないかと、斯樣に思つて居るのであります」と指摘している。第一院による暴走の危険を抑制し、第一院の決定事項をチェックしながら足らざる部分を補い、第一院だけでは十分に捉えきれない民意を汲み取るところに、その存在価値があると主張しているのである。言わば衆議院の監視役、アドバイザー的存在としての役目が期待されたのである。
「参議院」という名称に関しても、当初は第一院とセットで「上院・下院」、「左院・右院」、「南院・北院」、「元老院・衆議院」、「公議院・特議院」、「耆宿院・衆議院」、「審議院・衆議院」といった案が挙がったという。だが、結局、衆議院の「『議』論」に「『参』与」するという意味から「参議院」という名前になったらしい。「参議院改革」なる言葉が出てくるのは、偏に今日の参議院が金森の理想とは程遠いものになっているからに他ならない。
参議院ができた当初こそ、第1回参院選に無所属で出馬し初当選を果たした劇作家で小説家の山本有三(勇造)が中心となって保守系無所属議員を集め、参議院のみの会派として「緑風会」が結成され、参議院の独自性、自主性の確保を目指したこともあった。一時は96人を擁し、虹の七色の真ん中に位置する「緑」の如く、文字通り常に是々非々、公平公正を重んじた。
衆議院から送付されてくる法案を厳しく審査しながら修正を施し、採決でもメンバーそれぞれの自由意思を尊重した。文化財保護法を始め、緑風会が旗振り役となって作られた法律も多い。しかし、自民党と社会党による「55年体制」成立後は、緑風会も徐々に政党化の波に?み込まれ、既成政党への転向議員は増え続けた結果、1965年4月、18年で幕を閉じた。
参議院が「ミニ衆議院」になりつつある中、これに一石を投じたのが自民党の河野謙三であった。1971年6月の第9回参院選における投票率が59・24%という低さだったことに衝撃を受けた河野は、参議院議員全員に「選挙を終わって」と題する書簡、いわゆる「河野書簡」を送り、参議院の信頼回復を訴えた。
そして7月、野党の賛同も得て参議院議長に就くと、河野は急ピッチで参議院改革に乗り出した。まず、議長就任に伴い、副議長となった森八三一と一緒に党籍離脱を敢行、これは議事進行の公平性、中立性を目指すもので、今でも慣例として続いている。さらに「参議院問題懇談会」を設け、「参議院運営の改革に関する意見書」を答申、ここで提起された改革案は、その後の参議院改革における叩き台となっている。
通常国会の12月召集から1月召集への変更、衆議院にはない行政監視委員会の設置、決算審査の充実や調査機能の拡充と、実現したものもある。本会議採決における時間短縮ための押しボタン式投票も導入され、近年では本会議場のバリアフリー化が進められた。しかし、これらは技術的、部分的な措置であり、抜本的改革とは言い難い。
今日では「参議院無用論」まで飛び出す始末である。「そもそも第二院は必要であろうか。もし第一院に一致するならば、それは無用であり、一致しないなら害悪である」と喝破したのは、フランス革命の理論的リーダーで知られるシェイエスである。参議院改革が進まないのは参議院議員自らの怠慢である。
もちろん、参議院を廃止して一院制に移行するにしても、新たな第二院を創設するにしても憲法改正が必要であり一朝一夕にはいかない。
しかし、例えば参議院における党議拘束の廃止や参議院議員の入閣禁止と、憲法に触れずとも一定のルールを設ければ簡単にできるものもある。「良識の府」としての権威を取り戻すべく、来る参院選では、それぞれの政党がオリジナルの改革案を示すことを期待したい。
2025年1月6日号 週刊「世界と日本」第2284号 より

《しおた うしお》
1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『昭和の教祖 安岡正篤』、『日本国憲法をつくった男 宰相幣原喜重郎』、『憲法政戦』、『密談の戦後史』、『内閣総理大臣の沖縄問題』、『危機の権力』、『解剖 日本維新の会』、『大阪政治攻防50年』。近著に『安全保障の戦後政治史』など著書多数。
石破茂首相は就任直後の衆院選で大敗を喫したが、何とか無風で2025年を迎えそうな空気となった。
選挙後の24年11月の世論調査で「首相交代より政権継続」を望む割合が軒並み50%を超えた。現在はこの民意が唯一の頼りである。
といっても、政権は「風前の燈」という状況に変わりはない。
衆議院で与党が過半数割れの「少数政党並存」の政情に加え、石破流政治の理念や路線、政策が不明という不満、首相としての資質、能力、力量などを疑問視する声も多い。民意の石破離れが起こるかどうか、「一寸先は闇」だ。
25年前半は1月下旬の通常国会開会、3月末前後の新年度予算成立、4月の関西・大阪万国博覧会開幕、6月の国会会期末に続いて、参院選が控える。7月には東京都議会議員選挙も予定される。
最大の焦点は参院選だ。衆議院と同じ少数政党並存が参議院でも現実となるか否か。
参議院では現在、自民党は単独過半数に12不足の113、連立与党の公明党との合計は過半数の15超の140議席だ。参院選で自公合わせて17以上の減となれば、参議院も少数政党並存となる。
24年衆院選の自公両党の獲得議席は、その前の21年衆院選と比べて計78減だった。加えて、25年参院選の自民党の第1次公認候補には、裏金問題関係議員が12人いる。これを見れば、参院選での17以上の減は、実現困難な数字ではない。
石破首相は25年、参院選の乗り切りとその後の政権継続を展望して懸命に策を練っているはずだ。参院選対策と政権強化策の両にらみで、政権戦略を構想中に違いない。
第一は、衆院選後、政策協議方式で3党体制に加わった国民民主党を正式に連立与党に組み込む「自公国政権」プランだ。第二は、野党第一党の立憲民主党との大連立も選択肢にあると見る。
路線や政策の相違は大きいという指摘も多いが、大連立だと、衆参ともに圧倒的多数の与党が出現する。
両党の関係では、石破首相と立民の野田佳彦代表との「見えない絆」も見落とせない。
野田内閣時代の12年8月、その約1年前まで野党・自民党の政務調査会長だった石破氏をインタビューしたとき、「考え方は同じ保守。ともに国家を語り合える人」と野田氏を評価した。
石破政権を左右するのは内閣支持率に表れる民意の動向だ。
25年前半、政権が実績と実効を示し、石破流政治に対する国民の期待が高まれば、支持率も好調に推移する。石破首相は反転攻勢の好機を逃さず、「自公国政権」や大連立を仕掛ける手がある。
逆に、政権が成果を残せず、連立組み替え作戦も不成功なら、死に体となる。支持率が超低空飛行となる危険性も大きい。
自民党内で「石破首相では参院選は戦えない」という反発が噴き出し、石破降ろしが現実となる展開が予想される。
そうなれば、石破首相は、進むか退くかの決断を迫られる。時期は25年度予算が出来上がる3月末前後という見方が有力だ。
そこで「進む」を選ぶなら、一つは、前回の衆院選からわずか5カ月だが、予算成立の直後に衆議院解散に再挑戦する戦法もある。ただし、首相にその政治的パワーがなければ絵に描いた餅だ。
もう一つは、石破首相が6月の通常国会会期末まで持ちこたえた後、内閣不信任決議案提出を逆手に取って衆議院解散に打って出る。この場合は、次期参院選との衆参同日選となる確率が高い。
衆参同日選は衆議院が中選挙区制だった1980年と86年に事例がある。2回とも自民党は衆議院で大勝、参議院も勝利を収めた。
今も党内では「党危機の最大の突破策は衆参同日選」という神話が消えていないが、現行選挙制度でも通用するとは限らない。だが、一点、同日選だと、自民党以外は候補者不足に陥るという弱点があり、自民党に有利という主張も根強い。
衆参同日選では「公明党の壁」も無視できない。公明党は、特に選挙対策の面で、伝統的に同日選に抵抗感がある。25年は、公明党が重視する東京都議選も同時期に行われる。
一方、首相の決断が「退く」のケースだ。「短命不可避」の悪条件の下で在任6カ月が限界、と首相自ら認識し、新年度予算成立を見届けて退陣に踏み切る可能性もある。
衆参同日選の成否は別として、実は自民党からは衆院選の早期再実施の待望論が流れてくる。「24年衆院選での民意の大量離反は裏金疑惑問題による一時的現象」「その結果、生じた少数政党並存を一刻も早く打破すべき」との主張が渦巻く。
他方、「立憲民主党と国民民主党の勢いは今が天井で、今後は下り坂では」という身びいきの観測も強い。
早めにやり直し衆院選を実施すれば、自民党離れを起こした潜在的な自民党支持層が大量に戻ってくるという計算が働いているようだ。
政治の将来を読む上で重要なポイントは、24年の衆院選による少数政党並存政治は、自民党自滅による一時的現象と見るのが正解かどうかである。
全体として、国民は既得権益優先の派閥主導型自民党政治は時代遅れと感じているのではないか。1党支配や2大政党よりも、少数政党並存も含めた「緩やかな多党政治」が、価値観の多様化を容認する現代の日本社会に最適の政治形態、と多くの国民が受け止めているように映る。
であれば、少数政党並存は一時的現象ではなく、新時代の幕開けと見るべきだろう。このモデルが、変形型も含め日本政治の主流となるかもしれない。
24年11月に自民党の森山裕幹事長をインタビューして、衆院選の際の事前予想を尋ねたら、「負けると思っていた」と回答した。石破首相、森山幹事長とも負け戦覚悟で衆院選に挑んだ一面があったことは否定できない。
その主眼が、時代遅れの派閥主導型自民党の解体、新型政党への改造だったとすれば、むしろ政治大激動の決戦はこれからが本番である。石破首相の「進むか退くか」の判断では、もう一つ、この政治決戦への取り組みがキーとなりそうだ。
2025年1月6日号 週刊「世界と日本」第2284号 より

《いしかわ よしふみ》
1967年愛知県生まれ。専門は地域経済学、政策評価。博士(工学)。岐阜大学卒業後、東海総合研究所(現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング)などを経て現職。現在、名古屋大学客員教授、環太平洋産業連関分析学会会長。内閣府経済財政一体改革推進委員会評価分析WG・国と地方のシステムWG委員の他、国・自治体の各種委員を歴任。
品川から名古屋まで40分、大阪まで67分で結ぶリニア中央新幹線。当初は2027年の開業を見込んでいたが、静岡工区における水を巡る問題の懸念から、開業は大幅に遅れることになった。環境問題の対応はしっかりする必要があるが、着工から10年も経つ中で開業が延びれば、その分機会費用も大きくなる。
リニア中央新幹線は、時速500㎞を超える新たな高速交通機関であり交通分野のイノベーションである。現在、品川から名古屋はのぞみで約1時間30分、品川から大阪は2時間20分程であるため、リニア中央新幹線が開業すればそれぞれ約50分、約70分の時間短縮となる。このことは人の生活にも企業活動にも大きな効果をもたらすが、経済効果という視点で見れば、第一に生産性の向上が期待できる。
日本経済は失われた30年といわれ長らく経済成長が鈍化しているが、これには生産性の停滞が大きく響いている。DXなど効率性を高める投資がなされないなど様々な要因があるが、遅々として進まない生産性の向上において、リニア中央新幹線が果たす役割は大きい。例えば、リニア中央新幹線が開業すれば、品川・名古屋間の往復で約2時間の時間短縮となるが、果たして個々の企業努力でその分の生産性向上が容易にできるだろうか。その点、リニア中央新幹線は、「利用する全てのビジネス客」に2時間分の生産性向上を与えることになり、中小企業を含め企業全体の生産性を底上げすることに寄与する。
2020年からのコロナ禍でリモートワークが盛んに導入され、出張で時間を費やす必要が無くなったことで生産性が増したと実感したビジネスパーソンも多いだろう。一方で、フェース・トゥ・フェースが少なくなったことで社内や顧客とのコミュニケーションが難しくなり、その面では生産性が下がったとみる向きもある。そのような中必要なのは、適度なリモートワークとフェース・トゥ・フェースのハイブリッドな働き方である。リニア中央新幹線は後者のフェース・トゥ・フェースを必要とする場面での生産性向上に極めて大きな効果をもたらすのである。リニア中央新幹線による1回の出張で節約された2時間は、新たな営業先への訪問に充てても良いし、事務作業に充てても良い。また、その分早く帰宅してジムに通うなど余暇を楽しむ人がいても良い。そのことがまた新しいビジネスを生んだり、消費需要を拡大したりすることに繋がる。このように、企業の生産性の向上は自社の生産増に繋がるだけでなく、他産業にも波及していく姿として捉えられる。
このような波及効果は企業が多く立地する大都市だけではない。例えば中間駅ができる岐阜県中津川、長野県飯田などは歴史文化や自然に富み、周辺には温泉や観光スポットなども多数ある。これまでは名古屋市民にとってもそれなりに時間のかかる場所であったし、東京の人たちにとっては馴染みのなかった地域だったかもしれない。しかし、例えば金曜日に仕事が終わった18時に名古屋駅を出発しても、これらの地域の宿での夕食に十分間に合い、仕事の疲れを癒すことができる。翌日丸一日周辺を観光しても、日曜日一日はゆっくり自宅で過ごしたり買い物したりもできる。このように数分の時間短縮ではない1~2時間の時間短縮は、人々の生活を変え観光面での経済効果も期待できる。
ところで、日本経済にとって人口減少、とりわけ生産年齢人口の減少は、産業の供給力に負の影響を与える可能性がある。働く人の能力の向上や省力化のためのAIやロボティックスの導入が必要であるが、これも十分に浸透しつつあるとは言い難い。リニア中央新幹線は、ワークライフバランスの達成に寄与することで、優秀な働き手が企業で活躍する基盤となりうる。例えば、これまで結婚や出産で企業での活躍が制限されていた女性も多いだろう。出張を伴う業務の場合、朝10時からの東京での会議に出席するためには、8時には名古屋駅を出なければならないが、リニア中央新幹線ができれば9時に名古屋駅を出ればよい。そうであれば子どもを保育園に預けてからでも会議に間に合い、12時から会議の参加者とランチをしても14時には名古屋のオフィスに戻れる。その後残務をしても夕方には子供を保育園まで迎えに行けるのである。そうなれば今までは活躍の場が限られていた人材が様々な職種に就けたり、企業は有能な人材を新たに雇用することも可能になる。
ここまで主に生産性向上と労働力供給という面から経済効果を見てきたが、これらはストック効果と呼ばれる。リニア着工前に国の交通政策審議会で示された生産額ベースの年間の経済効果8700億円は、応用一般均衡モデルという経済モデルで推計されているが、本稿で示した効果を全て捉えているわけでない。さらにいえば、リニア中央新幹線の効果にはストック効果以外に建設中のフロー効果もある。フロー効果は建設産業だけが得るものではなく、コロナ禍で低迷する景気を広く下支えしてきた。建設に必要な資材やサービスの中間需要や雇用される労働者の消費需要により経済効果が様々な産業に波及し、またその調達先は全国に及ぶため工事沿線地域以外の全国に波及する。
また、開業すれば南海トラフ地震時には東海道新幹線の代替路として日本経済を支えることも可能であるが、その効果は今まで示したストック効果にもフロー効果にも入っていない。リニアの開業の遅れは得られるはずの機会を得られないという機会費用だけでなく、災害リスクを更に大きなものにしてしまうのである。
リニア中央新幹線に限らず人間社会が行う全ての活動にはプラスとマイナスの面がある。現代においては、経済・社会・環境の3側面を総合的に捉え、マイナスを如何に小さく抑え、プラスを如何に大きくするかが重要である。その意味においては、工事に伴う住民の生活や環境に対する負荷を軽減しつつ、リニア中央新幹線が持つポテンシャルを最大限発揮するような意識と取り組みが大切である。
2024年12月2・16日号 週刊「世界と日本」第2282・2283号 より

《いとう たつみ》
1952年生まれ。政治評論家 (政治評論 メディア批評)。講談社などの取材記者を経て、独立。政界取材30余年。中曾根内閣時代、総理官邸が靖国神社に対し、“A級戦犯”とされた英霊の合祀を取り下げるよう圧力をかけた問題を描いた「東條家の言い分」は靖国神社公式参拝論争に一石を投じた。著作多数、夕刊フジ「ニュース裏表」(木曜日発売)、自由民主「メディア短評」の執筆メンバー。ラジオ日本報道部客員解説委員。
総選挙の結果、「多数なき国会」が出現した。
それにしても、有権者は実に微妙な議席配分をしたものだと思う。政権継続を目指した自公に過半数を認めなかっただけでなく、「政権交代こそ最大の政治改革」を訴えた立民にも第一党の座を与えなかった。しかも、維新、国民民主を合わせても自公の議席数に届かなかった。これでは立民を中心とする野党も多数派を形成することができない。
世論調査によれば半数以上の人がこうした選挙結果を歓迎しているようだ。少数政権となった自公両党が野党の意見を取り入れつつ、景気・物価対策などの政策課題を解決していく「熟議の国会」を期待しているのかもしれない。しかし、はっきり言って、それは幻想というものだ。
「多数なき国会」は議論が分かれる問題の結論を出すことができない。決められるのは大多数が賛成している案件だけだ。強い反対論が存在する問題であればなおさらだ。要するに「決められない国会」ということだ。
こうした状況を解消するためには、政策の近い政党同士が連立または連携関係を構築する以外に道はない。これまで参院で与党過半数割れになることはあったが、衆院でどの政党にも多数が与えられなかったことは、55年体制が出来上がって以降、初めてではないか。
自公が国民民主に政策協議を持ちかけたのは当然の成り行きだ。もし、この誘いに国民民主が乗れば、「多数なき国会」状態は解消し、通常の与野党対決型の国会に戻る。
はたして、自公と国民民主との連携は成立するのか。この原稿を書いている時点では、協議が始まったばかりで先行きは見通せていない。しかし、部分的・時限的に合意することは可能でも、全体的な合意に達するのは難しいのではないかと予想する。
なぜか。
自公政権に協力することは、自公とともに政治に対する責任を共有することを意味する。それは自公に対する国民の批判を引き受けることに他ならない。
国民民主は、同党が選挙で訴えた経済政策、とりわけ所得税がかかる年収の最低ライン「103万円の壁」対策などの実現を与党に迫っている。一見、国民に歓迎される政策のように見えるが、どんな政策にもデメリットはある。
例えば、「減税するにしても『103万円の壁』を解消することが、一番合理的なのか」といった批判が出てくるかもしれない。あるいは、「もっと支援すべき層に狙いを絞った政策の方が効果的ではないか」との議論もあるだろう。自公と連携するなら、そうした批判の矢面に立つ覚悟が要求される。さらに、この案を受け入れる条件として「その他の政策に賛成せよ」と言われて、国民民主として「了」とすることができるのか。
現時点では議席を4倍に伸ばした政党として期待を集めているが、与党と一緒になれば「与党の補完勢力」とのレッテルを貼られてしまうリスクもある。公約実現をアピールできるメリットもあるが、全体としてはリスクやデメリットの方が大きいと考える可能性が高い。まして、来年夏に参院選が控えているなかで、あえて「火中の栗を拾う」決断はできないのではないか。
では、「多数なき国会」状態が解消されなかったらどうなるのか。結論から言えば、「もう一度選挙」ということにならざるを得ない。
デフレ脱却を目前にして、政治の停滞が経済運営の足かせとなることは疑いがない。また、激動する国際情勢の中、「決められない政治」がもたらす損失は極めて大きい。それに、与野党ともに、もう一度選挙を行うことは大きな負担だ。できれば「もう一度選挙」は避けたいというのが本音だろう。
しかし、国政を運営するなかで、どうしても譲れない一線はある。遅かれ早かれそうした事態がやってくるのは必然的といえるのではないか。
石破首相を代えることで局面の転換を図る「説」もあるが、筆者はその可能性は少ないと考える。
かつての自民党は派閥が強固で、後継総裁の「話し合い選出」が可能だった。しかし、今はそうではない。総裁選の手続きなしに後継総裁を選出することは不可能だ。国会開会中に総裁選を行った例はあるが、その間、国会は空転する。そうした政治空白を野党や世論は許さないだろう。
ということは、石破首相が途中で政権を投げ出さない限り、少なくとも来年の通常国会が終了し、参院選が終わるまでは自民党は石破首相を支えるしかないのではないか。仮に首相を代えたところで衆院の議席数は変わらず、政権運営の苦境を脱することはできない。いずれにしても、解散・総選挙で改めて国民の審判を仰ぐしか手立てがないということだ。
思えば、1990年代の政治改革には「カネのかからない選挙制度」だけでなく、今回のような「多数なき国会」とならない選挙制度を実現するとの目的もあった。その背景には、1990年に発生したイラクのクウェート侵攻に対し、国際社会から人的貢献を求められたわが国の意思決定に時間がかかり過ぎたことへの反省があった。コンセンサス重視の「決められない国会」ではなく、多数派の責任による「決められる国会」へ。それが小選挙区制中心の選挙制度を導入する理由だった。
そうした選挙制度の下で中選挙区制時代にもなかった微妙な議席配分の国会が出現した。なんとも皮肉な結果という以外にない。
筆者は今年7月1日付の当欄で、自民党の「一強体制」が終わり、「全弱体制」になると予想した。そして、それが高ずると「流動化」以上に政治が右往左往する「政治の液状化」状態に陥る可能性があることを述べた。その後の展開を見ていると、想像以上のテンポで危惧する方向に進んでいるように見える。
「もう一度選挙」がいつ行われるかは分からない。それは、操縦不能な飛行機に例えられるかもしれない。石破首相としては、できるだけ政局を落ち着かせたうえでタイミングを計ろうとするだろうが、「多数なき国会」のなか、どこまでコントロールできるか疑問だ。
わが国の政治は緊急事態に陥ったことを認識する必要がある。
2024年11月18日号週刊「世界と日本」第2281号 より

《こみね たかお》
1947年生まれ。69年東京大学経済学部卒業後、経済企画庁入庁。経済研究所長、物価局長、調査局長などを経て、2003年から法政大学政策創造研究科教授などを歴任。著書に「平成の経済」(日本経済新聞出版、2019年、第21回読売・吉野作造賞)など多数。
衆議院選挙の結果、与党が過半数割れとなった。こうした情勢下、経済政策を政治的に誰が中心となって担うのかについての不確実性が高まっている。しかし、誰が担おうと、今求められている政策の基本方向は変わらない。筆者は、経済政策については、次のような三つの大きな方向転嫁が求められていると考えている。
一つは、「デフレ脱却最優先」から「ポストデフレ期の経済政策」への転換である。政府は本年6月に閣議決定した骨太方針(経済財政運営と改革の基本方針2024)で、経済政策の第1の目標として「デフレ完全脱却の実現」を掲げている。石破新総理もしばしば「デフレからの脱却」に言及してきた。筆者はこうした政策姿勢を改め「ポストデフレ期」の政策姿勢に改めるべきだと考えている。
筆者から見ると、政治的に「デフレからの脱却」を熱心に進めようとしたり、多くの人がそれに期待を寄せているのはやや不思議である。この点を見るために、まずは「デフレからの脱却とは何か」という定義を確認しておこう。これについては、内閣府が2006年3月に「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」という明確な定義を示している。
要するに、物価上昇率がマイナスにならない状態が確保されれば、デフレから脱却したことになるのであり、デフレからの脱却を進めるということは「物価が下がらないようにする」ことなのである。しかし、物価上昇に苦しむ国民が求めているのは、「物価が上がらないようにする」ことである。デフレから脱却しようとすることは、国民の希望に反しているのだ。
では、ポストデフレ時代の経済政策とはどんなものか。具体的には、デフレからの脱却を目指すのではなく、インフレの防止を目指すべきだ。また、金融政策も当然正常化すべきだ。現在政府が目指している「賃金と物価の好循環」というスローガンも軌道修正が必要だ。物価が上がってその分賃金が上昇し、その賃金コストの上昇分だけ物価が上がるという循環を繰り返していると、確かに物価の上昇は続くのだが、実質賃金は不変なので、国民生活は全く良くならない。実質賃金を引き上げるには、付加価値生産性を引き上げて、物価以上の賃金上昇を実現する必要があり、政策的にはそれを目指すべきである。
二つ目は、ばらまき型の財政から持続可能な財政への転換である。今回の衆院選挙に際しての各党の公約を見ると、どの党も「あれもやります、これもやります」という「ばらまき合戦」になってしまっている。このまま進んでいけば、ただでさえ国際的に見ても極めて悪化した状態にある日本の財政事情はさらに悪化するだろう。
前述のように日本経済がデフレから脱却したと考えると、これからは物価の上昇が高まり、日本銀行は金利を引き上げていく。長期金利の上昇は当然国債発行金利の上昇を引き起こし、国債の利払い費も増える。これまでのように、財政を打ち出の小づちのように使うことは許されなくなる。
こうした困難を乗り越えて、財政の維持可能性を保つためには、どうしても総理の強いリーダーシップが必要だ。そういう総理はかつては存在した。例えば、1996年1月に発足した橋本龍太郎内閣は、消費税の引き上げ(3%から5%へ)を実現し、具体的な歳出削減を盛り込んだ財政構造改革法を成立させた。2001年4月に成立した小泉純一郎内閣も「小さな政府」を掲げて、熱心に歳出削減に取り組んだ。今後はこうした例にならって内閣を挙げての財政改革が推進されることが求められる。
三つ目は、人口政策の「人口減少ストップ型」から「人口減少との共存型」への転換である。日本の人口は2010年以降減少を続けている。これに対して政府は少子化対策に力を入れており、人口減少に歯止めをかけようとしている。衆院選挙の各党の公約を見ると、いずれも少子化対策に熱心だ。
しかし今や、人口減少をストップさせるのは不可能である。この点は、出生率(合計特殊出生率、一人の女性が一生の間に産む平均的な子供数)の動きからも確かめられる。人口減少をストップさせるには出生率は2・07以上でなければならない。ところが、最新の2023年の出生率は1・20である。
「強力な少子化対策を講じれば出生率は上がるだろう」と多くの人は考えているようだが、これも簡単ではない。この点を確かめるために「希望出生率」の水準を見よう。これは、結婚したい人は全て結婚し、産みたいと考える子供数が希望通り実現した場合の出生率である。この希望出生率は、かつては1・8程度であったが、新型コロナ感染症の後は1・6程度に低下している。若者の経済状態を改善しても、子育ての教育費負担を軽減しても、出生率は1・6以上には高まらないのである。
こうした状況を踏まえると、これからは人口減少を所与の条件として、国民のウェルビーイングを高めていくという方向に向かうべきだろう。筆者はこれをスマートシュリンク(賢く縮む)と呼んでいる。「シュリンク(縮む)」という言葉には負のイメージが伴いやすいが、それは正しくない。多くの人は、人口が減ると、経済も国民の所得も税収も減っていく世界をイメージするかもしれない。しかし、既に日本は2010年頃から人口減少社会に入っているのだが、2010年と2023年と比較してみると、GDP(実質)は9・1%、同名目は17・1%、個人消費(名目)は12・1%、企業の経常利益は122・2%(法人企業ベース、2010年度と22年度の比較)、国税収入は67・8%増えている。
人口が減っても、現実の経済は、生産性が上がり、付加価値が増えて、拡大し続けているのである。その生産性は今後さらに高めることが可能だ。人口減少の負の影響を克服して、スマートシュリンクを進めることこそが、ほとんど唯一の国民のウェルビーイングを高める道である。
以上のような政策転換が容易でないことは分かっているのだが、いずれも何時かは転換を迫られることばかりである。先見性をもって将来を先取りした政策運営を行って欲しいものだ。
2024年10月15日号週刊「世界と日本」第2279号 より

《しおた うしお》
1946年高知県生まれ。慶大法卒。雑誌編集者、月刊『文藝春秋』記者などを経て独立。『霞が関が震えた日』で講談社ノンフィクション賞受賞。『大いなる影法師』、『昭和の教祖 安岡正篤』、『日本国憲法をつくった男 宰相幣原喜重郎』、『憲法政戦』、『密談の戦後史』、『内閣総理大臣の沖縄問題』、『危機の権力』、『解剖 日本維新の会』、『大阪政治攻防50年』。近著に『安全保障の戦後政治史』など著書多数。
10月1日、石破茂首相が登場した。9月27日の自民党総裁選は決選投票での逆転勝利だった。国会議員票は189対173で、高市早苗氏との差はわずか16票である。この結果を見ると、自民党は大きく勢力2分の党内分裂状態と映る。
石破、高市の両氏は路線や理念では、共に「保守・右寄り・タカ派」を自認するが、大きな違いもある。石破氏は田中角栄元首相、高市氏は岸信介元首相の政治の継承者という顔だ。その意味で、今回の総裁選は戦後保守政治の2潮流の対戦という一面もあった。
石破氏はかつて取材で、「政治の師は田中さん」「民意を知り、民意を実現するのが政治、という姿勢を学んだ」と答えた。
高市氏については、2021年の総裁選の翌日、安倍晋三元首相がインタビューで「祖父の岸が築いた自民党の本来の役割と目指す方向を見つめ直す。そのために擁立した」と明かした。3位に終わった高市氏を「岸政治の再現者」と見立てて支援したのだ。
自民党の保守路線には、予算ばらまきや既得権益確保を望む層も含め、草の根の国民の声を大切にする民意型と、伝統的思想に基づく「国家・国益重視」の理念型の2つの基本形がある。石破氏は民意型、妥協を許さない国家主義者の高市氏は理念型の代表選手だ。
争点のテーマでは、憲法改正、靖国神社参拝、集団的自衛権行使、選択的夫婦別姓が議論となる。
石破首相は「憲法第9条2項の削除」を唱える改憲派だが、現実の政治では「改憲より経済成長」が持論で、改憲は「急がず」という立場だ。対する高市氏は総裁選の党主催討論会で「『日本人の手による憲法』への幅広い改正」を訴えた。積極的改憲論者である。
靖国では、首相に近い防衛相の中谷元氏は石破氏について、「公式に参拝したことがない。中国や韓国に対しても排他主義的ではない」と評した。一方の高市氏は総裁選出馬の記者会見で「国策に殉じ、祖国を守ろうとされた方々に敬意を」と参拝続行を明言した。
集団的自衛権では、14年に安倍内閣が行使容認、安全保障法制の制定に舵を切った。当時、高市氏は自民党政調会長として政策面で政権を下支えした。
14年の内閣改造で、石破氏は防衛相就任要請を断った。代わって引き受けた中谷氏が安倍氏と石破氏の差異について「集団的自衛権容認という点は同じだが、安倍さんは『限定的容認まで。それ以上は改憲が必要』と。石破さんはそうではなかった」と回顧した。石破氏は「現憲法下でも集団的自衛権の幅広い行使は可能。そのために安保法制の制定を」という考え方だった。
注目の選択的夫婦別姓でも、総裁選で姿勢の相違が明らかになった。積極派の石破氏は「基本的には賛成」と唱える。消極派の高市氏は「旧姓を通称使用できるように地方自治体などに義務付けを」という点にとどめた。
高市氏は石破政権の人事で総務会長就任要請を断り、「協力拒否・無役」を決めた。安倍氏は12年の総裁選で同じく逆転勝ちし、直後の人事で相手方の石破氏を幹事長に起用した。高市氏はその例を手本に、幹事長なら受諾の方針だったが、望みがかなわず、「党内野党」を選択した。
とはいえ、自民党でナンバーツーに躍り出た高市氏は、現段階では誰もが認める「ポスト石破」の最有力である。「石破政権の早期終結」も視野に、「岩盤支持層」など、党内外の高市支持勢力の結束維持と基盤拡大を最優先にするのが得策という計算だろう。
その点では異論もある。麻生太郎元首相は政権獲得前の07年と08年、1年で終わった第1次安倍と福田康夫の両政権の末期、共に約1カ月だけ幹事長を務めた。当時、少数派ながら福田退陣の直後に政権を握ったのは、2代続けて幕引き役を引き受けたのが幸いしたという分析もある。
麻生内閣で官房副長官だった腹心の鴻池祥肇氏はその場面を振り返って、「政治家として一番大事なのは、泥船に飛び乗って一緒に沈むこと。桟橋で見送って、泥船が沈むのを見ていたら、誰も敬愛しない」と語った。
高市氏の強みは、揺るがない保守思想、1993年の衆議院初当選以来、自由改革連合、新進党、自民党と歩きながら約30年を生き抜いてきた政治家としての生命力などだ。
他方、弱点は、我が強く、自己中心的で、しばしば「人柄に難あり」と評されてきた個性、といわれる。猛進型の裏返しで、バランス感覚、複眼思考、柔軟性に欠ける点も克服課題のようだ。
僅差の惜敗の直後、相手方の弱体新政権にどう対応すべきかという判断では、もしかすると、荒波に船出する泥船の新政権を桟橋で見送るのではなく、沈没も覚悟の上で泥船に同乗するという選択肢を考慮したほうがよかったかもしれない。
保守2大潮流という党内構図を抱えた自民党の今後はどうなるのか。民意結託型の石破首相は「民意に聞く」という自分流に徹していきなり衆議院の解散・総選挙というカードを切った。答えは総選挙の結果次第だが、大きく2つの「次代」が予想できる。
第1は、衆院選で自民党が何とか単独過半数を確保し、泥船ながら、「石破丸」が沈没せずに航海を続けるケースである。結果、党内対立を超克して、自民党のもう一つの伝統である「包括政党」という持ち味を発揮できれば、「大逆風」という現在の党危機の克服も不可能ではないが、視界ゼロだ。
第2は、自民党の単独過半数割れで、政治大激動・政党大再編の幕が開く展開である。「混乱政治・日本弱体化・失われた時代」の再来という悲劇的な予測も少なくないが、大激動・大再編の始まりが新しい日本の夜明けとなる可能性もないとはいえない。
自民党の2つの潮流を背負う石破首相と高市氏は、日本政治の旧構造と旧体制の幕引き役で終わるのか、それとも新時代の扉を開く先導役となるのか。民意の回答が、次の衆院選の第一の見所である。
2024年10月7日号週刊「世界と日本」第2278号 より

《かわくぼ つよし》
1974年生まれ。東北大学大学院博士課程単位取得。専門は日本思想史。現在、麗澤大学教授。論壇チャンネル「ことのは」代表。(公財)国策研究会幹事。著書に『福田恆存』(ミネルヴァ書房)、『日本思想史事典』(共著、丸善)、『ハンドブック日本近代政治思想史』(共著、ミネルヴァ書房)など多数。
これまで保守の思想の歴史を勉強してきて、改めて、保守の思想の本質は何かと考えると、それは、人間という生き物を愛することに尽きるといえそうだ。保守とは人間を愛することである。言い換えると、人間という、不可思議で、なんとも割り切れない存在に深く目を向け、そうしたありようを愛情と愛着をもって深く受け容れること、そしてそこから出発して、人間世界のあり方を考え、様々な問題に対応していくこと、それこそが保守の根本的な立場といえる。
人間は、実に、割り切れない、両義的な存在である。善と悪を同時に抱え持ち、敬虔であるとともに猥雑であり、泣きながら笑い、笑いながら泣き、信じながら疑い、疑いながら信じる、矛盾と逆説とアイロニーに徹頭徹尾貫かれた存在、それが人間であろう。複雑で、非合理で、不可知で、ときに驚くほど多面的である、それが人間の姿である。他者のことどころか、自分のことだって、その真の姿を見通すことはできない。自己内省したところで、自分という存在の本質が見えるものでもないだろう。それゆえにまた人間は内省しようとするのだろうが。一体自分を突き動かしているものは何なのか、自分が追い求めているものは何なのか、いくら自問自答しても確かな自己認識には決して到達しえない。人間は誰しも、人間知性そのものの限界を感じながら生きている。神や仏・天のように全てを見通し達観したいが、人間に見えるものはほんの一部に過ぎない。その一部も、朧げな姿をまとって、あきれるほどに時間をかけて徐々に見えてくるだけである。人間は有限であるのに、核心的なものを理解、了解するためには無限の時間を要するかのようだ。こうした人間の姿は、まさに人間の自然の姿、宿命の姿であり、否定したくても否定しようのない、まさに絶対肯定の態度で受け入れるほかない、人間の根源的事実そのものであろう。であるならば、その事実を愛情をもって受け入れ、そこから、良い意味での人間らしい世界のありかたを模索する生き方こそが健全であるといえよう。
保守思想が立脚するのは、こうした自然で無理のない、健全な人間観である。というよりも人間の矛盾した姿をありのままに見るならば、保守の立場に立たざるをえないのである。保守は、そんな人間を愛し、そんな人間の可能性を信じ、そんな人間の歴史に敬意を払う思想なのである。それに対し、保守を反動呼ばわりして攻撃する革命派や進歩派、左派・社民リベラルは、どこか人間を軽んじている。だから、人間よりも自分達の信じる理念や信念、正義、理論を上位に置こうとする。そこから人間世界を管理・支配・指導しようとする。そこに無理が生じる。理論と人間の実際とがかみ合わないのだ。人間の世界は、主義やイデオロギーよりも、もっと広く、そして深い。単一の視点から掴めるような底の浅いものではないのだ。それでも彼らは、自分たちの主義主張・イデオロギーを押し通そうとする。そこで何が起こるかは、共産主義革命運動によってもたらされた粛清の歴史を見れば明らかである。左翼だけではない、右翼の革命運動でも、同じことは指摘できる。どちらにもしても、自分達が信じる一面的な正義だけで人間・社会を管理・支配しようとすれば、人間・社会の自然な姿は崩壊・解体してしまう。現代の西側諸国では、日本も含め、社民リベラルが推進するポリコレ、キャンセルカルチャー、Wokism(過激な反差別主義)が自然な人間世界を破壊しようとしている。彼ら・彼女らの中には不健全で、歪んだ知的エリート主義があり、自分達の知的優位性・特権性の誇示のために運動を展開しているような側面があるから、人間の現実の姿など最初から関心がないのかもしれない。そこには、人間存在に対する愛情の眼差しが全く見られない。それどころか「知的エリート」たちの権力基盤である大学や出版、メディア、教育などの領域を総動員して、人間世界の自然・摂理を無視するかのような破壊活動に血道をあげている。反差別と人間の自然な姿を肯定することとは決して対立するものではない。人間という生き物の宿命に愛着を持ちながら、反差別運動を展開することはできるはずだ。
国際情勢に眼を転じても、冷戦崩壊後のアメリカが主導してきた国際政治は、あまりにも善・悪の二元論・二分法に支配された、非人間的なものだった。アメリカ型のリベラルデモクラシーこそ人類の正義とばかりにイデオロギーで世界を支配し、その覇権主義に対する反感、脅威を抱いたスラブ・ロシアはウクライナ侵略戦争という手段を用いてアンチテーゼの挙に出た。人間が多面的であるように、国家・国民・民族もまた多面的であり、それぞれの個性・感性・価値観・文化・美意識を持って生きている。それらに対する敬意と配慮、関心こそが国際社会の基盤にならなければならない。人間の多元的な世界を破壊・解体する帝国主義・植民地主義・選民主義は、国際政治の世界から一掃しなければならない。
そして、それが出来るのは、日本という文明・国家ではないだろうか。少なくとも日本には、そのための思想的貢献が出来るはずだ。日本にはヘゲモニズムや選民思想とは対極的な平等思想を育んできた歴史がある。その平等の範囲は人間以外の生き物を含み、自然全体に及ぶ。生きとし生けるものが皆それぞれの個性と特徴を活かしながら共にこの世界で調和しながら暮らしていくことを理想と考える共生・共存の思想が連綿と流れている。強者を主体とするヒエラルキーを設定しない日本の「多様性の哲学」を世界に広く訴え、それによって平和で友好的な国際世界を樹立すること。そのような人類の未来像を描き出し、その実現に向けて行動していくこともまた、日本の保守が今なすべき責務であるといえよう。
2024年10月7日号週刊「世界と日本」第2278号 より

《ますだ やすよし》
東洋大学・成蹊大学兼任講師、博士(経済学)。1958年生まれ。81年京都大学経済学部卒業後、富士銀行入行。88年、富士総合研究所に転出し、ロンドン事務所長、主席研究員等歴任。2002〜23年、東洋大学経済学部・大学院経済学研究科、情報連携学部教授。16〜18年、国立国会図書館専門調査員。専門は金融、国際経済。
「国際収支」というエコノミストしか見ない統計の名が、最近、総合月刊誌にも登場する。財務省の神田眞人前財務官が主催する「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋」懇談会の報告書が7月2日に発表されたからであろう。 神田前財務官は、「国際収支に国の経済力が表れる」と考え、国際収支統計から日本経済の課題を読み取ろうということで懇談会を開催したとのことである。もっともな問題意識である。以下、この財務省の報告書の内容を踏まえて「日本経済の課題」を筆者なりに考えてみた。
貿易・サービス収支の赤字が定着
日本は、1996年以降30年近く経常収支の黒字を計上してきた。2023年度も過去最大の25兆円の黒字を計上し、これは世界では中国、ドイツに次ぐ第3位の大きさである。しかし、2018年度からは貿易・サービス収支が赤字に転じる一方で、第1次所得収支の黒字が急拡大して経常収支を支える構図になっている。これを「貿易立国から投資立国に変わった」「クローサーの国際収支の発展段階説における『成熟債権国』の段階に入った」と捉える論者が多い。
まず、日本のお家芸のモノの輸出の衰えは明らかである。神田氏が「自動車の一本足打法」と嘆くとおり、今や巨額の資源・食料品の輸入を自動車関連の輸出では賄えず、2021年度から貿易収支は赤字となっている。
サービス貿易についても、サービス輸出にカウントされる訪日外国人(インバウンド)増加により旅行収支黒字は急拡大したが、コンピュータサービス、著作権等使用料、専門・経営コンサルティングサービスからなるデジタル分野では巨額の赤字を計上している。その結果、2018年度以降、貿易・サービス収支は赤字が定着してしまった。巨額の貿易・サービス収支黒字を計上していた2010年までに比べ、日本産業の国際競争力が低下したことは明らかである。競争力を高め、再び貿易・サービス収支を黒字にすることが第一の課題である。その為には、生産性向上、労働市場柔軟化、人的資本拡充等、多様な課題がある。
巨額の所得収支黒字を大事に育てよう
他方で、日本の個人・企業等が保有する対外純資産が生み出す第一次所得収支の黒字が経常収支黒字を支えている。第一次所得収支の黒字は、2021年度から増加ペースを速め2023年度には36兆円に上った。主因は、円安と海外金利上昇による日本の投資収益受取の急増である。
日本の所得収支は、長期的に黒字である。長年にわたる経常収支黒字が累積して対外純資産(資産—負債)が世界最大に膨らんでいるからである。一部に「所得収支黒字の約3割を占める直接投資収益再投資は日本に還流せず、これを除いて経常収支を考えるべき」という論調があるが、これはおかしい。たとえ日本に還流しない再投資でも、対外直接投資の収益は日本居住者の所得であることに違いはない。
貿易・サービス収支が赤字だが、巨額の所得収支黒字が補い経常収支が黒字を維持するという国際収支構造を見て、「過去に汗水たらして稼いだ貿易黒字で貯金をため込み、今はその利子・配当の金融所得を頼りに生活する資産家」と否定的に捉える論者がいる。しかし、筆者は恥ずべきではないと考える。20世紀初頭まで覇権を握っていた英国は、戦後産業が衰えても長らく海外からの金融所得に頼って高い所得水準を維持できた。日本も今後長らく、所得収支黒字で所得水準を維持できると期待される。
むしろせっかく保有している巨額の対外資産から、できるだけ大きな投資収益を得て所得収支黒字を拡大することが肝要であろう。そのカギは、日本の金融機関の運用力と、対外直接投資の質の向上が握る。これが第二の課題である。
経常収支黒字を保つには財政再建が不可欠
なお、何が何でも経常収支が黒字でなければならないわけではない。企業は赤字が続けば存続できないが、国は対外ファイナンスさえできれば経常収支が赤字でも繁栄できる。米国が好例である。そもそも世界の経常収支の合計はゼロサムであり、すべての国が黒字なることはできない。
経常収支が赤字でも、ファイナンスに支障が生じないように国債の信用力を保ち、対日投資が活発になされる環境を整備し、円を国際化し、海外から円滑に資金流入がなされることが重要である。特に貧弱な対内直接投資を活性化することは不可欠である。これが第三の課題である。
とはいえ、できれば経常収支は黒字であった方が良い。その為には、前述の稼げる産業を育てること(第一課題)も重要だが、財政赤字をこれ以上拡大させないことも重要である。経常収支は、家計・企業・政府の各部門の純貯蓄(貯蓄—投資=資金余剰)の合計である国内部門の資金余剰と等しい。現在は、政府部門の資金不足を、家計・企業部門の膨大な資金余剰で補って余るので経常収支は黒字になっている。今後、企業利益は縮小し、家計の貯蓄率は高齢化に伴い低下し、家計・企業の資金余剰は縮小する。その時、政府の資金不足を縮小しておかねば、日本は経常収支赤字国に転落する。財政再建が必要であり、これが第四の課題である。
経常収支から為替レートを論ずるのは元々無意味
経常収支の細かい分析を基に円の需給、ひいては為替レートを語る論を最近よく目にする。「経常収支のうち収益再投資分は為替の需給に影響せず、これが経常収支黒字でも円安が進む原因だ」といった説明がなされる。しかし、国際収支は事後的な取引結果を記すだけであり、為替レートに影響する事前的な売買意欲は示さない。
また、経常収支は、理論上、対外資本流出入を示す金融収支と一致する。例えば、輸出で得た外貨を売れば円高要因となるが、その資金は必ず対外純投資(資本純流出)となりこれは円安要因となる。経常収支と、これに一致する金融収支は為替レートに逆方向に作用するのである。
経常収支が為替レートを決めるという「フロー・アプローチ」は、各国が変動相場制に移行した1973年直後には信じられていたが、その後経常収支よりも資本流出入の方が重要なファクターであることがわかり、神通力を失った。国際収支で為替レートを語る論はもっともらしいが、根本的に理屈が伴っていない。
2024年9月2・16日号週刊「世界と日本」第2276・2277号 より
退職代行が流行る社会は健全か
千葉商科大学
国際教養学部准教授
常見 陽平 氏
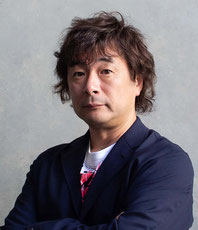
《つねみ ようへい》
1974年生まれ。北海道出身。一橋大学商学部卒業。同大学大学院社会学研究科修士課程修了。㈱リクルート等を経て現職。
「職業選択の自由、あははーん」たまにこのフレーズを思い出す。学生援護会(現:パーソル)が発行していた転職情報誌『salida』の1989年のCMだ。高橋幸宏と仙道敦子が出演する。このフレーズは「憲法第22条の歌」というタイトルで、シーナ&ロケッツによるものだった。覚えている人も多いことだろう。この「職業選択の自由」が脅かされている。主なものは就職差別、オワハラ(就活終わらせろハラスメント)、そして退職妨害だ。
出身地、家族構成、思想・信条に関する質問は、厚生労働省が採用選考において不適切であるとガイドラインを示している。しかし、連合の「就職差別に関する調査2023」によると令和になっても、2020年代になっても、採用選考における差別、不適切な質問が存在することが明らかになっている。たとえば、応募書類やエントリーシートで、「本籍地や出生地に関すること」の記入を求められたと答えた求職者は43・6%、面接では28・3%存在した。「採用試験の面接で、不適切だと思う質問や発言をされた」求職者も19・5%いた。「女性だからどうせ辞める」「恋人はいる?」「かわいいね」などと言われたという。
大学教員をしていると、学生からオワハラの相談をよく受ける。主なものは、他社を辞退しないと内定を出さない、内定承諾書を提出する、推薦状を提出させるなどというものだ。中には、内定辞退を申し出ると、研究にかかった費用を返金しろと迫る企業もあるという。
副業が広がる世の中ではあるが、多くの場合、新卒で入社するのは1社だけである。囲い込みに躍起になるのは、昔も今も変わらない光景である。バブル期などでは旅行、豪華な料理などでの接待まで行われた。現在は、圧の強い囲い込みが跋扈している。
大学で問題となっているのは、事後推薦状である。学校推薦の求人ではなく、自由応募であるにも関わらず、あとで教授の推薦状をもらうように迫るものだ。推薦状には、学生に対する教員からの評価を知りたいという意図もあるかもしれない。ただ、内定を辞退しにくくするという意図も見え隠れする。中には学部長や学長の推薦状を要求する企業もある。学校でも対応し切れない。立教大学、中央大学を始め、推薦状を書かないと宣言する大学も現れた。
そして、退職妨害だ。退職しようとする社員に対する「慰留」はともかく、これが過度になると退職妨害、さらにはハラスメントになる。辞めることに対して説教をする、転職先などに悪口を言いふらす、代わりを連れてくるように迫るなどの行為は悪質である。
このように、職業選択の自由が脅かされている時代だということを、まず理解しておきたい。ただ、背景にある企業の採用難も深刻である。若者の数は今後、減り続ける。大学生の数は維持されているものの、地方からは人材が流出していく。多くの業界で売り手市場となっている。採用担当者は経営陣からも現場からも「人材はなんとかならないのか」と圧をかけられ苦しんでいる。採用における差別発言・問題発言、オワハラ、退職妨害、すべて人手・人材不足で線でつながる。採用活動に注力しなくてはならず、未経験者が人事に配属され、人権などに関する理解が不十分の中、配属されるので、トラブルを起こしやすい。管理部門の中で、最も未経験者が活躍しやすいのが、採用担当なのだ。そして、人手・人材不足であるがゆえに、内定者に対しても、退職を申し出る人に対しても圧をかけてしまう。
話題の退職代行サービスはこのような前提を確認すると、見方が変わる。退職代行サービスとは、文字通り、労働者の代わりに退職の申し出や手続きを代行するサービスである。費用はサービス内容によっても異なるが、1回の退職手続きで2?5万円程度である。
このサービスが存在すること、費用がかかることなどを聞いて、頭がクラクラしている人もいることだろう。しかし、このサービスが注目されたのは、2010年代後半であり、年々、ニーズが高まっているという。この4月は新入社員の利用が増え、各社前年の数倍となったという。
このサービスを利用する人は、まさに退職妨害を避けられるという点が支持されている。退職を切り出すのは面倒で、新しい会社での新生活の準備に集中したい、スマートにやめたいという声もある。中には、大変にお世話になった上司や同僚に退職を切り出すのが辛いため、あえてこのサービスを使うという人もいるようだ。好き嫌い、是非は別として、このような理由から支持されていることは理解しておきたい。
一方で、退職代行が広がり、支持される社会を肯定できるのか。労働者の職業選択の自由、中でも「退職の自由」が脅かされているという自体を直視したい。誰もが自分で選んだ職業に就く権利をもっている。これは同時に、退職の自由を保障するものだ。会社に退職を制限する権利はない。退職代行サービスを使う気持ちは理解できなくはない。ただ、このサービスを活用しなくても、退職はできる。
企業も、引き止めのために圧をかけるのではなく、なぜ離職するのかを立ち止まって考えたい。もちろん、どれだけ魅力的な職場でも、様々な事情で退職せざるを得ないこともある。自分のキャリア形成を真剣に考える人ほど、新たなチャレンジをすることもある。とはいえ、働く環境、待遇、人間関係などに問題がなかったかを考えたい。
一生様々な場で(企業に所属するとは限らない)、様々な仕事をする、そのために学び続けるというのが、これからの社会である。いや、今もそうなりつつある。早期離職を防止しつつも、いざ人材が流出した際にどうするかを考えたい。
最近、増えているのが、「出入り自由」という世界観だ。採用試験に合格した人に入社時期を選んでもらう制度、たとえ内定辞退したとしても数年間有効な内定パスを出す企業、他社で合わなかった場合に、いきなり最終面接を受けられるファストパスを出す企業もある。また「カムバック採用」「アルムナイ採用(同窓会採用)」「ブーメラン採用」など、出戻り歓迎の制度をつくった企業もある。
退職代行サービスが生まれる背景を理解しつつも、職業選択の自由を改めて確認しておきたい。CMソングを歌ったシーナも鮎川誠も、出演した高橋幸宏もこの世にいないが、彼ら彼女たちのためにもこう歌いたい。「職業選択の自由 あははーん」と。
2024年8月19日号 週刊「世界と日本」第2275号 より

《たにぐち ともひこ》
富士通フューチャースタディーズ・センター特別顧問、筑波大学特命教授。安倍第二次政権で主に内閣官房参与として同総理の外交演説を担当。二〇二三年三月まで慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。一九五七年香川県生まれ、東京大学法学部卒。著書に『安倍総理のスピーチ』(文春新書)ほか。
日本は先の大戦に大敗して以来、承認欲求のオバケになった。
生来の不良にして更生不能の極悪人であるかに決めつけられ、心に深い傷を負った。
それ以来、何かにつけて良い子に思われたいと念じる習いは性となり、今日に至る。
日本人が集団としてかかった過剰な承認欲求という病の病歴は、実のところ長い。
丁髷を落として和暦を捨て、外国に合わせてニホンという本名に替えジャパンの通名を選び、おのれの姓、名をアベコベに名乗るまでした明治この方、百五十年以上も続くのがわれわれの宿痾、「良く思われたい病」だ。
いい加減、この病を退治する時がきた。国益を保全し、伸ばすため、他人の評価を気にしない心構えを身につけねばならない時だ。心臓に毛を生やす時、と言えば品下るか。
嫌われようが陰口をきかれようが自分は自分、何が悪いと言える国にならなければ、いまや国益を守ることはできない。のっぴきならない次のような難題が山積みだからだ。
例えば
①男系皇統の継続をいかに図るか。
②なぜ移民を今から制限しておくべきか。
そしてなぜ
③憲法九条の改正が必要か。
三例は、いずれも国家の根幹に関わる。
どんな国にし末代に残したいかの問いと、中身において同義だ。かつどれも喫緊の課題だ。
九条に一項を加え自衛隊の存在が憲法上正統であることを明記すべしとしたのが、故安倍晋三元首相の考えだった。一人前の国には必ず軍隊がある。日本とて同様と、追認するだけのことだ。
かつてと違い今日の米国は、さすがそれだけのことに眉をひそめなどしない。むしろ当然のことと受容する。
反発する国はあり、批判を煽るメディアもあろうけれど、ここで昂然胸を張り、日本にとって当然であるばかりかインド太平洋の安全にも資すことを言わねばならない。でなければ、いつまでもなめられる。それは日本へのさらなる軍事的挑発を誘引し、日本の安全保障を弱くする。その逆では決してない。
一例目と二例目は、日本が友邦・同盟国とみなす大半の諸国において反発か、少なくも違和感を喚起しよう。
①に対しては、女王が例えば異民族の男を婿に取り、生まれた女子がまた王になって何が悪いとする難詰が、②には、全人口に比し微々たる割合の外国人しかいないのに、早くも移民制限とは排外主義そのものだとする反発を招来しよう。
日本の皇室は、他のどの王室より格段に長い歴史をもつ。のみならず、男系一系を維持継続してきた点、世界にあるいかなる家系にも類を見ない。
言ってみれば人類史が古代以来引き継いだ宝物同然の存在なのであるから、そこに当世風の改変など加えるべからずと説き、説いてもわからぬなら、放置するのが至当だ。
世はDEIの時代。多様性(D・ダイバーシティ)を認め、差別をなくし(E・エクイティ)、誰も排除しない(I・インクルーシブネス)とする三徳目を高唱しない限り、企業も学校も存在を否定されかねない勢いだ。
とすると①への反発と違和はむしろ真っ先に国内から、とりわけ年来自民党を支えてきた経団連傘下企業の経営者などから湧き起こることを想定しておくべきだろう。
時を置かず、外国のメディアや知識人が批判の合唱に加わる。当該国指導者は影響を受け、対日関係を損ねるとまで言う者さえ現れるかもしれない。
あらゆる悪口雑言に耐え歴史と伝統を守り抜くには、「良い子」などではいられない。これをとくと弁え、かつまた相当の胆力を備えておく必要がある。わからず屋で結構、石頭と言われるならいっそ本望と思うべきだ。
日本にいま、なんらかの在留資格をもって住む外国人は三百四十一万人あまりいる。年々増加中であって、全人口に対する比率も着々と増えている。
労働人口減少の程度とその速度に照らしてまだ遅すぎる、長期に滞在し労働力となる外国人をどしどし入れるべしとするのが、日本政府における近年の傾向であって、経済界の総意でもある。
米加豪のような建国以来の移民国に加え、英国始め大半の欧州諸国は、この点で、日本を督促してやまない。
自分たちの国は移民がもたらす秩序の動揺に悩み抜いているというのに、日本だけ無傷でいるのを許すまじとでもいうような、ひそかなそねみがあるいはあるかもしれない。
さあらばあれ、急速な外国人流入が国益を損ねる理由は、日本の特殊事情による。
全在留外国人三百四十一万人のうち、大陸から来た中国人が約八十二万二千人を占める(数字はいずれも二〇二三年十二月)。その比率は四人に一人。
日本が外国人に門戸を開けば開くほど、右の比率で中国人が増えるのであるから、日本における外国人問題とは、すなわち最大集団をなす中国人の問題だと言い換えてよい。
中国人は法律によって、国家に求められたなら、知り得た事実を必ず開示しなければならない。また中国共産党党員は、党規約の定めによって、自分を含め最低三人の党員がいる場合、それが会社であれ学校であれ、また国の内外を問わず、党の基礎組織(細胞)を作って党との連絡を設けなければならない。
いままさにこの瞬間にも、理工系大学院の研究室や企業の研究開発部門に党と国家に絶対の忠誠を誓う・誓わざるを得ない人々が増えている。勢いを抑えることに日本の国益がかかる。この際に中国人を総数で抑制することは、日本国のリスク管理上むしろ必須だ。
以上三例に沿って述べてきた点は、政治家任せにせず、自分ならどんなレトリックで主張できるか各々想を巡らすべきだ。過激矯激に走らず、冷静沈着を維持すべきであることは言を俟たない。
もとより政治指導者の責任は最も大きい。いまほど総理大臣の信念と覚悟、勇気が必要な時はない。失うことのできないもの、守るべきものを守る胆力が土台として必要だ。そこからしか、強い言葉は生まれてこない。
2024年8月19日号 週刊「世界と日本」第2275号 より

《やもり かつや》
京都大学防災研究所教授。専門は、防災心理学。現在、日本災害復興学会会長、地区防災計画学会会長、日本災害情報学会副会長、自然災害学会副会長。防災功労者防災担当大臣表彰、兵庫県社会賞などを受賞。主な著書に、『防災心理学入門』、『防災人間科学』、『現場でつくる減災学』、『巨大災害のリスク・コミュニケーション』など。
今年元旦に発生した能登半島地震は、被災地に暮らす子どもたちにも大きな影響をもたらした。今回の地震では、道路網やライフラインが蒙った大被害のために、被災地の多くが「孤立」し、生活環境が非常に劣悪な状態に置かれた。このために、年度末の受験期を控えた学年を中心に、被災地の外へ集団で「一時疎開」(広域避難)する手段も講じられた。その数は数百人にも上り、募集のあり方、保護者の了解を得るまでの手続き、疎開先でのマネジメントに関する課題も指摘されている。
また、2月26日時点で、能登半島の六つの市町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)の小中学校の状況を、教育委員会のアンケートをもとにNHKがまとめたデータによると、全児童生徒(6525人)のうち、「避難所や親戚の家などから学校に通う」、「元の学校に籍を残しながら近くの別の学校に通う」、または「2次避難先の学校に通っている」など、『自宅外避難』の状況にある児童生徒が1457人(全体の約22%)に上り、地元を完全に『転出』し、「別の場所で他の学校に在籍している」児童生徒も192人(全体の約3%)いた。
通い慣れた学校、住み慣れた土地を離れることになった子どもたちと言えば、忘れられないエピソードがある。去ること30年前、阪神・淡路大震災(1995年1月17日)の被災地神戸市内で、当時小学校5年生の担任をしていたT先生からお聞きしたエピソードである。この学級は、4月以降、そのまま同じメンバーで6年生になり、T先生も持ち上がりで引き続き担任をつとめることになった。地震発生から2カ月半が経ち、学期もあらたまったことで、ほぼすべての児童が顔を揃えて6年生のスタートを迎えることができた。
ところが、T先生は、新学期早々、クラスの様子が少々おかしいことに気がついた。児童たちが大きく三つのグループに分断されていたというのだ。一つ目は、神戸の被災地で生活を続け、その間、自分自身が避難所で生活したり、ライフラインが十分でない自宅で生活したりしながら、避難所(他ならぬ自分たちが通っている小学校)で、炊き出し、清掃などのお手伝いに取り組んだ子どもたち。二つ目は、最初のグループと同じ環境で生活してはいたが、(主に保護者から)「避難所運営は大人に任せ、自分たちは勉強などに注力しなさい」という趣旨の言葉をかけられ、実際にそうしていた子どもたち。そして、三つ目のグループは、地元を離れて、神戸市内外の他の小学校に約2カ月通っていた子どもたち、である。
容易に想像がつくように、これら三つのグループの間には、「微妙な空気が流れていて、打ち解けるのが難しかった」(T先生談)。各グループには、それぞれやむにやまれぬ事情がある。でも、子どもだから、それを十分に察することができない場合もある。逆に、子どもからこそ、大人以上に敏感に違いは察してはいるのだが、クラスメートに対して自分の気持ちを上手に言葉や行動で表現できない場合もある。
能登半島地震の被災地でも、まったく同じことが起きていた。家族や地域が大変ななか、自分一人だけが遠方に避難していいだろうか、親が疲弊しているのに自分は学校に行っていいのだろうか。こういった罪悪感をもってしまった児童・生徒もいた。より落ち着いた(とされる)環境で受験勉強している同級生もいるのに、自分はまったく勉強が手に付かないと焦りを感じて、そのフラストレーションを周囲にぶつけた生徒もいただろう。あるいは、自宅の片付けや生活の立て直しに必死の大人たちを支えて、より小さな子どもたちの面倒を見た小中学生の逸話も数多く聞く。その経験からこれまでにはなかった自信や手応えを得た児童・生徒もいただろう。
では、こうした児童・生徒をどのように支えていけばいいのだろうか。筆者は、能登半島地震の被災地の子どもに対する支援を取り上げたテレビ番組の中で、「三つのキープ」という合言葉を呈示した。以下の三つである。
①「キープ・イン・タッチ」:原義は「連絡を取り合おう」という意味のフレーズ。能登半島の子どもたちのことを忘れずにいつも心に置く、そして折に触れて連絡をとろうという姿勢。
②「キープ・ペース」:被災した子どもたちが、焦らず、無理せず、それぞれのペースを守って新しい暮らしのリズムを獲得できるように支援すること。
③ 「キープ・ゴーイング」:ゴーイングは前に進むという意味。それぞれ自分のペースでいいけれど、基本的に「前向き」にものごとを受けとめていけるよう関わること。
前記の三つのキープに共通するエレメントを一つあげるとしたら、「長期性」(息長く)ということだと思う。前述の阪神・淡路大震災を小学生として体験した世代は、今、30歳後半から40歳くらいの年齢になっている。
筆者の周囲には、この世代の仲間が、自分の研究室のスタッフ(防災教育学が専門)を含めて何人もいる。あの日神戸のレスキュー隊の指揮を執っていた人物を父にもち、自身、消防士になった女性がいる。母親と弟を震災で亡くし、その後、小学校教員となった男性は、筆者が20年以上ご一緒している語り部グループの代表者に就任した。それぞれ、あの時の経験が、陰に陽に30年後の今を支えている。
この意味で、能登半島地震についても、今年元旦の出来事が、また、子どもたちが今進行形で体験していることが、10、20年後、そして30年後、彼/彼女の人生や生活にどのような形で位置づけられることになるのか—それこそが肝心である。目の前の児童・生徒たちとどう向き合うのか。喫緊の課題をどう解決するのか。それはそれで、もちろん大事である。しかし、それだけだとかえって行き詰まることもある。目先の課題解決に目を奪われて、逆に判断や対応を誤ることもある。被災地の子どもたちの未来を長い目で見ていく必要がある。











