刻々と変化する国際情勢を各国の政治・経済など様々な視点から考察する。

《しゅ けんえい》
1957年、中国上海生まれ。上海国際問題研究所付属大学院修士課程修了。学習院大学にて博士号(政治学)を取得。1986年、総合研究開発機構(NIRA)客員研究員として来日、学習院大学・東京大学非常勤講師などを経て現職。
2025年8月18日号 週刊「世界と日本」第2299号 より
中国世論の読み方―ネットメディアの台頭
東横学園大学 客員教授
朱 建榮氏
日本人の多くは、中国の当局と民間の主要な論調、すなわち「世論」を読み取るなら、真っ先に『人民日報』や『環球時報』が思い浮かぶだろう。
実はおよそ10年前から中国の街角から新聞雑誌販売のスタンドは姿を消している。JR線の駅構内の「キオスク」に似たような売店やコンビニも中国の駅にあるが、それもほとんど新聞を販売していない。『人民日報』は郵便局の一部で販売されるが、その発行部数の95%以上は共産党の細胞組織や行政機関の購読に頼っている。自民党機関紙『自由民主』(旧『自由新報』)とほぼ似たような販売方法だ。一方、『人民日報』傘下の『環球時報』はタブロイド紙として1993年に創刊され、ナショナリスティックな論調が多いとの評判だが、親新聞の販売部数の激減でグループ全体の経営難を軽減するために創設された、「販売優先」の産物と聞いている。今は依然人気が高いが、読者の9割以上は新聞紙ではなく、そのネット版「環球網」を読んでいる。
中国「世論」の主要陣地はこの10年、激変している。19年11月29日付「光傳媒」サイト掲載の中国人の「情報入手」ソースに関するアンケートによると、SNSは圧倒的に中心になっている。複数回答だが、75・25%は『微信』(WeChat)から、39・02%は中国版「TIKTOK」から、26・61%は「今日頭条」サイトから、20・03%は「微博(ミニブログ)」から情報を取得しているとの回答だ。伝統的な紙媒体(新聞と雑誌)と挙げたのは僅か0・68%で、老人を中心にテレビと挙げたのも6・56%にとどまり、ほかに4・24%は食卓、会議、家族等と挙げている。
この調査結果で分かるのはまず、中国国民の圧倒的多数は新聞やテレビ情報を頼りにしていないことだ。政府系メディアへの不信と、官製報道の「つまらなさ」とともに、それにとって代わるネットメディアが急速に広まった事情もある。
その最大の背景はインターネット利用者の急増にある。中国ネット情報センター(CNNIC)は毎年2回、全国のネット利用動態を発布するが、それによると、24年末まで中国のネットユーザーは11・08億人に上り、ネット販売利用者は9・74億人、ネット行政サービス利用者は10億人超になっている、という。
社会主義中国は世論と情報を統制し、ネット利用を制限するものだと思われがちだが、なぜ日本よりもネット利用の普及率が高いのか。理由はいくつか考えられる。
最大の理由は、ネットに代表される情報技術の進歩を、新しい産業技術革命と捉え、経済発展を強力に促進する新しいエンジンにしたい、との国家戦略があるためだ。今日の中国のハイテク躍進はネット環境が整備されたことと密接な関係がある。ネット利用速度を4Gの5倍以上速める5Gの設置済み基地局数は400万を超え、全世界の8割を占めている。
確かにネットの発達は政権にとって都合の悪い情報の流入、政府批判言論の拡散といったリスクがある。ただ、その代価を払っても、ネットを通じて全世界の科学技術、経済情報を瞬時にキャッチし、経済発展の力強い追い風になるというメリットがはるかに大きいとの損得勘定もある。
意外にも、ネットメディアは「ガス抜き」の役割を果たしてくれる。西側社会では抗議デモや新聞投書、選挙の投票などで民意を示すが、中国ではそれができない。21世紀に入っての一時期、都市住民や、労働者、農民による抗議デモが多発した。しかしネット社会の発達につれて、当局はネットでの不満の発声を完全に抑えられない以上、ある程度容認してガス抜きにする方針に切り替えたようだ。
2010年以降、中央政府から各地方当局まで、相次いで「網弁」(ネット対策室)が設置された。その対策に相当の人的、技術的資源が動員され、「不都合」なものがよく削除される。他方、そこに表れる民衆の集中した意見や不満も「網情」(ネット世論)として随時に党と政府の責任者に報告され、対策を取る依拠にしている。例えば、22年末、「ゼロコロナ」政策への不満がネットで爆発し(一部の人は街頭に出て「白紙」抗議運動に参加)、そのネット世論の津波が首脳部に報告され、急な解禁という180度の政策大転換につながった。今の中国では少人数の政府批判者(弁護士、活動家など)は拘束されるが、ネット社会で反発・批判の大波が現れると、当局は抑え込むのが不可能と分かっているので、ほとんどの場合、迅速な政策修正に着手すると言われる。
このような「世論」の現れ方は日本と正反対だ。24年末、言論NPOなどが発布した最新の「日中共同世論調査」報告書の中に、「ネット世論は民意を反映しているか」という項目があり、「適切に」もしくは「ある程度」反映しているとの回答者は日本では合わせて2割しかいないのに対し、中国では8割に上っている。
背景と社会事情の相違はあるが、中国人の8割以上がネットメディアを主要な「世論」と見ている現実を踏まえて、対中認識の基本から考え直す必要があるのではないか。
日本の世論調査で国民の9割前後、中国にいいイメージを持っていないとの回答だ。自分の学生に対してアンケートを取っても、監視カメラ、大気汚染、人権抑圧、そしてまもなくバブル崩壊との答えが多い。これらの見方に導く情報源はほとんど日本のテレビや新聞であり、実際に中国に行って現場を見た人が少なく、中国「世論」の主陣地がネットメディアに移ったことを知る人はなおさら少ないだろう。
中国のネットメディアに問題も多く存在する。昨年9月、深?で日本人学校に通う子供とその中国人母親に対する殺傷事件の発生後、イギリスFT紙では、①中国のネットメディアは「国内政治」「暴力」「ポルノ」に対する規制が厳しい割には、諸外国との関係の内容の規制は相対的に緩い、②かつての戦争の影響などで日本嫌いの一部の人間の反日書き込みがネット社会で強い影響力を持つ、③ネットの「流量」(アクセス数)稼ぎという商業主義が極端な言論を助長、といった特徴が指摘された。
中国の「国情」を有する社会で発達したネットメディアは問題を抱えながらも、試行錯誤して、真実そして法治、民主を追求しており、この大勢は変わらない。日本もこのような中国の変化を理解し、より客観的な中国認識を形成するとともに、中国のネットメディアを積極的に活用し、ありのままの日本がもっと理解されるようにも努力しなければならない。

《り そうてつ》
専門は東アジアの近代史・メディア史。中国生まれ。北京中央民族大学卒業後、新聞記者を経て1987年に来日。上智大学大学院にて新聞学博士(Ph.D.)取得。98年より現職。同年、日本国籍取得。
2025年8月18日号 週刊「世界と日本」第2299号 より
日本は李政権の本質を見極めよ
協力か対立かの岐路に立つ日韓関係
龍谷大学 教授
李 相哲氏
韓国では刑事被告人の李在明(イ・ジェミョン)氏が大統領に、大統領だった尹錫悦(ユン・ソンニョル)氏は拘束された状態で裁判を受ける身となった。激変の韓国はどこへ向かうのか。日韓関係はどうなるのか。
怪物独裁政権の誕生
韓国の立法府は「ともに民主党」(以下「民主党」)を中心とする左派勢力が議席の多数を占めていることについては、周知の通りだ。
国会では、大統領に就任した李氏が、それまで受けていた裁判を受けなくても良いという趣旨の刑事訴訟法改定案を、大法院(最高裁判所)が有罪趣旨で判断を下した「公職選挙法」違反について大統領退任後も罪に問われない「公職選挙法改定案」を、李氏の12の容疑を捜査してきた「検察庁廃止法」などを議決する構えだ。つまり、いまの韓国の国会は完全に李氏の私的機関に変質したと言っても過言ではない。
司法部門はどうだろう。国会で審議中の「李在明免罪法」を含め、李氏がやろうとしている政策について法解釈をし、正当性を与えることのできる法務部法制処長、大統領府の民情秘書室(司法部門を指揮、統括し、政府の高位職の人事を検証する)首席秘書官などに刑事被告人李在明の弁護士をあて、憲法裁判所には民主党寄りの裁判官で固めた。
原則なき「実用外交」は通用しない
このように三権すべてを一手に握った李氏は、対外政策をどうするつもりか。李氏の「実用外交」は善意の解釈をすれば国益のためなら、どんな国とでも仲良くするというものだ。常識的な姿勢と言って良かろう。
しかし、見落としてはならないのは、李外交は軸足をどこに置いているかだ。トランプ2期政権は日本や韓国など自由陣営の同盟国が自由や民主主義の価値を犠牲にして中国やロシアと経済関係を維持、または強化することは許さないつもりだ。言い換えれば、中国と米国との間で旗印を明確にすることが求められている。中国やロシア、北朝鮮といったレッドチームか、アメリカや日本欧米中心の自由陣営かを選び、その枠組みのなかでの外交を求められているのではないか。アメリカと同盟関係にあり、アメリカの核の傘の保護をうける韓国や日本が、経済利益を優先して「実用外交」を展開するのは難しい。
韓国の左派政権はこれまで、そのような枠組みから離脱し、「国益」や「民族」優先の対外政策を推し進めてきた前歴がある。李政権がこれからどのような姿勢で対米、対日関係を構築しようとするのかについては、以下3点に注目すれば分かるのではないか。
まず、北朝鮮問題をどうしようとしているのか。韓国政府がどのような性向をもつ政権かは、北朝鮮問題にどう対処しているかをみれば良くわかる。金正日(キム・ジョンイル)政権に各種名目で30億ドル以上の経済支援をおこない政権基盤を強化することに手を貸した。金大中(キム・デジュン)政権はもとよりその後に誕生した左派政権は「南北対話一つだけ成功させれば、他はメチャグチャになっても構わない」(2002年5月28日、廬武鉉(ノ・ムヒョン)という姿勢で北朝鮮を支援し、擁護した。文在寅(ムン・ジェイン)にいたっては、5年間の任期中に、金正恩(キム・ジョンウン)に奉仕し、金正恩の機嫌取りに終始し、金正恩弁護の外交に終始したため、「金正恩の首席スポークスマン」(米ブルムバーグ通信)と言われるほど、北朝鮮に夢中だった政権だ。
北朝鮮に前のめりの李政権
李氏もその点では過去の左派政権と脈絡は同じくしているのではないか。大統領就任後真っ先に行政命令として出したのが、南北軍事境界線沿いで韓国軍が行っていた対北朝鮮拡声器放送の中断だ。拡声器放送は北朝鮮が政権の命運と関係あるとしてありとあらゆる手段を使って妨害し、韓国に中断を迫ったものだが、李政権はその要求にまず答えたことになる。
そして、「太陽政策」の立案に関わり、所謂、北朝鮮の立場で物事を考えるべきという「内在的接近法」を唱えてきた学者を国家情報院院長にすえ、廬武鉉時代に南北問題を統括する立場にいた人間を統一部長官に抜擢した。つまり、李政権も過去の3つの民主党政権と同じく、北朝鮮に前のめりしているのが分かる。
つぎに、日米韓協力への態度だ。李氏はこれまで日米韓協力関係には否定的な立場をとった。「韓国の安保は韓米協力で充分だ。なんで日本を引きずり込むのか」、「日米韓が合同軍事訓練をすれば、日本の自衛隊を軍隊として認めることでもあり、そうなれば、自衛隊の軍靴が朝鮮半島を踏みにじる日がくるだろう」と、自著やインタビューで語っていた。かつて、文在寅政権は外相を中国に送り「日米韓協力関係を軍事同盟にしない」と約束したことがある。それは、北朝鮮に忖度していたからだ。今のところ李氏が日米韓関係をどうするつもりかははっきり見せていないが、文在寅時代がそうだったように、対米対日より北朝鮮優先の姿勢はすでに明確に表われている。
3番目に、李氏の「歴史認識」を見極める必要がある。大統領になった後、李氏は「(日韓は)まるで家の前の庭を一緒に使う隣人のように、切っても切れない関係」(25年6月18日)と発言したが、本当にこれまでの日本認識を改めたかは不明だ。李氏はかつて「日本は敵性国家」、「駐韓米軍は占領軍」と発言したことがある。李氏の過去を振り返り、彼の政治家としての足跡をたどっていくと、その場しのぎの嘘をついてしまい2度も裁判(選挙期間中に嘘を流布)にかけられた過去がある。そして、必要ならば態度を豹変、平気で前言を撤回することでも有名だ。
日韓の間に横たわる元徴用工問題、慰安婦問題、佐渡金山問題などは今のところ封印しているが、一つはっきり言えることは、実用外交を標榜する李政権は、状況次第では「三権分立」(裁判所が日本企業に支払い命令が出た場合など)、「国民の議論」が必要だとして蒸し返すことは充分考えられる。
尹政権が「中国やロシア、北朝鮮を敵視し、日本寄りの奇怪な外交をしたとして」糾弾している李政権が、対日外交だけは尹政権の路線を踏襲することはないのではないか。状況次第では、尹氏の対日外交、約束を全面的に見直す可能性もある。
日本は、慎重に李政権の出方を見極めながら対立を恐れず協力も視野におきながら慎重に付き合って行く必要があるだろう。

《まえしま かずひろ》
1965年静岡県生まれ。アメリカ学会前会長。グローバルガバナンス学会副会長。専門は現代アメリカ政治外交。上智大学外国語学部英語学科卒、ジョージタウン大学大学院政治学部修士課程修了(MA)、メリーランド大学大学院政治学部博士課程修了(Ph.D.)。近著に『混迷のアメリカを読みとく10の論点』(共著、慶応義塾大学出版会、2024)など。
2025年8月4日号 週刊「世界と日本」第2298号 より
トランプ政権と大学
なぜ「国力の源泉」をいじめるのか
上智大学 総合グローバル学部
総合グローバル学科教授
前嶋 和弘氏
トランプ政権は5月末、アメリカに留学を希望する人たちのビザ取得に必要な面接の新規受け付けを一時停止した。6月半ばに、面接は再開されたが、その際の条件として応募者に対して、SNSの公開と書き込んだ内容の精査が義務付けられている。
「反米的」と考えらえる留学希望者を洗い出すための措置である。「反米的」の定義はあいまいで、多様性の重視や気候変動対策など長年続いたアメリカの政策を取りやめていくトランプ政権への批判も含まれているとみられている。ガザへの激しい攻撃を続けるイスラエルに対する批判的な考え方をする希望者も洗い出そうという狙いもある。
「表現の自由」や人権を極めて重視してきたはずのアメリカがまるで、独裁国家のように変貌している。大学や大学院への入学者だけではなく、日本の大学に在籍しながら、1年間だけ短期交換留学を希望する学生も対象となるため、影響は甚大だ。
アメリカの大学教育は世界にとって羨望の的だった。第二次大戦後のアメリカの科学技術の飛躍的発展は連邦機関からの莫大な助成金が起爆剤となった。その中で生まれた科学技術の開発と発展には、インターネット、AIなど枚挙にいとまない。軍事技術も含まれる。世界に冠たるアメリカの科学技術を支えたのは、大学だった。
自然科学だけでなく、アメリカの場合には、社会科学、人文学の研究も世界を主導してきた。
大学の締め付けは、これまでアメリカが世界に誇ってきた「大学教育というソフトパワー(アメリカという国家への魅力)」だけなく、「ハードパワー(経済力、軍事力)」を源泉でもあった大学をいじめ、潰してしまう行為だ。
なぜ、トランプ政権は前代未聞の「大学潰し」を急ぐのか。それに分かりやすい理由がある、トランプ政権を支持する人々にとっては「大学は敵」(バンス副大統領)だからだ。
トランプ政権の支持層の中で、最も数が多いのはキリスト教の福音派だ。福音派とは聖書(旧約聖書、新約聖書)を一字一句信じる人々であり、アメリカの国民のなんと20%から25%もおり、トランプが昨年の選挙で勝ち抜いた南部や中西部を中心に偏在している。昨年の選挙の投票率は6割程度であると推定されるが、出口調査からは8割以上の人々がトランプに票を投じていることが分かっている。
福音派にとっては、聖書には「男」「女」という性別しかない。同性婚やLGBTなどの性的少数派への多様性配慮は許しがたい神への冒涜である。命は神が授けるものであるため、女性の権利としての中絶は禁忌だ。さらに、気候は神がつかさどるので、気候変動政策そのものも不遜なものとなる。
さらに、「神はエルサレムの地をユダヤ人に与えた」と旧約聖書にあるため、熱狂的なイスラエル支持だ。アメリカの中のユダヤ系は人口の2%程度であり、日本の中で誤解があるが、パレスチナ問題ではむしろ2国家共存を志向し、昨年の選挙では圧倒的に民主党のハリスに投票している。ユダヤ系の親イスラエルのロビー団体はあるが、福音派の親イスラエル団体の参加者の数の方が圧倒的に大きい。イスラエルの過度な攻撃を非難し集会に参加する大学生は「反ユダヤ主義(Antisemitism)」者となる。その中に、ユダヤ人学生も少なからずいるのは、皮肉なのか滑稽なのか、何とも形容しにくい。
とくに一部の名門研究大学がトランプ政権の大学潰しのやり玉となっている。名門大学は目立つために格好の見せしめであるほか、そもそも科学技術研究で進んでいるため、連邦政府からの助成が大きく、叩きやすい。アメリカ全体では大学の収入の中での連邦政府からの助成は10%から13%程度といわれているが、名門大学の場合、優秀で助成金を勝ち取れるため、資金が収入の半分を占めていることも珍しくない。
例えば、免疫学や移植、老化、神経科学、精神衛生といった医学で有名なジョンズ・ホプキンス大学は、年間40億ドルの連邦政府資金を受け取っており、大学の収入の40%近くを占めていた。しかし、同大学は4月初めには、2200人の一時解雇を発表しており、いまも再雇用のめどが立っていない。
各大学にとって留学生の場合、各大学の多様性を高める効果があるのはいうまでもないが、留学生は入学後、正規の学費を払うケースが多い。それを原資に、各大学はアメリカ国内の優秀な学生に対して奨学金として学費を無料にしたり、一部生活費も提供することも一般的だ。浮いた資金で優秀なアメリカの学生を獲得し、大学のレベルを上げ、さらに優秀で正規の学費を払う留学生も増えるという好循環を生んできた。優秀な大学ほど、留学生が多く、ハーバード大学の場合、全体の3割が留学生である。
トランプ政権は留学生の数を抑えさせ、この好循環にメスを入れようとしている。ビザを出す出さないはトランプ政権が決めることができる。特に中国からの留学生の場合には、「共産党との関係」といって断ることができる。もちろん、スパイ的な人物の入国は制限すべきだが、「安全保障の理由」はいかようにも理由をつけることができる。
補助金などの打ち切りをトランプ政権に宣言されている大学の一部は政権側にすり寄るための方策に走り出している。イスラエルのガザ攻撃に反対するデモの拠点になっていたとして およそ4億ドルの助成金が取り消されたコロンビア大学は生き残りのために、学生の監視などを徹底する案を表明している。
いずれにしろ、これでアメリカに集まっていた優秀な人材が世界に流出することは必至だ。科学研究誌『ネイチャー』によると、アメリカ国内にいる研究者の7割以上が「アメリカを離れることを検討している」という衝撃の記事を掲載している。トランプ政権の大学たたきで、アメリカの研究開発力が落ち、経済的な損失となるはずだ。一方で、トランプ政権は支持層を守るために、「それもやむなし」とみているはずだ。福音派が作った大学などへの助成は明らかに増えている。
トランプ政権の大学潰しは、反知性主義に他ならない。第二次大戦後のアメリカの発展を生んだ教育を捨てるような政策はあまりにも愚かだ。

《みのはら としひろ》
1971年生まれ。神戸大学大学院法学研究科教授、インド太平洋問題研究所(RIIPA)理事長。専門は、日米関係・国際政治・安全保障。カリフォルニア大学デイヴィス校を卒業後、1998年に神戸大学大学院法学研究科修了、博士号(政治学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、神戸大学法学部助教授を経て、2007年より現職。著作としては、『大統領から読むアメリカ史』(第三文明社、2023年)など。清水博賞、日本研究奨励賞を受賞。
2025年7月21日号 週刊「世界と日本」第2297号 より
トランプ2.0政権内の対立構造と今後の展望
神戸大学大学院 法学研究科教授
インド太平洋問題研究所 理事長
簑原 俊洋氏
2期目のトランプ政権が、8年前の1期?のトランプ政権とは様相が全く異なることは論を俟たない。就任から今日までの現政権の行動力はまるで別次元であり、このように短期間で米国を変容させたのは―その功罪はともかく―大恐慌真っ只中に就任したフランクリン・D・ルーズヴェルト大統領以来、実に92年振りである。就任から僅か100日間で国家非常事態法を8回も発令した大統領は、アメリカ史においてトランプ氏一人だ。この背景には、今では政治的エスタブリッシュメントとしての存在を完全に確立したトランプ大統領が、下野していた時代を含む過去8年間に多くを学習したことなど、様々な理由がある。これを踏まえ、本稿では、大統領の周囲を固める政策集団の陣容について検証する。なぜなら、トランプ大統領を動かし、政策形成に大きく関与しているのが、これら集団の存在であるからだ。加えて、この政策集団同士の影響力の強弱によってトランプ政権の政策は揺らぎ、一貫性を欠く要因にもなっている。
1期目の政権では、大統領を献身的に支える集団は存在せず、各々の側近がイシューごとに離散集合を繰り返して政策に関与していた。当然、大統領への影響力をめぐって頻繁に対立を繰り返し、足の引っ張り合いが日常茶飯事であった。そのため、機微な情報のリークが頻繁に生じ、結果的にトランプ大統領が公約として掲げた政策の多くは日の目を見なかった。さらに、当時は、トランプ氏の周辺には米国の将来を憂い、かつ大統領ではなく合衆国憲法への忠誠を重んじた多くの有能な側近がいた。彼らがブレーキ役を務めて巧みに大統領の衝動的な行動を牽制したことで、トランプ氏が目指した政策の多くはついに実現に至らなかったのである。
しかし、2期目のトランプ大統領の状況は全く異なる。彼の周辺には、大別すると利益が対立しあう三つの集団が存在する。一つ目のグループは、トランプ氏のイデオロギーを熱狂的に支持し、大統領に対する忠誠心を前面に打ち出すMAGA派だ。この中にはトランプ氏の尽力によって当選した連邦議員や福音派の宗教指導者、そして現政権では閣僚入りしていないスティーブン・バノン元首席戦略官のような人物も含まれる。また、忠誠派には、1期目からトランプ氏を支えた人もいれば、J・D・バンス副大統領やマルコ・ルビオ国務長官のように、1期目では激しく対立したものの、トランプ氏に勝てないと悟って後から転向して忠誠派に加わった者もいる。
次いで、二つ目のグループは、同盟国である日本とも太いパイプで繋がっている反中タカ派である。この集団の中心には、マイク・ウォルツ前国家安全保障担当大統領補佐官やエルブリッジ・コルビー国防次官などがいる。彼らは対中強硬派として知られており、米中関係を、「管理」するものではなく、戦争と見なして「勝利」する必要があると捉える。それゆえ、反中タカ派には知日派が多く存在し、同盟国としての日本の地政学的重要性を十分に認識している。また、心底からMAGAの思想に傾倒していないのもこのグループの特徴であり、伝統的共和党やかつてのネオコンの残りも参画している。
そして、三つ目のグループは、大富豪からなる機会便乗的なオリガルヒ派である。彼らの多くはトランプ氏のイデオロギーに共鳴しておらず―従って忠誠派の点では偽善者と罵られている―むしろ持ち前の財力を駆使してトランプ氏を支えることで政権中枢に食い込み、?らにとって有利な政策を導き出すことを目指している。このように機会便乗的に行動するオリガルヒ派の紛れもないリーダーは、テスラ社のイーロン・マスク最高経営責任者である。
これら三グループは基本的に対立関係にあり、例えばMAGA派とオリガルヒ派は相互に非難合戦を派手に繰り広げている。特に、関税政策とトランプの「大きくて美しい法案」を巡って確執は一気に拡大した。同時にMAGA派は好戦的なタカ派を危険視しており、かつオリガルヒ派も米中関係の安定こそが利益に直結すると考えているため、タカ派を警戒している。他方、タカ派は米国の同盟関係を軽視するMAGA派の姿勢が国益を毀損させることを憂慮する上に、オリガルヒ派が是とする中国の経済的な絆の強化を愚行と見なす。つまり、これはまさしく大統領への影響力をめぐる三つ巴の戦いであり、三陣営は激しく鎬を削りあっている。
しかし、6月になってこの争いについに決着が着いた。オリガルヒ派は、マスク氏と大統領の確執が一気に表に噴出し、最終的にマスク氏が政権中枢を去ることになった。一方の反中タカ派は、機密情報のリーク事件などがあってワルツ氏が更迭された結果、大統領に対する影響力は一気に萎んだ。なお、政権内に残っているコルビー氏は、「台湾防衛は必ずしも米国の死活事項ではない」と語るなど、政権に踏み止まるために従来の主張を大きく後退させている。すなわち、政策集団で唯一勝ち残ったのがMAGA派となったことにより、今後の米国は同盟国との関係を軽んじつつ、不法移民に対する取り締まりや反DEI政策といった自国を作り直すことを目的とした国内政策の追求に邁進しよう。
しかし、この矢先にイスラエルによるイランの攻撃があり、また米国がこの戦争に直接的に介入したことで目下MAGA派には深刻な亀裂が走っている。同派閥における親イスラエル派(対イラン攻撃容認派)と非介入派(イラン攻撃反対派)の争いはまだ序盤段階にあり、今後の展開次第で最終的な勝者は決する。つまり、対イラン戦争が泥沼化すれば非介入派の勢いは増し、他方、戦争が一気に片付いてイランの体制変革が円滑に進めば新イスラエル派が優勢になる。いずれにせよ、今の米国は日本が従来頼ってきた米国とは本質的に異なることを理解することが肝要であり、もはや変数となってしまった唯一の同盟国である米国と今後いかに上手に付き合っていくのかが日本にとって最大の外交課題及び試練であるのはいうまでもない。

《きむら まさと》
1961年生まれ。元産経新聞ロンドン支局長。国際政治、安全保障、欧州問題に詳しい。元米コロンビア大学東アジア研究所客員研究員。元慶応大学法科大学院非常勤講師(憲法)。著書に『欧州 絶望の現場を歩く―広がるBrexitの衝撃』『EU崩壊』『見えない世界戦争「サイバー戦」最新報告』
2025年7月21日号 週刊「世界と日本」第2297号 より
海外メディアは
今の日本をどう見ているか
在英国際ジャーナリスト
木村 正人氏
世界がいま日本をどう見ているのか。日本製鉄のUSスチール買収や令和のコメ騒動も筆者には「今さら鉄やコメを論じてどうなるのか」という気がしてならない。
英紙フィナンシャル・タイムズのレオ・ルイス東京支局長は「日本の指導者はコメへの執着を捨てるべきだ」(5月22日付)と題して「この国では農業よりも自動車産業に生計を頼っている人の方が多い。コメは必要であれば犠牲にしても構わない」と断じている。
血縁、地縁の世襲政治に囚われてきた日本は取捨選択を誤ってきた。中でも、日本の輸出競争力を削いだ1986年の日米半導体協定が電子立国・日本の大きな転機になった。
岸田文雄首相(当時)が2022年に「半導体は国の重要な戦略物資」と旗を振るまで実に36年を要している。
集積回路の部品数が2年ごとに2倍になるというムーアの法則に基づけば実に26万倍以上の歳月である。政府の無策は日本経済の未来に致命的な打撃を与えた。
02~03年、米ニューヨークのコロンビア大学に社費留学した時、日本では世界初の携帯電話IP接続サービス「iモード」が普及していたにもかかわらず、現地ではまだ「ページャ」と呼ばれるポケットベルのメッセージ機能が使われていた。
07年にロンドンで暮らし始めた当時、携帯電話はフィンランドのノキア製。米アップルの製品で身近にあったのは携帯型デジタル音楽プレイヤーの「iPod」のみだった。
それからタッチパネルで携帯電話、デジタルカメラ、テレビ、オーディオプレーヤー、ゲーム機、カーナビを操作できる万能端末の「iPhone」、SNSのフェイスブックやツイッター(現X)、OpenAIの生成AI(人工知能)「ChatGPT」が次々と市場を席巻し、世界は激変した。
いつしか駐英日本大使が「日本の主要輸出品はスシになった」という自虐ネタを披露しているという本当かウソか分からないウワサ話を耳にするようになった。ロンドンで日本の電気製品を見かけることは少なくなった。
スシよりロンドンでブームになったのは博多(豚骨)ラーメンだ。コラーゲンたっぷりの濃厚なスープがなぜかロンドンっ子には受ける。
日本研究で知られる英ケンブリッジ大学のバラク・クシュナー教授が12年に大和日英基金のイベントで著作『ラーメンの歴史学―ホットな国民食からクールな世界食へ』の出版に合わせて講演し、豚骨ラーメン店「Tonkotsu」の試食が行われた。
それからアッという間にラーメン・ブームに火がつき、日本の一風堂、金田家も上陸してきた。
コロナ危機に端を発するインフレと日・米英間の金利差で「円弱」となり、昨年5月には円の国際的な価値を示す「実質実効為替レート」は過去最低を更新した。
1ドル=360円の固定相場制の時代よりも「円の購買力が低い」という衝撃的な水準だった。
友人の英国人カップルが「日本にホリデーに行ってきた。激安だった」と嬉々として話す様子を見ると複雑な気持ちになる。
英誌エコノミストのビックマック指数によると、日本では480円で買えるマクドナルドのビックマックが英国では884円もする。
英国の大学に留学すると学費と生活費を合わせて1年で1000万円もする時代になった。ユニバーシティー・カレッジ・ロンドンに留学した長州五傑一人当たりの渡航費、学費、生活費が千両だったことを思い出した。
ロンドンから地方の有力紙の支局が撤退し、全国紙の人員も大幅に縮小された。欧州連合(EU)離脱で英国のニュース価値が下がったという事情はあるにせよ、長州五傑や薩摩藩遣英使節団が明治という新時代を切り開いた歴史を考えると寂しい限りだ。
その背後にあるのは日本の政府債務だ。
米紙ニューヨーク・タイムズ(5月28日付)は「日本の政府債務は今や経済規模の2倍を上回り、難しい選択を迫られている。日本政府は借金依存の財政支出を削減するよう圧力を受けている」と報じている。
人口減・高齢化・低成長に加え、物価上昇と金利上昇の中で財政規律への圧力が強まるが、財務省に不当な国民の怒りが向けられる。
日銀の異次元緩和に依存したアベノミクスの副作用が制御不能になりつつあると言う他ない。
「負の遺産」ばかりに注目していても仕方がない。スシ、ラーメンとくれば次はマンガである。
フィナンシャル・タイムズ紙(5月8日付)は「日本アニメは次の世界的な知的財産の金脈になるのか」と題した特集記事で「個性豊かなアニメは世界中の視聴者、ハリウッドスタジオ、プライベートエクイティ企業を魅了している」と報告している。
日本アニメのファンはスポーツ選手、ミュージシャン、政治家を含め推定8億人とされる。すごいソフトパワーだ。
米投資銀行ジェフリーズは24年版レポートで世界のアニメ市場は23年の312億ドル(4兆5000億円)から30年には601億ドル(8兆7000億円)にほぼ倍増すると予測している。
経済産業省のまとめによると、映像・アニメ・ゲーム・出版・音楽のコンテンツ産業の海外売上は半導体産業の5・5兆円を抜いて5・8兆円に達している。
「日本製鉄のUSスチール買収」の黄金株導入が米国への投資のあり方を変えたとしても、日本の鉄鋼産業の輸出額は4・8兆円に過ぎない。
政治家も新聞・テレビのレガシーメディアもナショナリズムを掻き立てる鉄やコメが大好物なのだ。
ビッグデータ分析のパランティア・テクノロジーズ防衛部門責任者マイク・ギャラガー氏は米紙ウォールストリート・ジャーナルへの寄稿(6月11日付)で「ドナルド・トランプ米大統領にとって日本は大きなチャンス」と指摘している。
「貿易とテクノロジー分野での同盟強化は米国にとって利益となると同時に中国への抑止力にもなる。いまトランプ大統領は日本を相手に、さらに大きな一歩を踏み出す機会を得ている」と論じている。
トランプ氏のカモになるわけにはいかない。
ロボット工学から材料科学、半導体装置に至るまで世界をリードする日本企業がビジネスチャンスをものにできるかどうか石破茂首相と赤沢亮正経済再生担当相の交渉力が問われている。
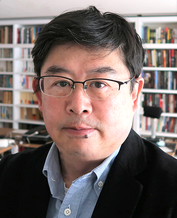
《ほさか しゅうじ》
日本エネルギー経済研究所理事・中東研究センター研究顧問。慶應義塾大学大学院修士課程修了、在クウェート日本大使館、在サウジアラビア日本大使館、中東調査会研究員、日本学術振興会カイロ研究連絡センター長、近畿大学教授等を経て、現職。日本中東学会会長を兼任。おもな著書に『ジハード主義』(岩波書店)など。
2025年7月7日号 週刊「世界と日本」第2296号 より
イスラエル・ガザ紛争
日本はどのように取り組んでいくのか
日本エネルギー経済研究所
理事・中東研究センター研究顧問
保坂 修司氏
2023年10月7日以降のガザにおけるイスラエルとパレスチナのイスラーム主義組織ハマース等との衝突は、発生以来1年半を経過したが、解決の目途すら立っていない。犠牲者数はガザだけで5万人を超え、その大半が女性や子どもを含む民間人であった。勝敗はすでに決しているにもかかわらず、イスラエルは攻撃の手を緩めていない。ガザは瓦礫の山と化したうえに、食料や医薬品など援助物資も届かず、住民は飢餓や病気に苦しめられている。
紛争勃発直後、日本を含むG7メンバー国は、ハマースの攻撃をイスラエルへのテロだと糾弾、イスラエルにはハマースへの反撃の権利があると主張した。米国は、バイデン政権時代こそ、イスラエルの過剰な反撃に不快感を示すことがあったが、トランプ政権になってからは、そうした批判も聞こえなくなり、事実上、イスラエルにフリーハンドを与えてしまっている。
他方、中東のなかでも、ハマースを支援していたイランやレバノンのシーア派武装組織ヒズバッラー、イエメン北部を占拠するフーシー派等いわゆる「抵抗の枢軸」はハマースの攻撃を容認したうえで、イスラエルの対ガザ政策にこそ原因があるとして、イスラエルを非難、実際にイスラエルと軍事衝突を繰り返した。しかし、イスラエルの攻撃を食いとめられていない。
それ以外の国のガザに関わる立ち位置は基本的にこの両極のあいだに入る。たとえば、パレスチナの大義を支持するアラブ諸国の多くは、イスラエルとの直接衝突を避けながら、イスラエルのガザでの軍事作戦を断罪、パレスチナ問題の抜本的な解決の必要性を強調した。ロシアや中国もこの立場に近い。また、ガザの人道状況悪化につれ、EUやNATO加盟国のなかからも、イスラエル非難の声が高まっている。
国際社会の大半は、イスラエルとパレスチナの2つの国が共存する、いわゆる「二国家解決」を支持しているが、当事者たるイスラエルのネタニヤフ政権、それを支援する米トランプ政権、さらにハマースとそれを支援する抵抗の枢軸は二国家解決には、いろいろ条件をつけたり、否定的だったりする。
しかし、ガザ紛争の泥沼化で西側諸国のなかからも二国家解決の前提ともなるパレスチナ国家承認の動きが出てきたのは皮肉であろう。すでに国連加盟国の過半数を超える約150カ国がパレスチナ国家を承認しているが、西側諸国を中心に約50カ国は未承認である。そのなかでスペイン、アイルランド、ノルウェーが2024年5月にパレスチナを国家承認した。また、フランスは、中東諸国がイスラエルを承認する代わりに、いまだパレスチナ国家承認に向けた議論を行う会議をサウジアラビアと共同で開催すると発表した。
こうした状況のなかで日本はどうしてきたか。日本は、上述のとおり、事件勃発以来、米国などG7と歩調を合わせてきた。2023年には日本はG7の議長国であったため、G7の意見をまとめる必要があったことも影響しているだろう。直近でいえば、なるべくトランプ政権を刺激したくないという思惑も透けてみえる。
日本の外交は米国追従との批判を受けることが多いが、こと対中東政策にかぎっては、かならずしも米国と同調してきたわけではない。ガザ戦争の、ちょうど50年前、1973年10月6日、第4次中東戦争が勃発した。このとき起きた、いわゆる「石油ショック」で日本はパニックに陥った。そのため日本は、米国からの同調圧力をはねのけ、対イスラエル外交を抜本的に見直すとの声明を出すとともに、アラブ諸国に対する大規模な経済支援を約束、アラブ諸国に石油禁輸措置を解除させることに成功した。以後、日本は、こと中東外交に関してはエネルギー安全保障を踏まえた独自外交を展開することが珍しくなくなったのである。
しかし、近年、地球温暖化等を含め、石油の重要度が低下し、中東で事件が起きても、石油ショックのような事態になりづらくなると、日本の中東外交は米国寄りにシフトしていった。今回のガザ戦争では、日本は早い段階からハマースの攻撃をテロだと厳しく非難する一方、イスラエルの反撃に関しては「深刻に憂慮」といった程度の言及にとどまっていた。また、日本は、ガザへの緊急人道援助を約束していたが、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)職員がハマースのイスラエル攻撃に関与していたとして米国がUNRWAへの資金供与を停止すると、日本もそれに同調することになった(のち解除)。
しかし、ただでさえ、中国の経済的・政治的なプレゼンスが中東で増大し、逆に日本の地盤沈下が顕著になるなか、このまま中東の問題で手をこまねいていれば、日本の埋没はますます加速するだろう。個人的には中東地域は日本のエネルギー安全保障や経済の浮揚で今後も重要な役割を果たすと考えている。中東との関係が大事であるなら、G7ではじめてパレスチナを国家承認するといった大胆な政策を打ち出してもいいはずだ。
ガザ戦争勃発後、日本政府はパレスチナの国連正式加盟に関する国連安保理決議案に賛成した(決議は米国の拒否権で否決)が、日本政府は、パレスチナの国連加盟と日本政府のパレスチナ国家承認は別問題だとし、国家承認には及び腰である。しかし、ガザ情勢のさらなる悪化で国内からもパレスチナ国家を承認すべきとの声が高まっている。
本稿執筆中の6月13日、イスラエルがイランの軍事施設等を攻撃、イスラーム革命防衛隊司令官や原子核物理学者らを殺害した。イランもまたイスラエルに対し報復攻撃を実施、そのため、フランスとサウジアラビアが共同主催する予定の二国家解決に向けた国際会議も延期され、中東における全面的軍事衝突の恐れが現実味を帯びてきた。日本は、イスラエルとイランの軍事的応酬に懸念を表明、両国に自制を求める外相談話を発表したが、これでは言わないよりはマシという程度にすぎない。カナダでのG7サミットでも、イスラエルの自衛権を支持し、イランを非難する声明が出された。日本は、パレスチナ問題解決にあたって、G7の結束ではなく、G7とそれ以外の国や地域との調整役を果たすことでこそ、外交力を発揮できるのではないだろうか。

《いとう とおる》
1969年広島県生まれ。中央大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程後期単位取得退学、博士。在インド日本国大使館専門調査員、島根大学法文学部准教授等を経て2009年より防衛大学校。2021年4月より現職。『新興大国インドの行動原理―独自リアリズム外交のゆくえ』、『インドの正体―「未来の大国」の虚と実』など著作多数。
2025年6月2・16日号 週刊「世界と日本」第2294・2295号 より
トランプ関税に備える
インド・モディ政権の期待と懸念
防衛大学校 教授
伊藤 融氏
世界が戦々恐々とするなか、インドはトランプ2.0の発足に冷静だった。いや、モディ政権に関して言えば、むしろ心から歓迎したというのが本音だろう。
というのも、バイデン民主党政権との間では、半導体や戦闘機エンジンなど機微な分野も含めた協力関係が進んだのは確かだが、ロシア非難や制裁に同調せず、ロシア産の原油や肥料を買い増しするインドの姿勢や、インド国内で進む民主主義や人権、宗教の自由の後退、さらにはカナダや米国でのインド諜報機関による標的殺害計画疑惑などを巡って溝も広がっていたからである。その点、トランプ氏は第一期政権期にモディ首相と極めて相性が良かっただけでなく、こうした価値観を巡る問題に頓着しないとみなされていた。また、ウクライナ支援に消極的で戦争終結を求めるトランプ氏の立場は、ロシアとの戦略的関係を維持したいインドの方針と合致するはずだと考えられた。
もちろん、「アメリカ・ファースト」、「アメリカを再び偉大に(MAGA)」を掲げるトランプ氏に何の懸念も抱かなかったというわけではない。トランプ氏は選挙戦中から、「関税王」とか「関税乱用国」などと、インドへの名指し非難を繰り返し、貿易を巡ってインドに注文を突き付けてくることは予想されていた。そもそもトランプ1.0の2019年、米国は一般特恵関税制度(GSP)の対象からインドを除外して途上国としての優遇措置を剥奪し、反発するインド側は米国からの輸入品の関税引き上げで報復したという経緯がある。その意味では、「貿易戦争」を仕掛けてくることは織り込み済みだった。
モディ首相は今年2月、石破茂首相らに続き、いち早くホワイトハウスに招かれた。それはトランプ2.0がインドを重視していることの証左であった。貿易問題が議題に上ることを念頭に、モディ訪米前にインドはハーレーダビッドソンや自動車、スマートフォン部品の関税引き下げを発表して先手を打った。それでも、トランプ大統領はモディ首相の面前で、インドの高関税を「大きな問題だ」と露骨に不満を示した。これに対し、インド側は今秋までに懸念事項に対処する二国間貿易協定をまとめることに合意した。
この首脳合意に基づき、二国間交渉が進むなか、4月2日にトランプ大統領は世界各国への「相互関税」リストを発表した。インドへの関税は日本を上回る26%とされたが、日本や欧州で驚愕の声が上がったのとは対照的に、インドはここでも泰然自若としていた。
インドの落ち着きぶりにはいくつかの要因がある。まずインド経済はそもそも内需依存型で、関税引き上げが産業界に及ぼすマイナスの影響は、日本のような国と比べると限定的である。そもそもトランプ大統領が問題視しているのは、インドの輸入関税そのものというよりも、米国が抱える二国間の貿易赤字であると思われるが、これについては、たとえば石油やガスの購入を増やすことでほぼ解消できると思われている。
最も重要なのは、トランプ大統領にとっては、一時は145%もの関税を課すと発表した中国こそが本丸の標的であることには変わりはないという点である。だとすれば、トランプ関税は中国との競争においてインドに有利に作用する。そのうえ、ASEAN諸国やバングラデシュ、スリランカなど他の輸出競合相手は、インドよりも高い税率を設定されていることを考えれば、世界の企業はインドを脱中国の生産拠点としてみなすだろうとの自信である。
実際、アップル社は米国向けiPhoneの大半をインドで製造する計画を発表した。これに対し、トランプ大統領はその場合には25%の関税を別途支払うことになるなどと牽制したものの、米国内で製造を完結するというのは非現実的なのは火を見るより明らかである。インドへの投資が進むはずだ。そんな楽観論が広がっている。
他国に先駆けて進んでいる二国間交渉では、インド側は一定量までの自動車部品や鉄鋼の関税ゼロを提案しているなどとされる。第一次産業が依然として就業人口の半数近くを占めるインドの現状を踏まえると、主要農産物の自由化を受け入れることはないであろうが、それ以外の分野では譲歩の余地がある。トランプ関税という外圧が、むしろインドの保護主義的な政策を転換し、競争力を高める改革のきっかけになると期待する向きもある。
実際、トランプ関税を意識した2025年度予算では、EV用バッテリー製造の資本財、銅、コバルト粉、リチウムイオン電池を含む12の重要鉱物のスクラップに対する関税免除が発表され、自動車業界はインドでの製造を後押しするものとしてこれを歓迎した。
他方で、モディ政権は「トランプペース」での交渉を避ける対抗策も打ち出している。5月に入り、インドは米国が3月に発動した25%の鉄鋼・アルミニウム関税に対し、報復措置を取る意思を世界貿易機関(WTO)に通知した。また、トランプ関税を牽制するかのように、一時は暗礁に乗り上げていた英国との交渉を一気にまとめ上げ、5月、印英自由貿易協定(FTA)合意を発表した。例えばインド産のエビが最大の消費国である米国から締め出された場合には、英国という新たな市場で売ることが可能になると期待されている。英国のみならず、欧州連合(EU)やニュージーランドなどともFTA交渉を加速させ、トランプ関税への対応を急いでいる。
トランプ関税と今後ありうる米中貿易戦争を巡ってインドが恐れているのは、世界経済自体が停滞し、そのことがインド経済の成長の妨げになるという点だが、これは自国ではどうにもならない。もう一つの懸念は、米市場から締め出された中国や他の国々の輸出品が、ダンピングされて大量に流入するというシナリオである。
14億の成長市場を世界が見逃すはずはないからである。すでにその兆候は見え始めているが、これに対しては、その都度、反ダンピング関税を発動するという対処療法を採用していくものと思われる。懸念はあるが、インドでは、トランプ関税は総じて自らの成長と改革の機会になるとのポジティヴな受け止め方が支配的である。

《キュウ タイゲン》
1956年生まれ。1995年2月日本東京大学大学院医学系研究科修士。2022年8月国立台湾大学医学部名誉教授。2024年5月衛生福利部長に就任。
2025年5月19日号 週刊「世界と日本」第2293号 より
台湾健康保険制度30周年
全ての人々の健康創造と、より健康な台湾を求めて
中華民国(台湾)衛生福利部長
邱 泰源氏
健康権は基本的人権であり、普遍的価値観でもある。健康の向上は、人々の福祉増進に関わるのみならず、世界各国の生存と発展にも影響をもたらす。昨年の第77回「世界保健機関」(WHO)年次総会は「世界保健総会 (WHA)2025―2028年度 第14次総合事業計画」(GPW14)を承認し、その中には「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジのためのプライマリ・ヘルス・ケアとエッセンシャル・ヘルス・システムの能力向上」の戦略目標が含まれ、各国に関連テーマへの行動を呼びかけた。
台湾は1995年に「全民健康保険」制度を創設し、それまで職業ごとに異なっていた保険制度を統合し、現在は保険カバー率が99・9%を超える「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ」を実践している。この30年間、台湾の人々に公平で、利用しやすく、かつ効率的な医療保障を提供しており、台湾社会の安定と人々の健康安全における重要な柱かつ保障となり、さらにはユニバーサル・ヘルス・カバレッジの模範となっている。同制度はグローバル・データベース・ウェブサイト「Numbeo」(ナンベオ)のヘルスケア指数ランキングで7年連続首位をキープしている。
台湾の健康保険の財務運営は、賦課制度、自給自足モデルを採用しており、保険料改革および財源の補充(たばこ健康福祉金等)を通じて、人口高齢化および医療コスト上昇といった財務的課題に効果的に対処し、制度の安定性と持続可能性を維持してきた。
台湾の国民の健康を持続的に向上させるため、台湾の頼清徳総統は2024年に「健康台湾」の政策ビジョンを提唱し、国民が健康になることで、国がより一層強くなり、世界も台湾を受け入れるようになることを期待した。これは、人を中心とし、家庭を核心とし、コミュニティーを基礎とする理念を有し、積極的に健康促進と予防保健のサービスを拡大している。例えば、「かかりつけ医プロジェクト」および「全ての人とコミュニティーのケア・プロジェクト」を通じて、慢性疾患患者に包括的ケアを提供している。また、遠隔医療を通じて過疎地域の医療サービスのアクセス性を向上させ、長期ケアと緩和ケアの一体化サービスを推進し、住み慣れた地域での居住を実現し、全方位的に、全ての人、全ての年齢層に尊厳あるヘルスケアを確保し、健康権の平等を真に実現する。
また、WHOは2021年に「デジタルヘルス2020―2025に関する世界戦略」を発表し、人を中心とするデジタル・ヘルス・プランを迅速に発展・運用していくことを提起した。そのプランを通じて、感染症の予防、測定と対処を行い、関連するインフラの構築とヘルスデータの応用で健康と福祉を促進する。台湾は引き続き、情報通信の優位性を運用し、健康保険クラウドシステムによる電子カルテ情報共有の効率化、FHIR(高速ヘルスケア相互運用性リソース)に準じた国際医療データ交換の推進、AI(人工知能)技術を活用したスマート医療の発展の推進などを含む、高コストパフォーマンスおよび効率的な保険システムとサービスを構築していく。バーチャル健康保険カードと「マイ・ヘルス・バンク」アプリにより、リアルタイム健康情報の管理を実現し、人々が健康に有益な選択をするよう促進していく。
2008年より、台湾は「医療技術評価」(HTA)を導入し、実証に基づき政策を策定している。それにより、新薬を迅速に健康保険に適用させることを促進できた。2023年にも初めて遺伝子と細胞の治療薬品が適用され、精密医療の先駆けとなり、患者の治療の選択肢が改善された。さらに、革新技術の運用により医療環境の改善をサポートし、スマート医療ケアを発展させ、全体の医療サービスの質と量を向上させ、人々により良いヘルスケアの質を提供していく。
台湾は政治的な課題に直面しながらも、常にグローバル保健実務に積極的に参画しており、グローバル保健システムを支持することに力を入れている。新型コロナウイルスの流行時、台湾は防疫物資、技術、経験を分かち合う際に極めて重要な役割を発揮し、世界各国から信頼される協力パートナーとなった。また、台湾の健康保険の経験は世界に貴重な鑑となるものである。台湾は引き続き全民健康保険、財務管理、デジタルヘルスなどの分野における成功の経験を各国と分かち合い、より多くの国々がWHOの掲げるユニバーサル・ヘルス・カバレッジの目標を実現するのを協力していく。
目まぐるしく変化するこの時代に、健康はボーダレスな課題であり、グローバルな協力がさまざまな危機に対処していく重要な鍵となっている。ところが、中国は国連総会「第2758号決議」(アルバニア決議)とWHO総会「WHA25・1号決議」の2つの決議をことあるごとに曲解し、台湾を世界の最重要な保健協力システムであるWHOに参加できないようにしている。ここで注目すべきことは、この2つの決議は「台湾」あるいは「台湾が中国の一部である」とは言及されておらず、中華人民共和国にWHOにおける台湾の代表権を与えるものではないということだ。
国連の包容性と普遍性の核心的価値を実践するため、台湾はWHO及び関連各方面に対し、台湾の長期にわたるグローバル保健システムへの貢献を注視し、WHOがよりオープンな姿勢と柔軟性を持ち、専門的かつ包容性の原則を堅持し、台湾がWHO年次総会および「WHOパンデミック協定」の協議を含むWHOが主催する会議、活動、メカニズムに参加できるよう、WHOが自主的かつ実務的に台湾を招待するよう願っている。台湾は国際社会と引き続き手を携えてボーダレスな健康の未来を共に創出し、WHO憲章にある「健康権は基本的人権である」、並びに国連「持続可能な開発目標」(SDGs)にある「誰も取り残さない」のビジョンを共に実現していくことを心より望んでいる。

《にしの じゅんや》
1973年生まれ。96年慶應義塾大学法学部政治学科卒業、同大学大学院法学研究科政治学専攻修士課程修了、2005年、韓国・延世大学大学院政治学科博士課程修了(政治学博士)。専門分野は東アジア国際政治、現代韓国朝鮮政治、日韓関係。慶應義塾大学法学部専任講師、同准教授を経て現職。共著書に『戦後アジアの形成と日本』、『朝鮮半島と東アジア』、『アメリカ太平洋軍の研究』など。
2025年5月19日号 週刊「世界と日本」第2293号 より
先行き不透明な朝鮮半島情勢
慶應義塾大学法学部教授 東アジア研究所長
西野 純也氏
第2期トランプ政権の発足は、朝鮮半島情勢にも不透明感をもたらす要因となっている。韓国も日本と同じく「トランプ関税」への対応として対米交渉を迫られており、その交渉の先行きを見通すことは容易ではない。加えて韓国内で懸念されているのが、昨年に米韓間で合意した防衛分担特別協定(SMA)の再交渉を求められたり、在韓米軍の削減が議論される可能性である。第1期目やこれまでのトランプ大統領の言動に鑑みて、米国が韓国防衛の一義的責任を韓国にさらに強く求め、米国の負担を減らす措置として在韓米軍の削減を検討することは十分にあり得る。となれば、それは日本の安全保障環境の悪化としてのしかかってくるかもしれない。
日本の安全保障という観点からもう一つの大きな懸念材料が、トランプ大統領と金正恩総書記とのやりとりが再開され、それが米朝交渉へと発展する可能性である。トランプ大統領はかねてより金総書記との良好な関係をアピールし、1月の就任直後と3月には北朝鮮を「核保有国」だと発言したこともある。そのため、米朝対話さらには交渉が始まることになれば、それは「北朝鮮の非核化」を目指すよりも軍備管理交渉の性格を帯びるのではないか、との見方がメディア等に根強く存在し続けている。
しかし、米朝対話がいつ行われるのか、本当に行われるのか、依然として見方は分かれている。ウクライナや中東の情勢が落ち着きを見せれば、トランプ政権は、次は北朝鮮問題に取り組むのではとの観測があったが、ウクライナも中東も情勢安定化の兆しはなかなか見えない。また最近、米朝交渉に備えた人事ではないかと見られていたアレックス・ウォン国家安保担当大統領副補佐官がトランプ政権から退くことになった。つまり、米朝対話の可能性を見極めることが難しい状況となっている。
金正恩総書記も米国との交渉に前向きなわけではない。今年は北朝鮮の経済発展5カ年計画及び国防力強化5カ年計画の最終年であるため、金正恩政権は国内向けに成果を示す必要があり、外交よりもないち内治に集中している。特に、今年秋には朝鮮労働党創建80周年の記念日が控えていることに加え、来年初めには5年ぶりとなる第9回党大会が開催される可能性が高く、「人民生活の向上」に資する成果を上げなければならない。ロシアとの戦略的連携の深化もあり、対米交渉を急いではいない。
以上のように、トランプ政権の発足は朝鮮半島情勢に不透明感をもたらしているが、それだけではない。韓国政治の混迷もまた、情勢の展望を困難なものにしている。昨年12月の尹錫悦大統領(当時)による非常戒厳の発令とその後の韓国政治の展開は、朝鮮半島情勢の先行きを一層不透明なものにしている。4月に憲法裁判所が尹大統領の罷免を決定して6月3日に大統領選挙が実施されるが、選挙結果は予断を許さない。5月上旬の時点で最大野党・共に民主党の李在明候補が各種世論調査ではトップを独走するが、5件の裁判を抱える李候補に拒否感を抱く国民も多い。公職選挙法違反の罪に問われた裁判では、5月1日に韓国の最高裁判所が2審の無罪を差し戻す判決を下したため、最終的には李候補が有罪になる見通しとなった。但し、最終的な判決がいつになるのか、被選挙権を失うような量刑になるのか、仮に李候補が当選した場合、大統領は在任中に訴追を受けないとの憲法の規定はどう解釈されるのか、など不透明な点が多い。
また、与党・保守陣営が候補者を一本化して選挙戦を展開することができるのかどうかも、選挙結果を左右することになる。もし、保守陣営が候補を一人に絞り込んで李候補との一騎打ちという構図を作れれば、保守と進歩(革新)の両陣営に分極化が進んだ韓国社会の現状では、選挙は接戦になる可能性もある。しかし、保守陣営が候補者を完全に一本化するのは容易ではないため、選挙戦では李候補の優勢が続くことになろう。
では与野党政権交代が起こった場合、韓国新政権の外交安保政策はどうなるのか。まず、米韓同盟が基軸であることに変わりはないが、トランプ政権が同盟軽視の姿勢を見せれば、韓国は同盟の中でより自立性を高める動きを進めることになろう。北朝鮮の核能力高度化などを受けて、米国の拡大抑止の信頼性に対する疑念が韓国社会で高まり、独自核武装論を唱える声がすでに大きくなっている。それに対して尹政権は米国の拡大抑止力の強化に努めてきた。バイデン政権との間で「ワシントン宣言」を出して核協議グループ(NCG)を新設し、韓国周辺に米国の戦略爆撃機や原子力潜水艦の展開を頻繁に行うことで抑止力の向上を図ってきた。新政権ではこうした動きからさらに進んで、韓国内で「核潜在力」と言われるウラン濃縮さらには再処理を目指すような政策論議が活性化するかもしれない。
加えて、歴代の進歩政権で進めてきた戦時作戦統制権の米国から韓国への移管に向けた動きが再稼働するであろう。文在寅政権の時には、戦時作戦統制権の移管により米韓連合軍司令部を未来連合司令部(仮称)へと改編する予定であったが、尹政権の発足後にその動きは止まっていた。トランプ政権が防衛費分担や在韓米軍削減などの問題を提起するようなことがあれば、より大きな枠組みでの米韓同盟の再調整へと発展していき、その中で「韓国防衛の韓国化」が一層追求される可能性は十分にある。その一方で、ここ数年の大きな成果である日米韓協力のこれ以上の前進は難しいであろう。日韓関係については、厳しい国際情勢に対処していくには関係をしっかり管理し、関係悪化は避けるべきとの認識の一致は韓国内にある。それを実現していくためには、新政権発足後のできるだけ早いタイミングで日韓首脳会談ができる環境を準備することが重要な第一歩となる。

《あびる たいすけ》
1969年生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒業、モスクワ国立国際関係大学修士課程修了。東京財団研究員、国際協力銀行モスクワ事務所上席駐在員を経て現職。専門はユーラシア地政学、ロシア外交安全保障政策、日露関係。著書に『「今のロシア」がわかる本』、『原発とレアアース』。監訳本に『プーチンの世界』がある。
2025年4月21日号 週刊「世界と日本」第2291号 より
米トランプ政権下での米ロ急接近の
戦略的背景と日本の選択
笹川平和財団上席研究員
畔蒜 泰助氏
米トランプ政権発足直後から米ロ両国が急接近し始めている。2025年2月11日、ロシア政府による米国人人質の解放を受けて、翌2月12日、米トランプ政権発足後、初めての米ロ首脳電話会談が行われた。これに続き2月18日にはサウジアラビアの首都リアドで米国側からはマルコ・ルビオ国務長官、マイケル・ウォルツ国家安全保障問題担当大統領補佐官、スティーブン・ウィトコフ中東特使が、ロシア側からはセルゲイ・ラブロフ外相とユーリ・ウシャコフ外交問題担当大統領補佐官が参加する米ロ高官協議が開催されている。
2024年11月の米大統領選に勝利したドナルド・トランプは、その選挙キャンペーン中からウクライナ戦争を早期に停戦させる意向を表明していた。そして2025年1月20日、米トランプ政権が正式に発足する前後から、ウクライナがNATO加盟すべきでないというロシアの立場に理解を示すなど、ウクライナや欧州諸国の頭越しに米国は従来の対ロシア政策の一大転換を図っているのだ。
ここで2025年2月12日に行われた米ロ首脳電話会談後、ロシア大統領府が発表した文書を確認したい。
「両首脳はウクライナ和平の可能性について話し合った。ドナルド・トランプは出来るだけ早く停戦し、危機を平和的に解決することに賛成した。一方、ウラジーミル・プーチンは紛争の根本原因を取り除く必要があると指摘し、平和的な交渉を通じてのみ持続可能な和平に達することができるという点で、ドナルド・トランプ大統領と同意した。また、中東和平、イランの核開発計画、ロシアとアメリカの二国間経済関係の問題も会話の中で取り上げられた。」
また、2月18日の米ロ高官協議後に米国側が発表した文書によると、米ロ両国は以下の点で合意している。
・在外公館機能の正常化・ウクライナ停戦・和平を巡るワーキング・グループのメンバー選定・立ち上げ・ウクライナ紛争終結の成功によって生まれるであろう、地政学的な相互利益と歴史的な経済・投資機会に関する将来の協力のための土台作り
ここで注目すべきは、米ロが一連の交渉において①ウクライナ停戦・和平、②相互利益のある地政学的問題での協力、③経済・投資分野での協力という三つの柱を同時並行的に行っているという点である。
但し、①についてはやはり2月12日の米ロ首脳電話会談でのロシア側の発表文書から判断して、米国が「出来るだけ早い停戦」を志向しているのに対して、ロシアは停戦の前に「紛争の根本原因を取り除く必要がある」と主張しているなど、米ロ両国にはその時間軸も含めて明確な違いがある。
2025年3月18日の二度目の米ロ首脳電話会談において、エネルギー関連施設への30日間の攻撃停止に合意する一方、アメリカがウクライナとの間で合意した30日間の停戦には応じないなど、米ロ両国の立場の違いは既に鮮明に現れている。ウクライナや欧州諸国は、戦況で有利に立つロシアが意図的に停戦を先延ばしにしているとの批判を積極的に仕掛けている。米国でもトランプ大統領自身、停戦交渉のスピード感に不満を抱いていることから、ロシア産石油・ガスの取引に追加制裁の可能性を示唆している。
それにもかかわらず、一連の米ロ急接近のトレンドは、今後、紆余曲折はあるものの反転はないと見ている。米トランプ政権は自らの戦略的必要性から従来の対ロシア政策の一大転換を余儀なくされているからだ。これを理解する上で参考になるのが、ウォルツ国家安全保障問題担当大統領補佐官がまだ下院議員時代の米大統領選挙直前に英エコノミスト誌に寄稿した共著記事の中の次の一節である。
「次期大統領は、ウクライナと中東の紛争を速やかに終結させるために緊急に行動し、最終的に戦略的に注意をすべきこと、即ち中国共産党のより大きな脅威に対抗することに集中させるべきである」と述べている。
つまり、米トランプ政権はもはや世界のあらゆる場所に軍事的に関与する余裕はなく、一日も早く欧州(ウクライナ)と中東での紛争を終結させて、米国にとって唯一の戦略的競争相手である中国の潜在的な脅威に備える必要があるとの戦略観が根底にあるのである。
ところで、前述の通り、米ロは①ウクライナ停戦・和平、②相互利益のある地政学的問題での協力、③経済・投資分野での協力という三つの柱を同時並行的に交渉していると指摘した。ここにおける②は前述した2月12日の米ロ首脳電話会談でのロシア側の発表文書から判断して中東和平問題やイラン核開発問題といった中東地域での米ロ協力であろう。
前述したウォルツの「ウクライナと中東の紛争の速やかな終結」との指摘とピタリと符合する。米トランプ政権はロシアが直接の当事者であるウクライナでの停戦は勿論、中東地域、特にイラン核開発問題の解決においてロシアとの協力を必要としているのである。
なお、ロシアは米ロ接近と引き換えに中国との戦略的関係を犠牲にすることは出来ないし、そのつもりもない。それでも米国がロシアと協力してウクライナと中東での紛争を終結さられれば、その戦略資源を中国が大きな影響力を有するインド太平洋地域に集中させることが出来る。ロシアもまた対ロシア制裁の部分緩和を受けて米国やその同盟国との経済・投資協力が復活すれば、ウクライナ戦争の勃発以降、中国への経済的依存度を著しく高めている状況を改善でき、あからさまに露中関係を悪化させることなしに、中国とのバランス・オブ・パワーを回復できる。
とすれば、米トランプ政権が対中国戦略の一環としてロシアとの急接近を図る中で、我が国もまた、安倍政権時代の対ロシア積極関与政策を復活させるのか?それとも異端のトランプ政権の対ロシア政策の一大転換は成功しないと見て「今日のウクライナは明日の東アジア」との岸田政権が掲げたスローガンの下、引き続き欧州諸国と連携してウクライナ支援と対ロシア経済制裁という従来の対ロシア政策を継続するのか?早晩、どちらかの決断を迫られることになろう。

《ちの けいこ》
横浜市生まれ。1967年に早稲田大学卒業、産経新聞に入社。マニラ特派員、ニューヨーク支局長。外信部長、論説委員、シンガポール支局長などを経て2005年から08年まで論説委員長・特別記者。現在はフリーランスジャーナリスト。97年度ボーン上田記念国際記者賞を受賞。著書は『戦後国際秩序の終わり』(連合出版)ほか多数。近著に『江戸のジャーナリスト 葛飾北斎』(国土社)。
2025年4月21日号 週刊「世界と日本」第2291号 より
パナマ運河返還を巡る米パ紛争
歴史に翻弄されたノリエガ将軍
ジャーナリスト
千野 境子氏
ウクライナ停戦、関税賦課、グリーンランド買収、ガザ再開発、カナダ併合、不法移民追放…次々と「標的」を定めて我が道を突っ走るトランプ大統領。具体的な成果は未だの感もあるが、パナマ運河ディールには米軍のパナマ侵攻と独裁的指導者ノリエガ将軍の失墜が思い出される。米国はパナマ運河奪還に再び武力行使するのだろうか。
トランプ氏は大統領就任前から今まで、通航料金への不満に始まって運河を取り戻すためには軍事力行使も排除せずとの強硬発言を続けて来た。相手の反発など歯牙にもかけない。
しかし政権も100日を前にディール外交の正体もかなり見えてきた。最初に暴言や妄言で耳目を集めてディールが始まる。本音や本意は後回しだ。
パナマ運河も本音は運河支配、即ち管理権の獲得であり、それを嚆矢に中南米から中国の影響力を排除する。最終目標は締め出しと考えられる。
相手側から総スカンのグリーンランドやカナダと異なり、パナマ運河は3月初め、運河の太平洋側バルボア港と大西洋側クリストバル港の2港を運営する香港系複合企業CKハチソン社が、米投資会社へ株式の大半の売却で合意した。実現すれば米国には大きな得点だが、ここへ来て中国がCKハチソンと関係のある企業と協力しないよう国有企業に指示するなど売却阻止に圧力をかけ、着地点はまだ不透明だ(本稿執筆時点)。これもディールの一環だろう。
また2月にはヒスパニック系のルビオ国務長官が初外遊先として中米5カ国を歴訪した。パナマを含む4カ国は近年、外交関係を台湾から中国に乗り換えた国々で、狙いが中国の影響力排除にあるのは明らかだ。歴訪はそのための第1歩だった。
パナマのムリーノ大統領はルビオ長官訪問後、すぐに中国の「一帯一路」構想参加へ今後見合わせることや、不法移民の受け入れに前向きの対応を表明した。パナマ側の譲歩と言えるが、米国は感謝や見返りを与えるどころか、運河支配へ攻勢をさらに強める構えを見せており、譲歩は対トランプ・ディールで裏目に出た形だ。
なぜムリーノ氏は「パナマ・ファースト」を掲げ「アメリカ・ファースト」に対抗しなかったのか。トランプ氏は第1期政権でもパナマに運河返還要求をしており、当時のバレーラ大統領の「静かな外交」を見習ったのかもしれない。あるいは今回、関税戦争に突入しかねないカナダ式対応を避けたのだろうか。
パナマ運河を巡る一連の動きを眺めながら改めて思い出すのは、最高実力者として独裁的権力を揮ったノリエガ将軍(1934~2017)のことである。同将軍の去就を巡って米パ関係が対立・緊張を深めていた1989年11月、私はパナマシティーの国防軍司令部でインタビューにこぎつけた。小柄ながら糊の効いた軍服姿はサマになっていた。「パナマと将軍の将来について」という最後の質問への答えは、思えば暗示的だった。
「国はその持てる労働能力と地理的条件に左右される。ちょうど日本が敗戦の廃墟の中から見事に蘇ったように、パナマもたとえ政府は変わろうが、その位置は変わらず国家は永遠である。私個人の今後については神のみぞ知るということにして頂く」
翌12月、米軍はパナマに侵攻。将軍配下の国防軍の名実共に解体を目指し、国防軍司令部は爆撃で瓦礫と化した。ノリエガ氏はと言えば、逮捕され米国で長い収監生活の後、母国で生涯を終えた。
パナマ運河は、ノリエガ氏がまさに言うように地理的条件によって世界のハブとして国家の存立基盤となり、しかしそれゆえに対米関係に翻弄される歴史を歩んだ。もともとは1869年にスエズ運河を建設したフランス人外交官レセップスらの建設が挫折し、1903年に米国が当時コロンビアから独立したばかりのパナマと条約を結んで建設を再開、難工事や伝染病流行の末に1914年に完成した。
この工事で米国人3万人が犠牲になったとのトランプ発言は1桁多くフェイクだが、米国の功績が大きいのは確かだ。条約も米国が運河の管理・支配権を永久に持つとした。
しかしパナマにすれば、運河地帯はパナマの土地であり条約により主権が及ばないのは不当だ。建設当初からのこうした不満は時代と共に高まり、1959年には運河地帯に入りパナマ国旗を掲げようとした抗議運動が流血を伴う事態にまで発展した。
米パの長い確執が終わるのは、1999年12月31日を以って運河のパナマ側への返還を謳った新パナマ条約に、カーター大統領とトリホス将軍が1977年に署名調印したことだった。
「私は天国に入りたいとは思わない。私が望むことはただ(パナマ)運河地帯に入ることだ」とは、トリホス氏の墓碑銘だ。パナマ人の悲願を象徴する文言であり、パナマ民族主義の父として国民から仰がれてきた。トリホス氏の後ろ盾で成り上がったノリエガ氏とは大違いである。
それほど大切な運河なのに、パナマがトランプ政権の要求に抵抗せずに譲歩するのは何故か。ノリエガ氏と米軍侵攻の悪夢がパナマの人々の深層心理に残っていると見るのは思い過ぎだろうか。
当時、国民の大半は独裁者の失脚に歓喜し街頭に繰り出したが、圧倒的な力による追放と破壊、混乱は米国への複雑な思いを抱かせ、二度と経験したくないトラウマともなった。
一方米国では新パナマ条約の批准が難航し、以後共和党や保守派を中心にカーター氏への恨みも返還要求も脈々と続いてきた。ただトランプ氏以前の大統領は声を上げなかっただけである。
米パの話に終始してきたが、パナマ運河はスエズ運河と並ぶ今尚世界の二大物流の要衝であり、年間通航隻数は1万3003隻、利用国(重量ベース)は①米国②中国③日本④チリ⑤韓国(いずれも2022年会計年度)で、日本・アジア諸国には南北米貿易に不可欠のルートだ。中国の存在感は数字からも歴然である。
米パの攻防は続く。パナマは対中経済依存の脱却も迫られるだろう。米国は力を以ってすれば運河地帯の支配は容易い。だが米国がそれで失うものはずっと大きいはずだ。

《みのはら としひろ》
1971年生まれ。神戸大学大学院法学研究科教授、インド太平洋問題研究所(RIIPA)理事長。専門は、日米関係・国際政治・安全保障。カリフォルニア大学デイヴィス校を卒業後、1998年に神戸大学大学院法学研究科修了、博士号(政治学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、神戸大学法学部助教授を経て、2007年より現職。著作としては、『大統領から読むアメリカ史』(第三文明社、2023年)など。清水博賞、日本研究奨励賞を受賞。
2025年2月17日号 週刊「世界と日本」第2287号 より
「トランプ2.0政権の発足と
日本に求められる対応」
神戸大学大学院法学研究科教授
インド太平洋問題研究所理事長
簑原 俊洋氏
前回、本稿において次のように書いた。「躊躇なく言えるのは、トランプ2.0は1.0と比較にならないほど国際政治に波乱をもたらし、日本を含む価値を共有する国家に対して幾多の苦難をもたらすということだ。」さらに、事前の備えは不可欠で「価値を共有するEU、韓国、カナダ、オーストラリア等と連携を取り、・・・国ごとのちぐはぐな対応ではなく、足並みを揃えて面として対応できるようにしておくことが国益と合致しよう。」とも述べた。
1月20日の就任式を経て、まさしくこの通りになった。つまり、自由主義世界にとって不幸なことに、「啓蒙なき自己利益」を礎としつつ、米国の「狭い国益」の追求に固執するトランプ大統領が当選したのだ。しかも、最高裁によって勝敗が決した2000年の大統領選以来で最も接戦となったものの―一般投票者数ではわずか1・5%差―、2016年の時と異なり、トランプ氏は選挙人数と一般投票者数の双方で過半数を得た。これは、彼の勝利が単に選挙制度がもたらした不都合な「事故」ではなく、多数のアメリカの有権者が望んだ結果であったことを意味する。
そのトランプ2.0が前回とは全く性質が異なることを最初に明白にしたのが、とてつもないスピード感をもって押し進められた閣僚人事であった。また、その人選も、〈能力〉よりも〈忠誠心〉に重きを置いた結果、軍人(退役軍人を含む)の入閣は激減した。加えて、道徳や倫理観が問われている人物も複数要職に任命した。例えば物議を醸した国防長官の人事は、上院で50―50と引き分けたことで、副大統領がタイブレイク票を投じてやっと承認にこぎ着けたほどであった。ともあれ、問題を多く抱える人物が承認されたこと自体、トランプ氏がいかに共和党を牛耳っているかを如実に示す。さらに、保守が過半数を占める最高裁の存在もあり、立法府に対する行政府の力は一気に増している。
権力の座に返り咲いたトランプ氏は、自らの正当性が立証されたと確信し、これが大胆に政策を実行する原動力となっている。事実、初日だけで26の行政命令と200を超す行政人事令に署名したが、この数はあらゆる記録を凌駕するものだ。むろん、トランプ氏の「革命」は一日で結実することはない。少なくとも中間選挙までは、自らの利益と合致する「偉大な米国」の国家づくりに勢いよく邁進していく。
本業が不動産にあったためか、二期目のトランプ氏は米領土の拡大に特に情熱を注いでいる。その戦略的重要性を踏まえ、パナマ運河とグリーンランドの割譲、そして隣国カナダを51番目の州として併合することに度々言及している。このように今までの常識を打ち砕き、価値を共有する国家であっても一切容赦しない新大統領の強硬な姿勢には唖然とさせられる。彼は恫喝によって相手に対して好ましくない状況を醸成し、その改善と引き換えに自らにとって有利な譲歩を引き出すのが常套手段だ(どこか中国と重なる)。当然、反発するとさらに激しい反撃に晒される。
ある米政府高官によれば、パナマ運河での目的は通航する米商船(特にLNGタンカー)に対する通行費の免除であり、そしてグリーンランドについては、武力による併合ではなく、先住民が大部分を占める島民に現金を支給してデンマークからの独立させるのが目的だとのことだ。他方、カナダについては、非友好的と見なしている与党を下野させ、なおかつ対米貿易黒字を大幅に削減するための圧力という説明がなされた。
では、トランプ氏は日本に対しては融和的に臨むのか。前述の高官曰く、その答えは日本の出方次第にある。まず求められるのは、対米貿易黒字の解消であり―トランプ氏の頭の中では、対米貿易で黒字がある国家は米国から「ぼっている」ことになるため―、そして防衛費をGDP比3%に引き上げることが最低条件となる。そのため、一石二鳥の解決法として、米国製の武器や装備品の大量購入が示唆されている。
むろん、関税を課す国家とそうではない国家とに分ける(率の違いも含む)ことによって国家どうしの結束を抑制できるため、分断を促すための道具としても関税は有効的に用いられよう。加えて、トランプ大統領と彼の取り巻きは、世界においてカオスを生み出すことによって米国はより多くの利益を得ることができると考えている。その一環として、ポピュリスト的な愛国主義右派勢力を積極的に支持することを訴えており、その主対象は欧州である。つまり、EU内の分裂を導き出し、米国に対して対抗できる存在としての力を削ぐという目的に他ならない。
こうした関税を含む同盟国に対するなりふり構わぬ姿勢は、必然的に中国に千載一遇の好機をもたらす。すなわち、同盟が揺らぐ隙を狙って接近することで、中国はこうした国々の対中経済依存を拡大できる。先般の戦略的互恵関係の宣言が示すとおり、日本も標的であり、中国は今後対日アウトバウンドを増やすのみならず、東北地方の海産物の輸入解禁もちらつかせている。また、日本のメディア関係者によれば、以前と打って変わって中国当局の接し方は友好的だという。その中国は、短期的には貿易問題において米国を利する形で譲歩してトランプ氏を宥めつつも、中長期的には第一列島線において自国にとって有利な地政学的な現実を確立したいと考えるのが合理的である。その意味でトランプ政権の再来は、現状変更を可能にする転機となる。
では、米国が予測困難な変数となった時代を日本はいかにして生き抜くべきか。まずは、正確な情報の収集であり、続いては、トランプ政権内に限定されることなく、米国内のあらゆるレベル(連邦・州)において質の高い複数のパイプを持つことである。なぜならトランプ政権が多面体であり、互いに警戒・牽制し合うグループが大統領に対する影響力をめぐって激しく鎬を削っているからだ。これらの中でどのグループが優位に立つのかを素早く把握することが肝要となる。さらには、本稿冒頭でも述べたとおり、自由主義世界の分断を試みるトランプ政権の矛先がたとえ日本に向けられても冷静沈着に対応する傍ら、価値を共有する国家とのさらなる堅固な連携は不可欠である。とりわけ、EUとオーストラリア、さらには海洋ASEANとの繋がりの強靭化は焦眉の急だ。万一、米国がNATOを揺るがすような事態を惹起した場合、逆に日本は既存のIP4(日豪NZ韓)の枠組みに拘泥されることなく単独でもNATOとの関係強化に動くべきだ。なお、NATO東京事務所の設置は、独仏両国が中国に忖度したために見送られたと聞くが、背に腹は代えられない。米国の孤立主義的な姿勢が、多くの局面で日本の重要性を増大させるであろう。米国が従来の外交路線を覆す「革命的新外交」を追求するのであれば、日本もまた能動的に外交を展開し、もっぱら米国に寄りかかる今までの形から多角的な同盟枠組みを模索する契機と捉えるのが、国益を担保し続ける最善の方策ではなかろうか。

《かわぐち まーん えみ》
85年シュトゥットガルト国立音楽大学大学院ピアノ科修了。共著に『優しい日本人が気づかない 残酷な世界の本音』(ワニブックス・福井義高)最新刊は『ドイツの失敗に学べ?』(ワック)など著書多数。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より
日本が学ぶべきドイツの失敗
作 家
川口 マーン 惠美氏
新年号なのでおめでたい話を書こうと思ったが、良い材料は何もなかった。21年12月にできた社民党のショルツ政権は、緑の党と自民党との三つどもえの連立政権だったが、3年間、政府内で喧嘩ばかり。いざこざの原因をひと口で言うなら、社民党と緑の党が進めた無意味なお金のばら撒き、脱炭素という名の産業破壊、難民の無制限受け入れといった政策に、現実派の自民党が抵抗し続けたこと。要するに、最初から無理な連立だった。
現在のドイツはインフラが崩壊。9月には何もしないのに、深夜、ドレスデン市の中心に架かっていた鉄橋が、エルベ川に崩落。その他も全土の鉄道、橋、道路が老朽化しており、修繕の掛け声は高いが、予算不足、人手不足で進まない。聞こえてくるのは、工事による鉄道の遅延と、道路の渋滞ばかりだ。
自治体は、国が無制限に入れ続ける難民を割り当てられ、極度に困窮。それどころか、庇護しなければならないと言われていたその気の毒な人たちのお陰で治安が悪化し、今やクリスマスマーケットまで厳戒態勢だ。ドイツの都会は、夜、一人では歩けなくなってしまった。
一時は独り勝ちと言われたドイツだが、典型的な株主資本主義に陥っていたため、国民は捨て置かれた。内需にはお金が回らず、年金生活者は貧しくなった。OECDが15歳の児童を対象に定期的に実施するPISAテストでも、ドイツは数学も読解力も科学も、10位以上に影も形も出てこない(日本は全て上位)。
その危ういドイツ丸の舵を握っているのが、経済音痴のハーベック経済・気候保護相(緑の党)。氏はエネルギー危機の真っ最中に、せっかく快調に動いていた原発を止め、緑の党の50年来の夢であった脱原発の完遂を祝った。まさに国富の破壊である。
しかし、船長室のショルツ首相(社民党)は国家の運命など眼中になく、自分の保身のためにひたすら沈思黙考。そんな中で自民党のリントナー財相は、財布は握っていたが主導権は握れず、ドイツ丸は一途、暗礁に向かって突き進んだ。
その結果、今やドイツ経済は一から十まで劣悪だ。大企業は、国内の工場は閉鎖か縮小で、製造部門をすごい勢いで国外に移している。しかし中小企業は取り残されて、倒産。主原因はもちろんエネルギーの高騰。高い電気で高い商品を作っても、誰も買ってはくれない。
ただ、国民は長い間、ドイツ丸が傾いていることを直視しようとしなかった。初めて目が覚めたのは、フォルクスワーゲン(以下・V W)の工場閉鎖と3万人解雇の報で、その途端、上を下への大騒ぎとなった。VWの敗因は、エネルギーの高騰に加え、EVシフト作戦の失敗でもある。
ドイツ政府が飴(購入時の補助金)と鞭(35年以後ガソリン・ディーゼル車の新規登録中止)を駆使して、国民をEV車に追い込み始めたのはメルケル政権の時だ。政府が生産を統制するのは、計画経済に他ならない。
ところがVWはその計画経済を良しとし、全面EVシフトに突き進んだ。つまり、政府の権力を笠に着て、消費者に彼らの望まないものを無理やり押し付けようとしたわけだ。自由経済の終焉、まさに東独化だった。ただし計画経済というのは、必ず計画倒れとなる。
22年秋、ドイツ政府は予算に違法なお金を組み込んでいたことを憲法裁判所(最高裁に相当)に咎められ、修正した途端、極度の金欠に陥った。そこで、EV購入時の補助金を外したら、それまでも売れなかったEVは、全くといって良いほど売れなくなった。E Vに対する、いや、東独化に対する国民の抵抗は思いのほか激しかった。ドイツ経済にとって、国家の政策ミス、企業の判断ミスは致命的で、それを被ったのが国民だったのだ。
ただ、この期に及んでも、緑の党の応援団である公共メディアは、政府の馬鹿げた経済目標や、ホームメイドのエネルギー高騰を批判せず、声を揃えてVW社の失敗の原因はEV開発に乗り遅れたことだと主張している。公共メディアが政府批判をしないのも、やはり東独化の一環だ。危ない、危ない!
11月1日には、自民党のリントナー財相が犬猿の仲のショルツ首相に、経済再建プランを提示したことで、政府内の争いがエスカレート。その後の緊急会議では、金欠緩和のために借金を増やせというショルツ氏と、増やさないというリントナー氏が正面衝突し、ついに6日、ショルツ首相がリントナー財相を解任という運びとなった。それを受けて自民党が連立政権を離脱。ドイツ丸の座礁である。
これにより政府は過半数割れのレームダック状態となり、野党第1党CDU(キリスト教民主同盟)のメルツ党首は、国民の信を問うためと、総選挙の繰り上げを迫った。
ドイツでは首相の一存で国会は解散できず、ここでは触れないが、いくつかの段階を経なければならない。今や、戦後史上最低の呼び名の高いショルツ首相は、総選挙をなるべく引き伸ばそうと画策したが、野党と国民が攻め立てたため、おそらく2月23日になる模様。その結果、第1党がCDU、第2党がAfD(ドイツのための選択肢)となることもほぼ確実だ。
ただ、問題はその後の連立交渉。もし、C DUがAfDと組むなら、ドイツには久しぶりに安定した保守政権ができるはずだが、C DUはいまだに、“極右”で“反民主主義”のAfDとは絶対に組まないと言っている。かといって、自民党は泡沫だし、緑の党と社民党と3党連立すれば、今のカオス政府の二の舞で何も変わらない
そもそも国民は、社民党や緑の党の左翼政治に愛想を尽かしたからこそ、保守のCD UとAfDに望みを託したのだ。ところが、CDUが政権を取っても、またぞろ緑の党がくっついてきて、今まで通り脱炭素という“宗教”が大手を振るい、再エネ、EV、難民を押し付けられ、それをメディアが鼓舞する状態が続けば、その時こそ国民は堪忍袋の緒が切れる。
こうなると、誰もが持つ単純な疑問は、C DUは本当に保守なのかということ。
実は、CDUが保守党だったのは過去の話だ。それどころか、メルケル氏が真に心を通わせていたのは緑の党で、首相終盤の頃、氏はそれを隠そうともしなかった。
ちなみに、16年のメルケル治世のうちの12年は社民党との連立だったが、その間、社民党はどんどんメルケル氏に政策を取られた。脱原発、徴兵制停止、再エネ拡大、難民の無制限受け入れ、同性婚の合法化、補助金のばら撒きは、皆、社会主義者の好む政策だが、メルケル氏はこれらを「民主主義の強化」として売り込み、国民はそれを信じた。
その政権を引き継いだショルツ首相は、メルケル人気にあやかろうと既存路線を忠実に踏襲。それどころか、メルケル氏が果たせなかった緑の党との連立まで実現させた。そして、3年後の今、ドイツ丸はブクブクと沈み始めている。
前世紀の2度の大戦に耐え抜いた多くの優良中堅企業を、ショルツ政権がたった3年でバタバタと倒産させていく様は、あまりにも悲しい。しかし、ショルツ首相もハーベック経済・気候保護相も反省の色はなく、来たる総選挙では共に次期首相を目指すライバルとして立つという。国民との温度差は限りなく大きい。
さて、最後に一言。3割もの票を獲得したAfDという政党を、支持者もろとも極右だ、反民主的だといって排除しているドイツが、民主主義のはずはない。それどころか、AfDの綱領は実にまともだ。
なお現在、ドイツの多くの政治家は、S NSで自分の批判をした国民を侮辱罪で訴えることが常套化しており、政府や検察はもちろん、時に司法までが与している。例えばハーベック氏は、他愛ないSNSの書き込みの投稿者を、この2年で805回も告訴。被告は国に罰金を取られ、政治家に賠償金をむしられ、これこそ言論圧迫だと憤りつつ、やはり、以後は口を噤む。このような東独的手法が次期総選挙で消えることを、私は強く期待しているが、そのためには米国のような根本的な政権転換が必要なのかもしれない。つまり希望薄である。

《たにぐち ともひこ》
1957年生まれ、東京大学法学部卒。富士通フューチャースタディーズ・センター特別顧問、筑波大学特命教授、安倍第二次政権で故首相の外交政策スピーチライター。近著は『安倍総理のスピーチ』(文春新書)。記事はエコノミスト、フォーリン・アフェアーズ、ニューヨークタイムズに掲載。BBCほか国際放送出演が多数。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より
いまこそ必要な「外政家」とは
富士通フューチャースタディーズ・センター特別顧問
筑波大学特命教授
谷口 智彦氏
2025年、中国は台湾をめぐって挑発の度を高めるだろう。ウクライナと中東では、情勢が大きく動く。
日本にとって、強い外交力を一身に体現する「外政家」が、今くらい必要な時はない。
外政家とは誰か。
政治家は星の数ほどいても、「ステーツマン」の称号を得る人は多くない。それと同じで、外政家の名にふさわしい人は少ない。
日本が世界にようやくその存在感を増しつつあった1970年代から80年代、国際場裡で八面六臂の活躍をした人に大来佐武郎という人物がいた。
エンジニア転じてエコノミストとなった人で職業政治家ではなかったけれど、首相となる大平正芳などと強固な関係を保ち、自分でリスクを取れた人だ。
どこのどんな会議へ出てもいつも同じ大来がいるのに気づいた外国人に、日本は「大来依存症」だと揶揄する向きがあった。
これはむしろ褒め言葉だった。世界における大来の存在が、日本を体現し象徴するほど大きかったことをよく偲べるではないか。
そんな人物を今の日本は持てるだろうか。持ち得たはずだったということを後に見る。
高い知名度を得た大来は一見して識見豊かなうえ信頼が置けそうでもあって、外政家の一肖像を表していた。
外政家と呼ばれる域に至るには長く活躍することが大切で、できればひとの記憶によい印象を残す面立ちでもあった方がよい。そんなことを、大来の例から悟ることができる。
政府職員に過ぎぬ外交官と違って、外政家は自分で決断し、責任を取る人だ。総理大臣であればよし、でなくとも、大来がそうだったように最終決定権者と同じ判断、決断のできる人である。いきおい、政治家が多くなるのは当然である。
生まれついての外政家はいないし、白面の青年でしかも外政家というのもありそうにない。外政家とは環境に育てられ、自らを育ててなり得る何者かだ。
成功と挫折にいずれも自ら豊かな経験をもち、それがゆえに、相手国指導者の心中深くを推し量ることのできる人である。
ドナルド・トランプ米大統領ら民主主義国指導者の場合、次の選挙をどう勝つかが常に念頭を去らない。トランプ氏の頭は、もう、2年後の中間選挙に向いていることだろう。
選挙の心配がない習近平氏にしても似たり寄ったりだ。2027年、中国共産党の次なる大会で総書記として同氏が四選を果たせる保証は、全くない。
相手の不安や喜びが何か、すぐに見当がつかないようでは外政家たり得ない。外政家は相手との交渉を専らとするネゴシエーターでもある。やり合う相手の喜怒哀楽を理解していれば、攻め口を見つけやすいだろう。
外政家はまた、自ら政治家としてリスクをとったことがしばしばだから、相手がどこまで折れるかあるいは踏み出すか、およその見当がつく。秀でた交渉者となり得る所以だ。
そして人間にまつわる記憶力に優れたものがあると、なおよい。
相手が特に親しくしている友人は誰で、恩師はなんといい、配偶者との出会いは誰が仲立ちしたのか。先方の母は、誰の従姉妹か。
そんなあれこれに関して、発音するのさえ容易でない名前を次々口にしてみせれば、相手は驚嘆するだろう。
安倍晋三第二次政権では長谷川榮一総理補佐官兼内閣広報官が、まさにこの通りの記憶力をもっていた。
ひとのことを知るのが何よりも好きで、興味の対象が自分でなく他者に向く性向が強くないと、ひとにまつわる記憶は育たない。自己偏愛者は、外政家に恐らく向いていない。
歴史に学ぶ者が、賢者なのだとか。外政家はその意味で、賢い人でなければならない。
外交には、長い間に堆積した過去のいきさつがある。どの局面で誰が笑い、また泣いたかの、大小無数のドラマがある。それを面白いと思うのが外政家であって、彼または彼女は、伝記や回想録のよい読み手であろう。
すると外政家は、かなりの確度で自らメモワールの筆を執り、後進に影響を及ぼす人ともなるのではないか。
資格要件をいろいろ挙げてみて思うに、安倍晋三元総理を喪ったとき、わが国はたぐい稀なる外政家を、永遠に失ったのである。総じて同意いただけるだろうが、前に掲げたもろもろの資質を、安倍氏はみな兼ね備えていたではないか。
安倍氏は相手を問わずそうだったように、初対面のドナルド・トランプ氏に対し、嫌味や衒いが全くない真っ直ぐな視線を投げた。
マスコミの評価でなく、あなたが何を話すかにだけ自分は興味がある、だからこうして早々に来訪したと、安倍氏の目は語って雄弁だったであろう。ゴルフのプレイが先にあったのではない。安倍氏がトランプの理解者だったからゴルフをするようになり、親愛を互いに深めたのだ。
主要国首脳の、ほかの誰にもできないことが安倍氏にはできた。
安倍氏は累次の国政選挙に勝ちおのれの政治力を強くし続けたから、トランプ氏に加え欧州各国指導者も一人また一人、尊敬を寄せるようになった。
やがて得た国際社会の信任を力として安倍氏が打ち出したのが、「自由で開かれたインド太平洋」という大きな認識枠組みだ。
インド太平洋を「不自由で、開かれない」場にしようとする中国の向こうを張ったものだとすぐさま見抜いた先進民主主義各国指導者たちは、安倍氏の胆力とビジョン設定力に敬服した。やがて、自らも同じ旗を掲げるようになった。
日本発の旗印を友邦国が揃って翻すなら、わが国の国益が貫徹しやすい環境が現れる。外政家安倍晋三氏の、本領発揮であった。
存命なら、安倍氏はイスラエルに、ヨルダン、エジプト、トルコやサウジアラビアに行ったことだろう。このどの国にも、安倍氏を強く敬慕する元首や首脳がいた。これから激動する中東情勢に日本をどう絡めるか、安倍氏は構想したはずだ。
せめて安倍氏生前の軌跡を見直し、外政家の登場と成長を反芻して今後の糧としたい。

《り そうてつ》
専門は東アジアの近代史・メディア史。中国生まれ。北京中央民族大学卒業後、新聞記者を経て1987年に来日。上智大学大学院にて新聞学博士(Ph.D.)取得。98年より現職。同年、日本国籍取得。テレビのニュース番組や討論番組に出演、情報を精力的に発信。著書に『日中韓メディアの衝突』『北朝鮮がつくった韓国大統領―文在寅政権実録』『なぜ日本は中国のカモなのか』(対談本)など多数。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より
危機か転機か2025年の朝鮮半島
龍谷大学 教授
李 相哲氏
金正恩労働党総書記のロシアへの派兵決定に加え、韓国の迷走で朝鮮半島情勢は混迷の度合いを深めている。世界を欺き、住民に派兵の事実をひたすら隠して人民軍を「傭兵」としてロシアに派兵した狙いは何だったのか。大統領が弾駮され職務停止状態の韓国が、このような世界情勢の急変に対応できるのか。2025年の朝鮮半島情勢はさらに流動的になった。危機か転機か、トランプ政権誕生と相まって朝鮮半島は大きな転機を迎えつつある。
トランプ政権で朝鮮半島はどうなるか
トランプ政権誕生により、朝鮮半島と日本の安保に影響する問題は、当面二点ある。本当にウクライナ戦争を早期に終わらせることができるのか、北朝鮮の核はどうするつもりかだ。
トランプ氏は、大統領選挙遊説中に「私が大統領に就任すれば、24時間以内にウクライナ戦争を終わらせるだろう」と発言した。誇張された発言とはいえ、トランプ政権で決着をつける可能性は高い。短期で決着がつくのか、長引くのかについては、北大西洋条約機構(NATO)の思惑やロシアの意向、ウクライナの国内状況などが複雑に絡んでいるなど、不確定要素が多すぎるため、誰も予測できない状況だが、確実に言えるのは、ウクライナ戦争終結が第2次トランプ政権の優先課題であることだ。多少強引なやり方をもってしても、戦争を早期に終わらせるのではないか。
その場合、北朝鮮の立場がどうなるのか。北朝鮮は、現時点で約12000人の兵士をロシアに派遣し、1000万発以上の砲弾に加え、170ミリ、240ミリ放射砲、短距離ミサイルまで供与するなどしてロシアの侵略戦争に深入りしている。しかし、ロシアがウクライナ戦争で大きな果実を手にすることができれば、北朝鮮もその恩恵を被ることができるが、戦争がロシアの実質的な敗北で決着すれば、金正恩は大きなダメージを負うのは間違いない。
ウクライナ戦争の行方と関係なく、派兵の代価として金正恩は、人民軍に支払われる給与と死亡保険金名目の巨額な外貨を手にし、軍事技術、現代戦の経験を積むなどして軍事力強化を図るものとみられる。
さらに、危険なのは、北朝鮮がロシアのために血を流す代わりに、将来、朝鮮半島有事の際朝鮮半島にロシアを引きずり込むことだ。そうなれば、米軍と韓国は北朝鮮の挑発を抑えにくくなる。
米朝対話には高いハードル
金正恩の暴走を止めるべく、トランプ政権は早期の米朝対話を試みるだろう。北朝鮮が第7回目の核実験に踏み切る危険性もあり、ロシアに追加で派兵、ミサイル発射実験を繰り返して緊張を高める可能性を未然に防ぐためトランプ氏は金正恩とのトップダウン方式の問題解決を図ろうとするかも知れないが、不発に終われば、一気に金正恩打倒に傾く可能性もありうる。
今の金正恩は、①2019年2月の、ハノイの会談のトラウマがある上に、②仮に米国が制裁解除に動くとしても、北朝鮮がそこから実質的な利益を得るまでには長い時間がかかるので、ロシアに頼るのが得策と判断したとしても不思議はない。金正恩は最近「アメリカとの交渉ではやれるところまでやってみた。しかし、結果的に確認できたのは、超大国(米国)の侵略本性と敵対的な政策は変わらないということだった」(24年11月、国防発展展覧会2024での演説)と発言、米国との交渉に未練のない態度を見せている。
気になるのが韓国の対応だが、韓国は、いましばらく、北朝鮮問題に真剣に取り組む余裕などないのではないか。尹氏に対する国会での弾劾、権限代行までが弾駮された韓国政局はこれからも混乱は続くのではないか。万が一、尹氏が退陣に追い込まれ、早期の大統領選挙に突入すれば、ともに民主党の李在明代表が大統領になる可能性すらある。日韓の間で解決に向かっていた旧朝鮮半島出身労働者(徴用工)問題をはじめ、水面下に沈みつつあった歴史問題が再燃、日韓関係は振り戻しになるだろう。
ウクライナ戦争や中東紛争など喫緊な課題を抱えているトランプ政権は、これまでと同じく、アジアの安保問題では日本が国力に見合った責任を果たし、韓国とともに中国やロシアを牽制する役割を果たすことを期待するはずだが、日韓関係が悪化すれば、米国の世界戦略も狂ってしまう。このような、状況をチャンスと思い金正恩が韓国と日本を排除した状態で、核保有黙認を前提条件に対話に応じる可能性もある。ただ、朝鮮半島における紛争状態を避けたいトランプ政権とは言え、このような北朝鮮の要求に応じることはできないのではないか。
対話無理なら「力」の行使も
対話が通じなければ、米国が取りうる手段は力の行使だ。「戦わずして勝つ」という哲学をもつトランプ氏が北朝鮮を先制攻撃することは考えにくいが、金正恩がさらに跋扈し、ロシアと密着していけば、米国は巨大な力を背景に中国に圧力をかけ、金正恩政権を打倒し、レジュムチェンジを図ろうとする可能性もある。中国政府も、東アジアの安定とパワーバランスを破壊している金正恩に不満を抱いているという徴候は至るところで確認できる。
トランプ政権は、ウクライナ戦争の早期終了という大きな課題を解決するためにも、中国との関係を再構築するためにも、北朝鮮問題を放置することはできない。
北朝鮮政権を延命させるか、温存するかの判断を求められるはずだ。その場合「力」の行使もありうる。トランプ政権の国務長官に就任するマルコ・ルビオ氏は、金正恩を軽蔑、「野良犬を捕獲するチームの助手さえも務まらない人間だ」と発言したことがある。政権で国家安全保障担当の大統領補佐官となるマイク・ウォルツ氏は、かつて北朝鮮問題解決のためには先制攻撃も必要と発言したことがある。
トランプ政権誕生とともに迎える2025年、朝鮮半島は、よくも悪くも、これまでとは違う大きな転機を迎えるのではないか。

《おかべ よしひこ》
1973年兵庫県生まれ。博士(歴史学)、博士(経済学)。神戸学院大学経済学部教授、ウクライナ研究会(国際ウクライナ学会日本支部)会長。
2025年1月20日号 週刊「世界と日本」第2285号 より
トランプ政権 激変する世界
「ウクライナ和平の実現」―日本の備えは―
神戸学院大学 経済学部教授
岡部 芳彦氏
昨年は、幸運にも、2回、ウクライナを訪問することができた。まず、8月末から9月の中旬まで、首都キーウのほか、西ウクライナのリヴィウ、イヴァノフランキウシクにも立ち寄った。2022年2月24日、ロシアによるウクライナ侵略が始まって、日本の外務省によって、ウクライナには海外安全情報の「退避勧告」が出され、研究者にとっても公に渡航することが出来なくなった。2024年2月に東京で開催された日本ウクライナ経済復興推進会議を契機として、復興などに携わる企業団体関係者が1週間程度、キーウを訪れることが特例として認められた。筆者は、これからウクライナを訪れる復興関係者の警備業務に参入しようとする日本企業のアドバイザーとしてキーウを訪れた。一昨年も個人的に渡航したが、戦争が始まって「公式」にウクライナを訪れたのは初めてである。その日程は、1週間ほどで終了し、一度キーウを出て、その後は、私的に2週間近く現地に滞在した。
一見、戦争前と同じような日常が広がるキーウだが、到着した日から3日続けて、夜中に空襲警報がなった。真夜中に2回鳴る日もある。首都なので防空装備が整っていると頭でわかっていても落ち着いて眠ることができない。ロシア軍によるウクライナ国民に向けた計画的な嫌がらせといっても過言ではない。単なる嫌がらせで済めばいいが、多大な被害も出ている。
ちょうど西部のリヴィウに到着した日、悲劇は起きた。ロシアのミサイルが住宅地に着弾し、夫以外の妻と3人の娘が死亡するといういたたまれない出来事があった。着弾したのはリヴィウ駅にほど近い住宅地である。一方、その日の昼、街の中心に出かけると、人気の観光地の光景が広がっていた。一見、日本の観光地でも見かけそうな雰囲気だが、大きく異なるのは、ロシアによる発電所などへの攻撃で今年の夏はウクライナ各地で計画停電が頻発したため、その間に発電機を動かす重低音が方々の飲食店から聞こえることである。日々の生活と戦争が入り交ざった日常が、今のウクライナにはある。
史上初のウクライナ語国語辞典を編纂したボリス・グリンチェンコの名前を冠した名門のキーウ首都大学から名誉教授の称号が授与されることになり、この訪問中に、同大学の入学式に合わせて式典が催されるはずだった。しかし前日にもインフラ攻撃があり、「急な停電で入学式が中止になった。よって名誉教授授与式もできない」との連絡があった。せっかくキーウまで来ているので、略式ででもお願いできなかと問うたところ、不可との返事。手続きやセレモニーを略してまでは行わないウクライナ人の一種の完璧主義を感じる一方、今のキーウでは少し先の行事の一つ決めるのも覚束ない現実も実感した。
この訪問では、ウクライナを代表する企業家のヴィクトル・ピンチューク氏の財団が主催し、ウクライナ版ダボス会議と称されることもあるヤルタ・ヨーロッパ戦略会議、通称YES会議にも出席した。基調講演者がゼレンスキー大統領で、大統領府長官、最高会議(国会)議長、首相など政府要人が勢ぞろいするため、シェルターを兼ねた地下2階での開催で、空襲警報がなっても中断されることはない。
世界の有力政治家や政府関係者が出席する中で、ひときわ目を引いたのが ウクライナで人気の詩人で現在は従軍するセルヒー・ジャダンと元兵士や現役兵士のパネルであった。博士号を持ち、4つの外国語を操る元学者が今や最前線でドローンの操縦手をしているという。戦争前には予想もしなかったし、時にロシア兵を殺めることもあるが「なんとか自分を適応させてきた」という。兵士と生の声を聞くと、さまざまな葛藤や心の傷を負っていることが分かる。一方、自分ではどうしようもない局面に「適応」させてきたのは、兵士だけではなく、ロシアによる侵略後にウクライナ国民の誰もが感じる心情だとも感じた。
12月の初めに再度キーウを訪問することになった。現在ウクライナに行く際、日本政府が認めている経路は、ポーランド経由のみだが、今回は諸般の事情で、ワルシャワに一泊することなく、機中泊のあと、ワルシャワからポーランド東部のヘウム駅で、ウクライナ国鉄に乗り換え、家を出てからキーウまで約52時間の移動時間となった。その訪問目的は、大学だけではなく、大統領直属の教育財団関係者との会談を通じて、教育分野における復興支援や日本におけるウクライナ文化の普及に何かできることがないか糸口を探ることである。訪問を聞きつけたキーウ首都大学から再度、名誉教授の称号授与式を行うという連絡があり、今度は大丈夫かなと恐る恐る行ってみると30人はいようか、大学評議員が、すべてアカデミックガウンに学帽を着用し、円卓に鎮座している。合唱団も入場し、厳かにセレモニーが執り行われた。その後、学生たちも聴講する中、「知られざる日本ウクライナ交流史」と題して記念講演を始めてすぐ空襲警報がなった。手慣れた感じで「避難しましょう」と第一副学長が告げ、地下のシェルターに降りてみると、言われなければ、隠れ家カフェのような空間が広がっていた。10年来の友人で元国会議員の副学長は「これほどきれいなシェルターを持っている大学はキーウではうちだけだ」と胸を張った。そこには食堂や講義室も備わっている。シェルター内のホールに通されると、驚いたことにすでにスクリーンやPCが用意されており、しかも中断したスライドが投影されている。「さあ、続きをどうぞ」と副学長に促され、講演再開となった。空襲が続くキーウでは、さまざまなイベントが影響を受けている。劇場では空襲警報が鳴った場合、中断されるが必ず最後まで演じるという。それでなければチケット代を返さねばならないからだ。ウクライナの人々は、いつ、どこで起こるかわからない人為的な不確実性に備える準備ができているのだ。戦時でも普通の生活が送れるようそれぞれの立場から「適応」させてきたのである。そういえば、9月に訪問した際、リヴィウの「赤い猿」という日本語で店名が書かれたラーメン屋に行った。豚骨ラーメンを食べたが、その味は日本でも十分に勝負できそうなほど旨かった。その日は、人気YouTubeの番組取材も入っていたが、冒頭で触れたリヴィウへの空襲があった日でもある。その10時間ほどあとには、普段と変わらない日常が戻っているのも、市民が戦時下の生活に自分を適応させた結果だと感じた。
トランプ政権も誕生し、ウクライナを取り巻く環境は大きく変化するのではないかと囁かれている。一方、ウクライナ国内では、各種世論調査などで、トランプ政権によってウクライナの環境が好転するという声も少なくない。3年前、起こるはずもないと思っていた戦争が始まり、早期の降伏が必至と誰もが思ったウクライナ。しかし、その国歌が謳いあげるように「ウクライナは滅びず」、今も存在している。戦争2年目の反転攻勢の失敗など、さまざまな局面を経てきたが、次々と起こる不確実な事態に適応してきたウクライナとウクライナ人たち。我々日本人は2025年に求められるのは、彼らから学んで、目まぐるしく変わる情勢に適応し、そして不確実なことに備える覚悟なのかもしれない。

《むらた こうじ》
1964年、神戸市生まれ。同志社大学法学部卒業、米国ジョージ・ワシントン大学留学を経て、神戸大学大学院博士課程修了。博士(政治学)。広島大学専任講師、助教授、同志社大学助教授を経て、教授。この間、法学部長・法学研究科長、学長を歴任。現職。専攻はアメリカ外交、安全保障研究。サントリー学芸賞、吉田茂賞などを受賞。『大統領たちの五〇年史』(新潮選書)など著書多数。
アメリカの歴史で、連続せずに大統領を2期務めたのは、19世紀末のクローバー・クリーブランドただ一人である。その不屈の精神から、彼は「鉄の男」と呼ばれた。ドナルド・トランプがこれに続く。ただし、トランプの不屈の精神には、再選しなければ逮捕され、トランプ王朝が崩壊するとの危惧感が強く働いていたであろう。
だから、トランプ前大統領は圧勝できたのか。
共和党の大統領候補は暗殺未遂事件を乗り超え、高齢批判やタカ派批判もものともせずに、圧勝して再選を果たした。他方、民主党の大統領候補は弱い政権の継承者というイメージを払拭できず、女性擁立の効果も乏しく惨敗した。
いかにも通俗的な解説だと思われるかもしれない。しかし、これは1984年の米大統領選挙の話である。共和党のロナルド・レーガン大統領は1期目の早々に暗殺未遂事件に遭遇するが、これを乗り超えて人気を確固たるものにした。だが、彼は史上最高齢の大統領で、ソ連を「悪の帝国」と呼ぶタカ派として知られた。世界中、反核運動が展開されていた。これに対して、民主党はカーター前政権の副大統領だったウォルター・モンデールを大統領候補に選んだ。そのモンデールはジェラルディン・フェラーロ下院議員を女性初の副大統領候補にした。この戦いでレーガンは実に525人の大統領選挙人を獲得して、文字通り圧勝した。モンデールは地元のミネソタ州とワシントンDCで勝てたにすぎない。今回の大統領選挙でトランプが得た大統領選挙人は312人であり、4年前にジョー・バイデン大統領が獲得した306人と大差はない。これに比べれば、トランプ「圧勝」は大げさである。
さて、今後に目を転じよう。トランプ再選のみならず、上下両院も共和党が制した。いわゆるトリプル・レッドである。これで、誰もトランプ次期大統領を牽制できなくなるのか。もちろん、そうではあるまい。上下両院とも、共和党はわずかに多数にすぎない。しかも、米国の連邦議会議員たちに、党議拘束はない。彼らは選挙区の事情や自分の信条から、トランプの意向に反するかもしれない。 また、米建国250周年に当たる2025年には、中間選挙が待っている。もしこれで上下両院の一方でも多数を失えば、一期限りのトランプ大統領が勢いを盛り返すことは難しい。移民問題や環境問題では、リベラルな州や都市はトランプ政権に反抗しよう。
より重要なことは、2029年1月にトランプ大統領は82歳で退任するが、後任が50歳代なら30歳ほどの世代交代が生じる。これはドワイト・アイゼンハワーからジョン・F・ケネディへの世代交代(27歳)よりも、おそらく大きい。当然、大統領の世代交代は、政界や官界、財界、メディアにも大きく影響しよう。
国際情勢では、ウクライナ戦争と中東での紛争の帰趨が注目される。トランプが言うように、前者は終息に向かうのか。それとも、後者がサウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)にも飛び火して拡大していくのか。ロシアと中国、イランと北朝鮮という反米「四人組」(リチャード・ハース)が協力を強めれば、二つの紛争は一層危険に結びついていこう。
また、トランプはアメリカの優越した立場を利用して、二国間での「ディール」を好む。だが、グローバルなマルチ外交でなければ対処できない課題が、国際社会には数多く存在する。地球温暖化問題はその代表例であり、人工知能(AI)の技術規制もそうであろう。AIには巨大な潜在力と利便性があるが、暴走すれば大きな危険が待ち構えている。だが、トランプは手間暇のかかるマルチ外交には無頓着で、彼に取り入ったイーロン・マスクに至っては、規制緩和と技術至上主義の権化である。
では、日米関係はどうなるのか。トランプ大統領と石破茂首相の「相性」もさることながら、前者は「強い」指導者を好む。だからこそ、彼は「シンゾー」とはうまくいったのである。だからこそ、トランプはロシアのウラジーミル・プーチン大統領にすら好感を抱けるのである。ところが、石破首相の権力基盤は脆弱である。来年夏の参議院選挙までに、いかに日本の内政を安定させるかが、日米関係にとっても死活的に重要であろう。首相が交代するのか、世論の風向きが変わるのか、連立の枠組みが変わるのか、それとも、政権そのものが交代するのか―四つの変数の組み合わせが日本政治を規定しよう。まずは、来年3月の予算成立の駆け引きが、一つの山場であろう。ここで首相が交代し、新首相が衆参ダブル選挙を挑むといったシナリオも、あながちないわけではない。その結果次第では、自公連立政権に国民民主党や日本維新の会を迎えなければならなくなるかもしれない。
先述のように、トランプ次期大統領は「第二のレーガン」を演じ切った。「タカ派」レーガン政権の二期8年の後に待っていたのは、核戦争ではなく冷戦の終焉であった。1980年代を通じて、民主党は敗北を重ねたが、その後には中道路線に舵を切ってビル・クリントン政権を誕生させた。アメリカにしても日本にしても、歴史は一筋縄では読み解けない。
他方で、レーガンの盟友だった中曽根康弘首相は、ソ連の中距離核ミサイルのヨーロッパ配備をめぐって、「平和は不可分」と力説した。今や北朝鮮兵がウクライナで戦っている。中曽根氏の言葉は、ますます真理となりつつある。ところが、石破首相が唱えるアジア版NATO(北大西洋条約機構)どころか、NATOそのものにも、トランプは懐疑的で批判的な目を向けている。われわれがヨーロッパの安全保障に関与し、ヨーロッパをアジアの安全保障に参画させる―この協力なしに、「またトラ」の荒波は乗り越えられまい。そのためにも、防衛費の倍増や反撃能力の保有など、岸田文雄内閣での公約を、石破首相が実行できるかどうかが、試金石になろう。その上で、日本の首相は誰であれ、トランプに了解可能な日米同盟の「物語」を語れなければならないのである。

《ほさか しゅうじ》
日本エネルギー経済研究所理事・中東研究センター研究顧問。慶應義塾大学大学院修士課程修了、在クウェート日本大使館、在サウジアラビア日本大使館、中東調査会研究員、日本学術振興会カイロ研究連絡センター長、近畿大学教授等を経て、現職。日本中東学会会長を兼任。おもな著書に『ジハード主義』(岩波書店)など。
昨年10月7日、パレスチナ・ガザ地区を実効支配するイスラーム主義勢力ハマースなどが突然、イスラエルに侵入、イスラエル人や外国人約1200人を殺害、また200人以上の人質を取った。これに対しイスラエルは圧倒的軍事力で大規模反撃を開始、パレスチナでの犠牲者は今年8月半ばには4万人を超えてしまった。また、イスラエルのガザ封鎖で、ガザへの食料や医薬品搬送が滞り、ガザは今世紀最悪ともいわれる人道危機に陥っている。さらにイスラエルは最近、北の隣国レバノンへの攻撃を活発化させ、10月1日には限定的であるが、地上侵攻も開始した。
今年7月末には、ハマースの指導者、ハニーイェ政治局長が、さらに10月にはその後継者のシンワールが殺害され、また、9月にはレバノンのシーア派組織ヒズバッラーのナスラッラー事務局長が殺害された。事態は沈静化どころか、悪化の一途をたどり、戦線は、パレスチナのみならず、レバノン、イエメン、シリア、イラン、イラクなど周辺国にも拡大している。現在、米国、エジプト、カタールがイスラエルとハマースの停戦の仲介を行っているが、ほとんど進んでいない。レバノンについても、米国が調停を行っているものの、やはり効果は不透明である。
一方、ハマース、ヒズバッラー、シリアのアサド政権、イエメン・フーシー派等、いわゆる「抵抗の枢軸」を率いるイランとイスラエルの関係も緊迫している。今年4月には、イスラエルによるイランの在シリア外交施設空爆やハマース・ヒズバッラーの指導者殺害をきっかけにイランとイスラエル間で4月と10月に報復の応酬があった。現時点では、両国の報復合戦には、最悪の事態は避けたいという「自制」が見られる。しかし、大規模な戦争に発展する可能性もゼロではない。
アラブ諸国を含め、国際社会は、原則的にパレスチナ問題をイスラエルとパレスチナという2つの国家を樹立することで解決する「2国家解決」で合意しているが、肝心のイスラエルとハマースなど「抵抗の枢軸」が2国家解決に否定的である。ただし、抵抗の枢軸の立場はイランの政策に左右されがちであり、イランが2国家解決を容認すれば(実際、そうした兆候がないわけではない)、一斉に停戦に向かう可能性もあるだろう。
イスラエルの強気を支えるのは米国の支援である。米国、そして米国の主導するG7は紛争勃発以来、イスラエル支持の立場を堅持してきた。とくに米国は、国連安保理でイスラエルに不利な決議案を軒並み拒否権で否決してきた。他方、G7以外の国の多くはパレスチナに同情的であり、とりわけ民間人の犠牲者増加には強い怒りを示している。西側の一員であるスペイン、ノルウェー、アイルランドが紛争勃発後、相次いでパレスチナを国家承認したのはその顕れである。
また、ロシアや中国も、パレスチナ支持を明確にしており、このことが、中東諸国の米国離れの促進、中露への接近の要因にもなっている。日本は、国連決議などでしばしば米国と異なる対応をしているが、G7の一員、米国の同盟国として、アラブ・イスラーム諸国から親イスラエルと見なされてしまうことは要注意である。
米国の親イスラエル的立場は、民主党でも共和党でも大差ないが、大統領選でトランプが勝利すれば、イスラエルがさらに強硬な姿勢に出る可能性もある。したがって、米大統領選の結果が出るまでは、ガザ戦争の解決はない、との見方もある。
もう一つ、ネタニヤフ首相の汚職疑惑や対パレスチナ強硬派の極右勢力を含む連立政権といったイスラエルの国内事情も、イスラエルの過剰ともいえる周辺国攻撃と無関係ではあるまい。
今回の紛争は国際経済にも大きな影響を与えている。昨年10月19日には、イエメン北西部を占拠するフーシー派がパレスチナ支援を名目に紅海を航行する船舶攻撃を開始した。その後、アデン湾やアラビア海にも攻撃の手を広げ、それによってアジア・中東・アフリカ・ヨーロッパを結ぶ通商の大動脈が滞ってしまった。フーシー派は、イスラエルがパレスチナ・レバノンへの攻撃をやめないかぎり、作戦を継続すると主張しており、日本にとっても他人事ではない(実際、日本関連船舶も攻撃されている)。
また、日本への影響という意味では、原油価格も重要である。現時点では、中東において大きな衝突があると、一時的に油価が上昇することもあるが、深刻なレベルには達していない。1973年の第4次中東戦争・第1次石油危機時にあったようなパニックの再来は考えづらいが、サウジアラビアやUAEといった産油国に危機が飛び火するようなことがあれば、油価にも影響が出かねない。また、パレスチナに同情する民衆の怒りが、有効な手を打てない政権に向かうと、産油産ガス国がエネルギーを武器に用いることもありうる。
もう一つ、今回、国際社会の反対を無視して、イスラエルが、民間人を標的にする攻撃をつづけたことで、世界中で反イスラエル感情が高まったことも指摘できる。ガザ戦争以前は、イスラエルのハイテク産業やスタートアップへの注目が高く、日本政府・企業も対イスラエル投資を熱心に進めていた。しかし、今回の事件で、イスラエルへの投資が鈍化しただけでなく、イスラエル企業に対するBDS(ボイコット・投資引揚げ・制裁)運動が活発化し、イスラエルから撤退する企業も出てきた。米国や日本を含むG7内でも、イスラエル批判の声は強まっている。仮に事態が沈静化したからといって、イスラエルへの投資がそう簡単に戻ってくるわけでない。
ガザ戦争終結には、国際社会が一致団結して、解決に向けた努力を行わねばならない。しかし、世界の分断がそれを困難にしている。日本が、G7の結束を強化したり、イスラエルやアラブ・イスラーム諸国を説得したりするのは重要だが、米国の対イスラエル政策を変えさせる努力も必要になるだろう。

《ちの けいこ》
横浜市生まれ。1967年に早稲田大学卒業、産経新聞に入社。マニラ特派員、ニューヨーク支局長。外信部長、論説委員、シンガポール支局長などを経て2005年から08年まで論説委員長・特別記者。現在はフリーランスジャーナリスト。97年度ボーン上田記念国際記者賞を受賞。著書は『戦後国際秩序の終わり』(連合出版)ほか多数。近著に『江戸のジャーナリスト 葛飾北斎』(国土社)。
2024年11月4日号 週刊「世界と日本」第2280号 より
フジモリ元ペルー大統領の墓標
ジャーナリスト
千野 境子氏
1990年7月、南米初の日系大統領となったペルーのアルベルト・フジモリ氏が9月11日、86歳で死去した。天国と地獄を地で行くような波乱の生涯だった。改めてフジモリ元大統領の時代とその功罪を考える。
今も瞼に焼き付いている光景がある。大統領就任1周年を前にした91年7月末、母親ムツエさんについての産経新聞連載「ペルー遥かな道」の取材で首都リマを訪れていた私は「パラシオ(大統領官邸)でアルベルトとご飯を食べるからウステ(貴方)も来なさい」とのムツエさんの言葉に、警護の車で一緒に官邸まで行った。ペルー大統領官邸の私的部分に足を踏み入れたのは後にも先にもこの時だけだ。
夕食は既に終わり、フジモリ大統領(当時)は食堂で末子のケンジ君のためにリンゴの皮を剥き、傍らでスサナ夫人が一心にペンを走らせていた。7月28日の独立記念日兼就任1周年の大統領演説の準備中だった。
あらあら、両親の役割がアベコベじゃないと思ったが、公的な場ではまったく見せたことのない温和で家庭的な子煩悩の大統領がそこにいた。
振り返れば、この頃から2期目(95年〜2000年)の初め頃までが、フジモリ氏のもっとも輝いていた時期だった。
就任時に8000%というハイパーインフレを、国際機関を含め誰もが不可能と考えた緊縮政策の断行により収束させ、連続爆弾テロで首都の住民を恐怖に陥れていた極左ゲリラ「センデロ・ルミノソ(輝く道)」には、歴代大統領として初めて対決姿勢で臨んだ。92年9月の最高指導者グスマンの逮捕に国民がどれほど歓喜し安堵したか、今では想像も出来まい。
同年4月のアウトゴルぺ(自主クーデター)と呼ぶ憲法停止措置と議会閉鎖も、大統領が自ら立憲秩序を破壊したにも関わらず、私益に明け暮れる既成政党に絶望していた国民は喝采し、非常措置支持は90%を超えた。
長引くインフレ、深まる経済危機、爆弾テロの日常化に、国民とくに貧しい大衆は救世主を待ち望んでいた。ペルー社会の非主流で無名の日系人学者フジモリ大統領の誕生は、こうした背景抜きにはあり得なかった。
しかしそこには大統領失脚の一因ともなった強権的手法の萌芽が早くもあった。強権は一概に悪とは言えない。日本大使公邸占拠事件でフジモリ氏の武力による人質救出作戦を批判するのは易しいが、ではそれ以外の解決方法はあっただろうか。ただ強権は奏功すればするほど、権力者はそれに依存し、結局は独裁となる。フジモリ氏もその道を免れなかった。
さらなる瑕疵はモンテシノス顧問の登用だ。軍人出身の弁護士で、南米コロンビアの麻薬カルテルや米中央情報局(CIA)などとの関係が指摘され、最初から政権の暗部だったが、有能ゆえに重用された。
大統領になったものの軍に基盤を持たず、非白人が最高司令官になるのを良しとしない軍にクーデターの企みさえあったことを考えれば、モンテシノスの存在は心強かっただろう。
しかし最初は虎の威を借りていたモンテシノスは、やがて国家諜報局(SIN)を操り、最後は大統領の首をとるモンスターと化した。
2000年9月14日夜、モンテシノスが議員の買収工作をする生々しい現場ビデオが公表され、衝撃が走った。フジモリ氏は直ちにSIN解体を発表したが、そんな程度で事態は収まらなかった。
11月16日、フジモリ氏はブルネイでのAPEC首脳会議出席の帰途、日本に立ち寄り議会に辞表を提出した。しかし議会は受理せず、21日に大統領罷免を可決、フジモリ政権は2期4カ月を以って終焉したのだった。
約5年の日本滞在の後、05年11月に大統領選再出馬を目指し密かに離日した。直前のある日、会見に呼ばれた。「ペルー情勢はイイです」と終始笑顔で、何時にない高揚感も漂い、何があったのだろうと怪訝に感じたが、間もなくチリ経由でペルー入国を図り拘束されたことをニュースで知った。
本当にそんな方法で帰国出来ると思ったのか。情勢判断の甘さと楽天家ぶりに驚いた。
もっとも状況がどうあれ、それに左右されない楽天性は、私にはフジモリ氏の天性のように思える。ペルー移送後、大統領時代の市民虐殺事件で禁固25年が確定し、2017年10月に収監先の警護施設で会った際も、恩赦が近いと、明るく意欲満々だった。
大統領として危機の時代を立て直したという自負と、職が未完に終わった無念さが、生きるエネルギーの源ではなかったかと思う。
フジモリ氏の大統領としての功罪は、牽強付会と言われそうだが、功の中に罪があり、罪の中に功がある。
ただ明らかなことは、今日のペルーはフジモリ時代に築かれた基礎の上にあるということである。11月17日からリマでAPEC首脳会議が開かれる。フジモリ政権が太平洋国家の一員となることを目指してAPECに加盟希望を表明し、1998年にロシア、ベトナムとともに認められたからである。
今年は日本人のペルー移住125周年である。フジモリ氏の両親も熊本から移住し、1938年7月に長男フジモリ氏が生まれた。ペルーの日系人は6世代20万人を数え、ブラジルに次ぐコミュニティを誇る。しかし日系人の政界進出にフジモリ氏がアクセルとブレーキ両方の役割を果たした点は否めない。
また昨年は日本とペルーの外交関係樹立150年だった。中国がペルーをはじめ中南米に地歩を広げ、存在感の増した今こそ、本当は日秘関係の強化が必要であるにも関わらず、日秘関係もフジモリ氏によって近くなり、フジモリ氏によって遠くなった気がするのは、私だけだろうか。
言い換えればフジモリ氏はそれほど大きく強烈な存在だった。
大統領府はその死を悼み、ペルーは3日間の喪に服した。報道によれば、一般公開されたフジモリ氏の棺には数千人からの多くは庶民たちが追悼に長蛇の列を作り、ミサが行われた国立劇場周辺では「チーノ」「チーノ」とフジモリ氏を惜しむ声が聞かれたという。一方で「反フジモリ」もなお健在で、分断対立の克服はペルーでも課題だ。
今はフジモリ氏が安らかに眠りにつくのを祈るのみである。

《いとう とおる》
1969年広島県生まれ。中央大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程後期単位取得退学、博士。在インド日本国大使館専門調査員、島根大学法文学部准教授等を経て2009年より防衛大学校。2021年4月より現職。『新興大国インドの行動原理—独自リアリズム外交のゆくえ』、『インドの正体—「未来の大国」の虚と実』など著作多数。
インドへの注目が集まっている。いまや世界一の人口大国となり、今後3年以内には日独を抜き世界第3位のGDPとなることも確実だ。対中リスク懸念が強まるなか、次の新興大国としての期待が寄せられる。ところが、この国はどういう国なのか?驚くほど知られていない。実際に付き合ってみると、当初のイメージとのギャップの大きさにたじろぐ日本人が多い。
いくつか例を挙げてみよう。たとえば、インドと言えばIT大国で、有能な人材がたくさんいるはずだというイメージだ。インドは現在、20歳代前半の層だけで日本の総人口を超えるほど若年層が分厚く、インド工科大学(IIT)など、理工系の大学新卒者だけで年間100万人輩出するのは確かだ。しかしそのうち、すぐにコードが書ける人材はほんの数%にすぎないとも言われ、その多くが給与の高い米国に流出する。しかし残りの卒業生が、喜んで工場の生産ラインでモノづくりに携わるかというと必ずしもそうではない。プライドの高さやカーストの意識から、そうした仕事はしたくないと考える者も多い。他方で読み書き算盤さえままならない若者も依然多い。企業が進出したとき、適度な能力のある人材が安く簡単に見つかるわけではないのだ。
それでもインドへの期待の声がやまないのは、中国と同じかそれ以上の成長市場であるうえに、中国とは違い、日本などと価値や利益を共有しているはずだというイメージがある。今後徐々に中間層が増え、市場としての潜在力があるのは間違いない。しかし、インドが西側の自由民主主義的な価値を共有しているというのは幻想にすぎない。カースト制は古くから根付いた慣習だが、現在のモディ政権下では「ヒンドゥー国家」を建設しようとする運動が進み、その過程ではムスリム排除やメディア、野党、市民団体の弾圧が深刻化した。これに対し、米欧の市民社会、議会、そして政府は批判を強めている。昨年秋には、カナダと米国で、現地のシク教徒活動家を印諜報機関が殺害した、あるいはしようとしたのではないかとの疑惑が持ち上がった。事実だとすれば、国際的な秩序やルールの点でも、西側と価値を共有しているとは言いがたくなる。
もちろん、インドは選挙で政権交代の可能性があり、どんなに弾圧されても批判の声を上げ続ける市民社会の存在も健在だ。この点では、中国やロシアに比べればはるかに「まし」なのはいうまでもない。それに、価値はともかく、インドという国はかつて中国と戦火を交え、いまでも未解決の国境問題で攻勢を受けているのだから、少なくとも中国に対する脅威認識はわれわれと共有していて、その点で協力するはずだという言説がある。実際、明言こそしないものの、日米豪印4カ国の連携、「クアッド」の根底には、中国に対する警戒感があるのは間違いない。
しかし、注意しなければならないのは、中国への脅威認識自体をインドが抱いているといっても、外交・安全保障政策において、日米豪など西側と常に協調するわけではない、いやむしろ正反対の行動をとることが少なくないという点である。インドはロシアのウクライナ侵攻ヘの避難を避け、ロシア制裁に同調せず、原油や肥料を大量に購入してきた。今年もワシントンでのNATO首脳会議の最中に、モディ首相はモスクワを訪問してプーチンと熱い抱擁を交わし、結束をアピールしてみせた。10月に予定されるロシアでの拡大BRICS首脳会合にもモディは出席を約束している。
なぜなのか。端的に言えば、中国からの脅威を実際に受けている場の違いである。日米豪は海洋国家として東シナ海や南シナ海での中国の威圧的行動に懸念を抱いている。しかし、インドが感じる脅威は海だけではない。クアッドのなかでインドだけが、陸上で中国と向き合わねばならない大陸国家でもある。2020年の国境衝突以降、中国はインドの主張する実効支配線に入り込んだままだ。さらに西にはパキスタンという中国と蜜月関係を構築した伝統的な敵対国が存在する。そんななかで、パキスタンの向こう側にあるイランとアフガニスタンはインドにとって本来味方につけなければならないパートナーだが、米国はアフガンから撤退してタリバン政権の復活を許し、イランに対しては制裁を科し圧力を強める。ミャンマー軍政やバングラデシュのハシナ政権に対しても、米欧は批判的だ。インドは、いくら海洋において日米豪が味方に付いているといっても、ユーラシア大陸においては四面楚歌状態にあると感じている。だからこそ、ロシアという伝統的な友好国を失うわけにはいかないのである。
加えて、インドは先進国ではない。モディ首相は独立後100年となる2047年までの先進国入りを目標に掲げるが、そのためには西側のルールや秩序に唯々諾々と従ってはいられない。だからこそ、エネルギー・食糧価格が高騰するなか、自らを「グローバルサウス」に位置づけ、ロシア産の原油や肥料を爆買いすることで国民生活を支え、経済成長を維持しようとしたのである。気候変動問題、WTOやインド太平洋経済枠組み(IPEF)など貿易分野でのルール形成においても、インドは西側先進国とは利害が真っ向から対立する。
しかしながら、中国の権威主義と覇権主義的な傾向への懸念、ならびに日本の人口減少に伴う相対的な国力の低下という現実を踏まえると、労働・消費市場としても、外交・安全保障のパートナーとしても、中国とは異質の新興大国インドと付き合わないという選択肢はありえない。西側とはさまざまな違いがあることを認識しつつ、いまのうちに企業も国もインドに入り込み、インドにとって必要不可欠な存在になることが重要だろう。すでに米国は戦闘機のエンジン製造や半導体工場建設に乗り出した。そうすることで、既存の価値や制度に沿った行動を促す。インドと付き合う際には、そうした長期的な視野に立った戦略が求められる。

《せ てるひさ》
政治学者、九州大学大学院比較社会文化研究院教授。1971年福岡県生まれ。英国シェフィールド大学大学院政治学研究科哲学修士(M.Phil)課程修了。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程修了。博士(法学)。著書に『リベラリズムの再生』(慶應義塾大学出版会)、『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』(集英社新書)、『本当に日本人は流されやすいのか』(角川新書)などがある。
主人公ではなくなった一般国民
現在、「草の根保守」の日本人、つまり特定のイデオロギーなど持たない大多数の普通の日本人でも日本の現状や将来に不満や不安を抱いている。かつて日本は「一億総中流」と言われた。しかし今は昔だ。給料は上がらず職場のブラック化も止まらない。政治は頼りにならない。人手不足だというから勤労者を大切にし、正社員化や賃金引上げを図ってくれるかと期待しても、政治家は低賃金の外国人労働者を大量に入れるぞと言い出す始末だ。「外国人に選ばれる日本を作るべきだ」などとしたり顔で述べる輩も跋扈している。
日本の経済や政治の主人公は日本の一般庶民ではなかったのか?
主人公はグローバルな投資家や企業
1990年代半ば以降、日本を含む先進各国では新自由主義(小さな政府主義)に基づき、グローバル化路線がとられてきた。「グローバル化」とは「国境の垣根をできる限り引き下げ、ルールや制度、文化、慣習などを共通化し、ヒト、モノ、カネ、サービスの流れを活発化させる現象、およびそうすべきだという考え方」だと言える。
グローバル化路線は先進各国に深刻な社会問題を生じさせた。国内の経済的格差の拡大、民主主義の機能不全、国民意識の分断などである。背景にあるのは、まさに各国の政治経済の主人公が一般国民からグローバルな投資家や企業関係者に変化したことだ。
グローバル化以降、国境を越えて資本を動かす力を持つグローバルな投資家や企業の政治的影響力が、各国の一般国民よりも非常に大きくなった。グローバルな投資家や企業は、各国政府に対し、自分たちが稼ぎやすい環境を準備しなければ資本を他所へ移動させるぞと圧力をかけられるようになったからだ。「人件費を下げられるよう非正規労働者を雇用しやすくする改革を行え。さもなければ生産拠点をこの国から移す」「法人税を引き下げる税制改革を実行しないと貴国にはもう投資しない」などと要求できるようになったのだ。
グローバル化以降、各国ではグローバルな投資家や企業の要求を受けた制度や政策が数多く作られ、社会のあり方が富裕層に有利になる一方、庶民層には不利になり、経済的格差が拡大した。政治的には、庶民層の声が、グローバルな投資家や企業関係者に比べ各国政府に届きにくくなったという点で民主主義の機能不全だと言える。加えて、グローバル化推進策から利益を得る層と、そうでない庶民層との意識面での分断や対立も招いた。
大多数の日本人の望みは「グローバル化」ではなく「国際化」
この状態の改善のために、私が日本でまず必要だと思うのは「グローバル化」と「国際化」の区別である。現在、「グローバル化」批判は非常に難しい。グローバル化を批判すれば、外国や外国人との各種交流をすべて否定していると誤解され、「排外主義」「極右」などのレッテルを周囲から貼られる恐れがあるからだ。そのため大方の人はグローバル化批判を控えてしまい、ずるずるとグローバル化路線が続くこととなる。
外国や外国人との交流の仕方は、当然ながらグローバル化だけではない。例えば「国」の役割を重視する「国際化」型の交流もあり得る。ここで「国際化」とは「国境や国籍は維持したままで、各国の伝統や文化、制度を尊重し、互いの相違を認めつつ、積極的に交流していく現象、およびそうすべきだという考え方」だと言える。
現在の日本人は「グローバル化」と「国際化」のどちらを好むだろうか。それを調べるため、私の研究室では2023年12月に両者をめぐる質問紙を作成し、社会調査会社に委託し、全国約300名の18歳〜70代の成人を対象に調査を実施した。調査の際には、いずれの選択肢が「グローバル化」型、「国際化」型に当たるのかは回答者に示していない。設問や回答の一部を紹介したい。
例えば、次の二タイプの「外国や外国人との交流の仕方」のうち、どちらが自分の望ましいと思う交流に近いかを尋ねた。タイプ①は「国境線の役割をなるべく低下させ、ヒトやモノなどが活発に行き交う状態を作り出し、様々な制度やルール・文化・慣習を共通化していく交流」(「グローバル化」型)であり、タイプ②は「国境線は維持したままで、また自国と他国の制度やルール・文化・慣習などの様々な違いも前提としたうえで、互いに良いところを学び合う交流」(「国際化」型)である。その結果、タイプ①の「グローバル化」型を選んだのは48名(16%)のみで、残りの252名(84%)はタイプ②(「国際化」型)を選択した。
経済政策についても尋ねた。「あなたが考える日本の望ましい経済政策の基本方針は、次のうちどちらに近いですか?」というもので、選択肢は以下の二つだ。①「日本経済をグローバル市場の中に適切に位置づけ、投資家や企業に投資先として選ばれやすい日本を実現すること」(「グローバル化」型)、②「日本国民の生活の向上と安定化を第一に考え、国内に多様な産業が栄え、さまざまな職業の選択肢が国内で得られるようにすること」(「国際化」型)。①はまさに現行の経済政策である。②は庶民の生活の充実を図る路線である。こちらは適度に関税をかけることも厭わない。結果は①の「グローバル化」型を選んだ者は27%(80名)、②の「国際化」型は73%(220名)であった。
他の設問でも「多文化共生」「教育目標」「移民と国際援助」などについて同様に尋ねたが、概ね4人中3人強という多数派が「国際化」型のほうを好むという結果が得られた。
草の根の庶民が主役になれる国づくりを取り戻せ
現在の日本では「グローバル化」と「国際化」はほぼ区別されていない。それゆえグローバル化の批判は非常に難しい。「排外主義」「極右」などのレッテル貼りを恐れ、大半の人はグローバル化批判を控えるからだ。「グローバル化」と「国際化」を峻別し、建設的な議論の環境を作り、一般庶民が主人公の国づくりを取り戻すべきである。











